終了しました
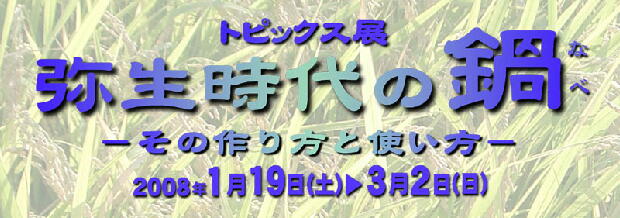

わが国の縄文・弥生土器研究は,その形態や文様の変化,それらの組み合わせの変化,そして地域性といった
視点に力点が置かれてきました。ですから,それぞれの土器はどのように作られどのように使われたのか,というシ
ンプルな問いに対して,考古学者は意外にも十分な答えをもっていなかったのです。
視点に力点が置かれてきました。ですから,それぞれの土器はどのように作られどのように使われたのか,というシ
ンプルな問いに対して,考古学者は意外にも十分な答えをもっていなかったのです。
北陸学院短期大学教授小林正史氏を中心として当館研究員も参加している研究グループ《野焼き研究会》では,
日本各地の縄文・弥生土器の製作・使用痕跡の研究プロジェクトを進めています。そしてその一環として,昨年度よ
り南関東の弥生土器の研究を始めました。とくに通常「甕(かめ)形土器」とよばれる“深鍋(ふかなべ)”の使用痕跡
を重点的に観察することでおもしろい事実が見えてきます。ありふれた出土遺物である土器を通して,案外見過ごさ
れてきた弥生人の暮らしの一端をどうぞご覧ください。
日本各地の縄文・弥生土器の製作・使用痕跡の研究プロジェクトを進めています。そしてその一環として,昨年度よ
り南関東の弥生土器の研究を始めました。とくに通常「甕(かめ)形土器」とよばれる“深鍋(ふかなべ)”の使用痕跡
を重点的に観察することでおもしろい事実が見えてきます。ありふれた出土遺物である土器を通して,案外見過ごさ
れてきた弥生人の暮らしの一端をどうぞご覧ください。


野焼きで焼かれた土器には,必ずといっていいほど「黒斑」という炭素が吸着した部分があります。黒斑を観察すれ
ば,燃料との接触の度合いや火回りが判断でき,土器の焼成技術を復元することができます。どのような焼き方をす
れば,どのような黒斑がつくのか,焼成実験の記録と実際の土器を対比してご覧ください。
ば,燃料との接触の度合いや火回りが判断でき,土器の焼成技術を復元することができます。どのような焼き方をす
れば,どのような黒斑がつくのか,焼成実験の記録と実際の土器を対比してご覧ください。
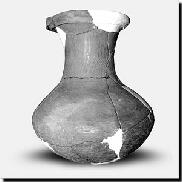
縄文土器は開放型野焼きで作られましたが,西日本の弥生土器は,弥生時代のはじめから覆い型野焼きを採用し
ました。南関東の弥生土器は,最初は開放型野焼きでしたが,やがて覆い型野焼きが採用されます。それはいつの
ことだったのでしょうか,きっかけは何だったのでしょうか?
ました。南関東の弥生土器は,最初は開放型野焼きでしたが,やがて覆い型野焼きが採用されます。それはいつの
ことだったのでしょうか,きっかけは何だったのでしょうか?

さてこの二つの土器,大きさが違うだけに見えますが…,右は炊飯に使われた痕跡がはっきりしていました。全国
的な傾向として,3〜4リットルを境におかず用と炊飯用の作り分けがなされたらしいことがわかってきています。南
関東でもそれは確かめられるのでしょうか?
的な傾向として,3〜4リットルを境におかず用と炊飯用の作り分けがなされたらしいことがわかってきています。南
関東でもそれは確かめられるのでしょうか?


弥生時代中期末より,側面から加熱をうけてススが円形に酸化した痕跡(矢印部分)をもつ深鍋が出現します。こ
の痕跡は,炊飯の終わりに蒸らし調理が行われていた痕と考えられます。現代東南アジアの蒸らしが行われた鍋と
比較してみてください。
の痕跡は,炊飯の終わりに蒸らし調理が行われていた痕と考えられます。現代東南アジアの蒸らしが行われた鍋と
比較してみてください。


この研究プロジェクトに欠かせないのが,東南アジアや南アジアの稲作農耕民における土鍋の製作法や使用法の
調査でした。そういった民族誌調査と弥生土器に残された種々の痕跡の詳細な調査,相互の比較研究と各種の実
験,それらを総合して研究を進めていきます。今回の展示では,民族誌調査の実例を写真と実物の土鍋でご覧いた
だきます。
調査でした。そういった民族誌調査と弥生土器に残された種々の痕跡の詳細な調査,相互の比較研究と各種の実
験,それらを総合して研究を進めていきます。今回の展示では,民族誌調査の実例を写真と実物の土鍋でご覧いた
だきます。
1「稲作農耕民の土器作り民族誌の比較研究」庄田慎矢(東京大学)
2「稲作農耕民の薪と土鍋による調理民族誌」小林正史(北陸学院短期大学)
3「南関東地方の弥生土器の野焼き方法と調理方法」渡辺修一(千葉県立中央博物館)
2008年2月10日(日)13:00〜16:00
千葉県立中央博物館1階講堂(定員200名・先着順・入場無料)
お問い合わせ:中央博物館歴史学研究科 043-265-3992