 |
 |
 |
「昆虫採集は悪いことだ」と言う人がいるかもしれません。ただ虫を殺すだけならそう言われてもしかたがありません。しかし、昆虫を採集して標本にし、このことを通じてわたしたちが、もっと自然を知ることができたら、昆虫やほかの生物にとってずっと役にたつことができるはずです。 昆虫はヒトが採っただけでは絶滅したりはしません。 標本を作ってくわしく観察しなければわからないことがいっぱいあります。それを学ぶことが標本作りの目的なのです。昆虫をただ採集するだけでは“虫を殺した” と批判されてもしかたがありません。 このページでは、価値のある標本を作るための道具や方法をわかりやすい動画で紹介します。 各項目の画像をクリックすると動画が開きます。 |
||
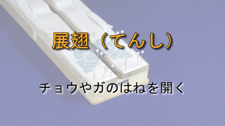 |
チョウやガの仲間は、はねを開いた状態の標本をつくって、模様がよく見えるようにします。 |
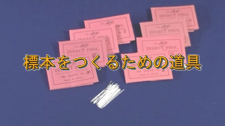 |
標本を作るためには、虫のからだのつくりに合わせていろいろな道具をつかいます。 |
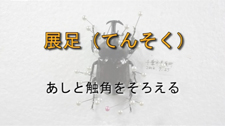 |
甲虫や、カメムシ、セミ、バッタなどで大きめのものは展足板であしと触角を整えます。 |
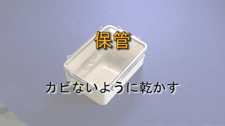 |
採集した虫をすぐに標本にできないときは、こわれたりカビたりしないように保管しましょう。 |
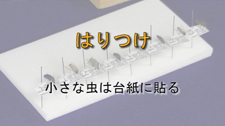 |
小さな虫や、針のさせない虫は、綿の上であしや触角を整えて乾かし、台紙にはります。 |
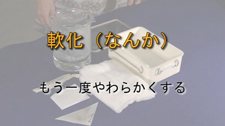 |
いったん乾燥した虫を標本にするときは、もう一度やわらかくします。これを軟化といいます。 |
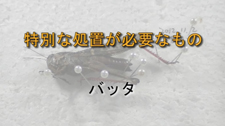 |
バッタ、コオロギなど内臓の多いものは腐りやすいので、やわらかいうちに内臓を取り除きます。 |
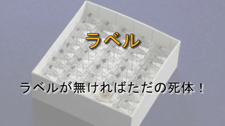 |
ラベルはその虫に関するたいせつな情報です。ラベルが無い標本はただの虫の死体です。 |
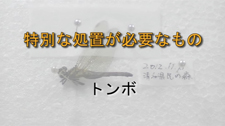 |
トンボの腹部は折れやすいので、前足のつけねから後ろに向かって細い枯れ草の芯をさし込みます。 |
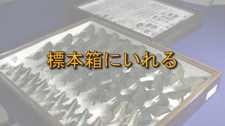 |
昆虫標本はほうっておくと、カビたり、害虫に食べられたりするので、標本箱に入れましょう。
|
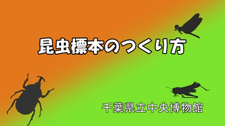 |
こちらでは、全体の動画を通しで見ることができます。 【動画28分03秒】 |
 |
【昆虫標本作製キットのご案内】ここで紹介した動画を収録したDVDを含む教材キットを貸し出します。 詳しくはこちら。 |