 |
下総香取ヶ浦 明治末期
佐原市津宮河岸を利根川から見た図で、
通運丸が上流から下ってくるところ。当時
は、現在の利根川・北浦・外浪逆浦(そと
なさかうら)を含んだ地域を「香取ヶ浦」
と通称していた。左上に『万葉集』巻十一
に載る柿本人麿の歌がある。
おほふねのかとりうみにいかりおろし
いかなるひとかものおもはさらん
|
 |
水郷の情趣 大正末〜昭和初期
岸辺にはあやめ、川を行くサッパ舟には、
水車(みずぐるま)とバハとともに牛が
乗せられている。水郷の情趣、素朴で
のどかなイメージの典型である。薄いが、
向こう岸近くには遊覧船が写っている。 |
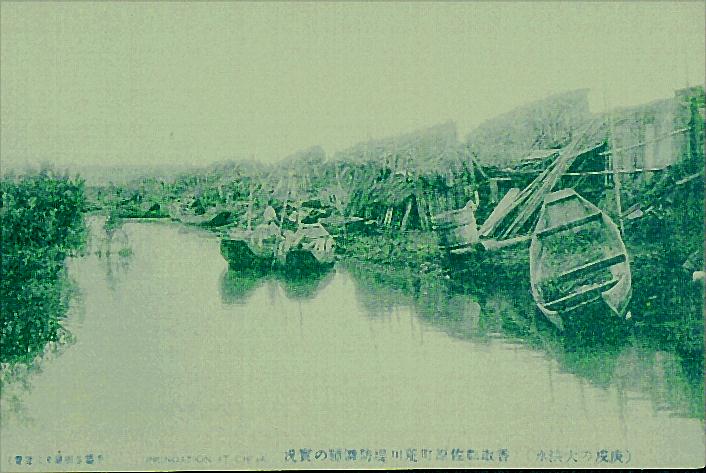 |
(庚戌の大洪水)香取郡佐原町荒
川堤防避難の実況 明治43年
庚戌は明治43年の干支。この年は全国各
地で洪水の被害があった。写真は、横利根
川と与田浦を結ぶ荒川沿いを写したもので、
川辺の家々が壊れ、サッパ舟も岸辺に打ち
上げられている様子がよくわかる。 |
 |
水郷の真中十六島の新島村 大正
末〜昭和初期
水田から水路であるエンマに水を出してい
る。田植え時期には、水の出し入れを水車
で調整した。 |
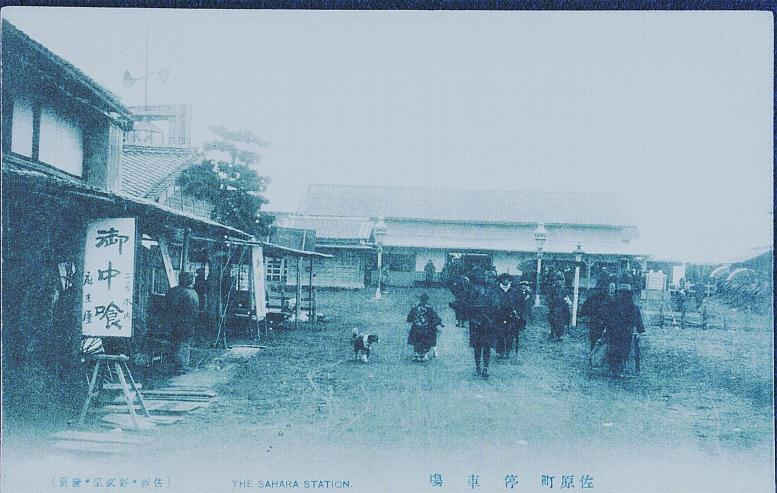 |
佐原町 停車場 明治末期
成田鉄道が佐原まで延びたのは明治31年
である。駅舎の前には人力車が並び、大き
な街灯も見える。「御中喰」の看板の店先
には、板渡しの排水路がある。 |