高瀬船とは
|
京都で有名な高瀬舟に対して、利根川で使用されていた高瀬船は、船(舟)の字だけでなくその規模も形状も異なるものである。高瀬と呼ばれる川船は全国各地の河川にあった。もともと瀬というのは水深がなく、比較的流れが速いという意味を持つ。高瀬というのは瀬高いところ、すなわち同じ瀬であってもより深みのない、水面下の地表が高いことを意味しており、おおむね河川で使用する船のことを高瀬船という。
利根川の高瀬船は関東の大河で、大量の米を運搬する船として、独自の道を歩んできた。その長さは最小でも約9.3m、最大では約26.7mもの大きさがあり、船上で生活できるようセイジ(世事、炊事)と呼ぶ船室を持つなど、1種独特な我が国最大級の川船だった。
主な高瀬船の大きさ
|
使用河川名
|
長さ(m)
|
幅(m)
|
積載量(t)
|
|
富士川
|
約13.2
|
約1.8
|
約2.25(38表積み)
|
|
高瀬川
|
約13.65
|
約1.99
|
約2.25(38表積み)
|
|
吉井川
|
約15
|
約2.1
|
約4.50(75表積み)
|
|
利根川
|
約18
|
約4.46
|
約28.8(480表積み)
|
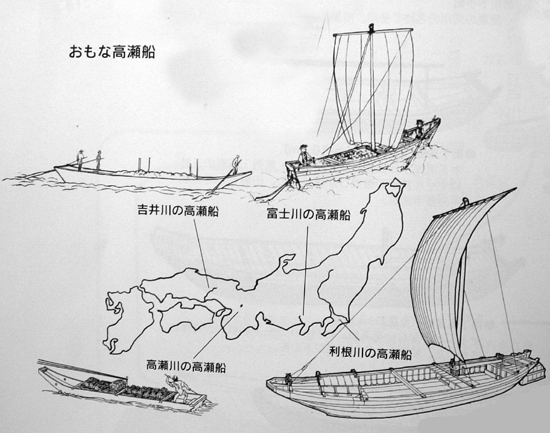
|