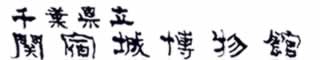
企 画 展
江戸川流域360年
会期:平成14年8月1日(木)〜9月29日(日)
関宿から端を発する江戸川はかつて利根川水運の一翼を担い、「江戸・東京への道として白帆を張った高瀬船や蒸気の煙を立ちのぼらせた外輪船通運丸が行き来しました。船が停泊する河岸が点在していた流域も時代の経過とともに大きく変貌をとげ、今日に至っています。
江戸川が誕生しておよそ360年経ちます。本企画展では江戸への大動脈であった江戸川とその流域が時代とともに河岸、戦時中は帝都防衛の拠点、戦後はベッドタウンへと変わってきた様子を紹介します。
| 1 水運の時代 |
| 2 帝都防衛の時代 |
| 3 ベッドタウン化の時代 |
| 1 水運の時代 | |
 高瀬船 |
江戸時代初期の利根川東遷と江戸川開削により関東各地と大消費地江戸が利根川及びその支流で結ばれるようになりました。これにより流域各地の年貢米や農産物・商品が輸送されました。 水運の主役高瀬船 江戸時代、利根川水運の主役となったのが高瀬船です。長さは最大で30メートル近くあり、1,200俵もの米俵を積むことができる大型のものもありました。高瀬船は川の状況や流れなどの違いにより、その地域に合った船が造られました。 江戸川流域の河岸 河川交通の発達に伴い商品流通が盛んになると、それらの商品を揚げおろしする輸送の中継地が必要になります。江戸川流域にも輸送の基地として河岸と呼ばれる集落が誕生しました。 江戸川左岸にある野田は醤油醸造が盛んな所です。野田河岸には原料になる小麦・大麦・塩などが運ばれ、製品はここから船で江戸へ運ばれました。 松戸は水戸街道の宿場町でもありましたが、江戸川沿いに河岸も存在しました。銚子から利根川の布佐河岸まで船で運ばれた鮮魚は生鮮(なま)街道で松戸河岸まで陸送され、ここから再び船に積み込まれて江戸へ運ばれました。 |
| 2 帝都防衛の時代 | |
 現在は醸造会社倉庫として 使われている。 |
江戸川流域は明治の入ると軍事拠点としての色彩も見えるようになってきました。明治18年、下士官養成機関が市川国府台に移ったのを皮切りに、松戸には工兵学校、流山には糧秣廠(りょうまつしょう=軍馬の餌を保管・供給する施設)、柏や松戸に飛行場が建設されました。 流域の軍事施設 市川市:国府台陸軍病院 野戦重砲兵連隊 松戸市:松戸工兵学校 松戸飛行場 流山市:流山糧秣廠 柏 市:柏飛行場 柏陸軍病院 柏高射砲連隊 戦時下のくらし 青壮年男子が戦場へと動員され、国内での人手不足が深刻でした。柏には日立製作所と東京機器工業が進出し、軍用機の部品製造が行われました。戦局の悪化とともに労働力が不足すると、これらの工場に東葛中学、松戸高女、野田高女の一部生徒が学徒動員で働きました。 |
| 3 ベッドタウン化の時代 | |
 常盤平団地 |
江戸川流域は首都東京に近く通勤圏内で、住宅地も確保しやすかったこともあり、常盤平団地(松戸市)、豊四季台団地、光ヶ丘団地(柏市)、みさと団地(埼玉県三郷市)などが建設され、新松戸では大規模な住宅造成が行われました。 住宅団地の建設 昭和32年に光ヶ丘団地の入居抽選が東京で行われました。このことが新聞、雑誌、テレビなどにも紹介され、人々の注目を集めました。団地生活は戦後の新しい暮らしとして人々のあこがれでした。 電化製品の普及 戦後、一般庶民の高嶺の花であった電化製品も高度経済成長が進むに従って次第に手に入りやすくなりました。昭和30年当時、「三種の神器」といわれたのは、電気洗濯機、電気冷蔵庫、テレビです。 |
 常盤平団地入居パンフレット (松戸市立博物館蔵) |
|
(敬称略)
伊原千代隆 須賀健一 森栄一 山口勘太郎
国土交通省関東地方整備局江戸川工事事務所 国土交通省国土地理院 彩流館 境町歴史民俗資料館 市立市川歴史博物館 関宿町役場 台東区立下町風俗資料館 千葉県立大利根博物館 千葉県立現代産業科学館 千葉県立中央博物館 土浦市立博物館 流山市立博物館 野田市立中央小学校教育史料館 野田市立東部小学校 船橋市西図書館
Copyrightc©2005 Chiba Prefectural Sekiyado-jo Museum. All rights reserved.