
私たちが暮らしている千葉県は,古くから多くの人々がさまざまな歴史と文化をはぐくんできました.これらの人々
の生活の跡は,今日では地中に埋もれ“遺跡”となって残されているものもあり,発掘調査によって私たちの眼の前
に現れてきます.
の生活の跡は,今日では地中に埋もれ“遺跡”となって残されているものもあり,発掘調査によって私たちの眼の前
に現れてきます.
千葉県では年間450件以上の発掘調査が行われ,その成果を整理・分析すると原始・古代の人々が遺した文化が
よみがえってきます.今回の展示は,できるだけ多くの皆様に貴重な文化遺産を御覧いただくため,県内の多くの調
査研究機関と博物館が共同で企画いたしました.展示された考古資料のなかから先人の生活や文化の一端に触
れ,房総の歴史を実感していただければ幸いです.
よみがえってきます.今回の展示は,できるだけ多くの皆様に貴重な文化遺産を御覧いただくため,県内の多くの調
査研究機関と博物館が共同で企画いたしました.展示された考古資料のなかから先人の生活や文化の一端に触
れ,房総の歴史を実感していただければ幸いです.
主催 財団法人千葉県教育振興財団
財団法人千葉市教育振興財団埋蔵文化財調査センター
財団法人山武郡市文化財センター
財団法人印旛郡市文化財センター
市原市教育委員会
木更津市教育委員会
船橋市教育委員会
千葉県立房総のむら
千葉県立安房博物館
千葉県立関宿城博物館
八千代市立郷土博物館
芝山町立芝山古墳・はにわ博物館
千葉県立中央博物館
後援 千葉県教育委員会



高原山遠景 黒曜石製の石器
この遺跡は,平成17年7月に千葉県立中央博物館職員によって発見された遺跡です.遺跡は黒曜石の原石が露
出している標高千メートル以上の尾根上にあります.ここからは,後期旧石器時代の石器が黒曜石原石に混じって
たくさん散布している場所が何か所も見つかっています.今回の展示には昨年度発見された3万年以上前の石器を
中心に,千葉県立中央博物館職員の分布調査によって採集された資料も織り交ぜてあります.高原山の黒曜石は
おもに関東地方東部にある旧石器時代の遺跡から見つかっています.下総台地というわが国屈指の狩り場を駆け回
った旧石器時代人が,定期的に高原山を訪れて,黒曜石を採取していたことがわかります.
出している標高千メートル以上の尾根上にあります.ここからは,後期旧石器時代の石器が黒曜石原石に混じって
たくさん散布している場所が何か所も見つかっています.今回の展示には昨年度発見された3万年以上前の石器を
中心に,千葉県立中央博物館職員の分布調査によって採集された資料も織り交ぜてあります.高原山の黒曜石は
おもに関東地方東部にある旧石器時代の遺跡から見つかっています.下総台地というわが国屈指の狩り場を駆け回
った旧石器時代人が,定期的に高原山を訪れて,黒曜石を採取していたことがわかります.



第3文化層の石器 第4文化層の石器(高原山産黒曜石製)
旧石器時代全般にわたって,6つの文化層の石器群が出土しました.石器出土総点数は1,469点で,29か所の石
器集中地点が検出されました.第2文化層はナイフ形石器を主体とし,信州産と思われる透明度が高い黒曜石が多
く用いられています.第3文化層は東北地方産と思われる良質の硬質頁岩(こうしつけつがん)を用いた大型のナイ
フ形石器が出土しており,第4文化層はナイフ形石器・角錐状石器(かくすいじょうせっき)を主体とし,漆黒で栃木県
高原山産と思われる黒曜石を用いています.
器集中地点が検出されました.第2文化層はナイフ形石器を主体とし,信州産と思われる透明度が高い黒曜石が多
く用いられています.第3文化層は東北地方産と思われる良質の硬質頁岩(こうしつけつがん)を用いた大型のナイ
フ形石器が出土しており,第4文化層はナイフ形石器・角錐状石器(かくすいじょうせっき)を主体とし,漆黒で栃木県
高原山産と思われる黒曜石を用いています.



第117号土壙(どこう) 第154号住居跡
鹿島川中流域の台地上にある遺跡です.縄文時代では中期加曽利E2・E3式期が主体となります.この時期の住
居では地床炉(じしょうろ)の他に土器を埋設したものや土器片で囲ったものが検出されています.「子ピット」のある
小竪穴も特徴的な遺構です.
居では地床炉(じしょうろ)の他に土器を埋設したものや土器片で囲ったものが検出されています.「子ピット」のある
小竪穴も特徴的な遺構です.




縄文土器 古代の土師器・須恵器
船橋市・八千代市の境を流れる桑納川水系の川底から,縄文時代後期~晩期と古代の土器等が大量に発見され
ました.桑納川遺跡群の発掘調査は,まだ始まったばかりで不明な点が多いのですが,隣接する台地には同時期
の遺跡が存在しており,こうした遺跡との関係が注目されます.なお,本遺跡は,一般の方によって平成17年度に新
たに見つかった遺跡です.
ました.桑納川遺跡群の発掘調査は,まだ始まったばかりで不明な点が多いのですが,隣接する台地には同時期
の遺跡が存在しており,こうした遺跡との関係が注目されます.なお,本遺跡は,一般の方によって平成17年度に新
たに見つかった遺跡です.



288号墓出土土器 201号墓出土ガラス玉
弥生時代後期~終末期にかけて営まれたムラの跡が見つかり,居住域と墓域が明らかになりました.後期中葉の
墓域では,周溝内埋葬施設5基を伴う方形周溝墓(ほうけいしゅうこうぼ)が検出され,多くの壺形土器のほか,ガラ
ス玉と銅釧(どうくしろ)が副葬品として出土しました.終末期の竪穴住居跡と方形周溝墓からは地元の土器に混ざ
って東海地方の土器が見つかっています.古墳出現前夜の有力者の成長と外来系土器の示す動向の関わりを示唆
する重要な資料です.
墓域では,周溝内埋葬施設5基を伴う方形周溝墓(ほうけいしゅうこうぼ)が検出され,多くの壺形土器のほか,ガラ
ス玉と銅釧(どうくしろ)が副葬品として出土しました.終末期の竪穴住居跡と方形周溝墓からは地元の土器に混ざ
って東海地方の土器が見つかっています.古墳出現前夜の有力者の成長と外来系土器の示す動向の関わりを示唆
する重要な資料です.
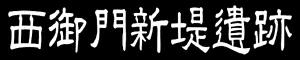


16号住居跡遺物出土状況 出土したミニチュア土器
印旛沼南岸に位置する古墳時代前期の集落跡です.住居跡などから80点に及ぶミニチュア土器が出土しました.
ミニチュア土器は非常に丁寧に作られ,孔のあけられたものも見つかっていることから,ムラの中で行われた祭りな
どで使用されたものと考えられます.
ミニチュア土器は非常に丁寧に作られ,孔のあけられたものも見つかっていることから,ムラの中で行われた祭りな
どで使用されたものと考えられます.



遺跡全景 ミニチュア土器出土状況
C区では,縄文時代~古墳時代中期までの集落跡が見つかりました.縄文時代では,北側斜面に大量の土器や
石器が廃棄されていたことが確認されました.また,弥生時代中期~古墳時代中期までの竪穴住居150軒以上と古
墳時代後期の円墳2基が調査されました.古墳時代の住居跡は,B区と比べて前期が少なく中期が多いのが特徴
です.
石器が廃棄されていたことが確認されました.また,弥生時代中期~古墳時代中期までの竪穴住居150軒以上と古
墳時代後期の円墳2基が調査されました.古墳時代の住居跡は,B区と比べて前期が少なく中期が多いのが特徴
です.



古墳時代の祭祀遺構 調査風景
集落跡の南端に古墳時代中期中葉~後葉にかけて祭祀(さいし)行為が行われた跡が発見されました.須恵器
(すえき)の甕(かめ)の周りに土器類がまとまって置かれ,破片もその下から密集して出土しました.また,土器の
間からは膨大な点数の石製模造品や鉄製模造品・土製模造品などが出土しました.
(すえき)の甕(かめ)の周りに土器類がまとまって置かれ,破片もその下から密集して出土しました.また,土器の
間からは膨大な点数の石製模造品や鉄製模造品・土製模造品などが出土しました.
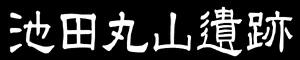


遺跡全景 須恵器坏(つき)身
大網白里町北西部の台地上にある古墳時代後期~平安時代にかけての集落跡です.今回紹介する2号住居跡
は,7世紀代につくられた竪穴住居跡です.ここからは,在地の土師器(はじき)とともに畿内系の土師器や東海産の
須恵器など,他地域から持ち込まれた土器類や,鉸具(かこ)・鉄鏃(てつぞく)・鎌・刀子(とうす)などの鉄製品,玉
類,海産の貝,鉄滓(てつさい)など,多彩な遺物がまとまって出土しました.
は,7世紀代につくられた竪穴住居跡です.ここからは,在地の土師器(はじき)とともに畿内系の土師器や東海産の
須恵器など,他地域から持ち込まれた土器類や,鉸具(かこ)・鉄鏃(てつぞく)・鎌・刀子(とうす)などの鉄製品,玉
類,海産の貝,鉄滓(てつさい)など,多彩な遺物がまとまって出土しました.
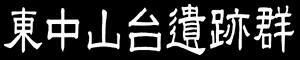

船橋市の南西部に位置し,東京湾を望む台地上に15~16世紀に営まれた中世後半の集落跡です.(36)地点で
は,地面を2m近く掘り下げて土地造成が行われており,東西約24m・南北約48mの屋敷区画が造られていまし
た.遺物は東海地方の瀬戸・美濃窯や常滑窯の焼物,中国産の磁器,土製の鍋・擂鉢(すりばち)や火鉢,銭貨な
ど,中世の人々の生活感あふれる日常品が数多く出土しています.
は,地面を2m近く掘り下げて土地造成が行われており,東西約24m・南北約48mの屋敷区画が造られていまし
た.遺物は東海地方の瀬戸・美濃窯や常滑窯の焼物,中国産の磁器,土製の鍋・擂鉢(すりばち)や火鉢,銭貨な
ど,中世の人々の生活感あふれる日常品が数多く出土しています.
| 【ミュージアムトーク】 |
| 開催期間中,以下の日程でミュージアムトーク(展示解説会)を行います. 1月25日(金)・2月1日(金)・2月3日(日)・2月11日(月・祝)・2月14日(木) いずれも14:30~15:00 また,ミュージアムトークの開催日以外でも,考古学の専門スタッフができるだけご質問等にお答えいたしますので,入場券売り場横の総合案内所または1階学習情報センターまでお気軽に声をおかけください. |
| 【関連行事】 |
| ● 千葉県遺跡調査研究発表会 詳細はこちら 1月27日(日) 10:00-15:30 事前申込・抽選200名 |
| ● 講演会「炭素14年代測定と縄文研究」 詳細はこちら 2月24日(日) 13:30-15:30 当日先着200名 |
| ● ステップアップ体験講座「勾玉づくり/鹿角製品づくり」 2月11日(月祝) 10:00-12:00と13:30-15:30の2回 当日先着各30名・材料費実費 |
| ● 「本物の土器にさわってみよう!」 詳細はこちら 会期中の土・日・祝日に開催 各日11:00-12:00と14:00-15:00の2回 事前申込不要 |