| 房総発掘ものがたり━各展示コーナー解説書━ 君津 黄泉がえり ━ 鹿島台遺跡〈A区) ━ <千葉県教育振興財団作成資料による> |
|
| ■所在地 | |
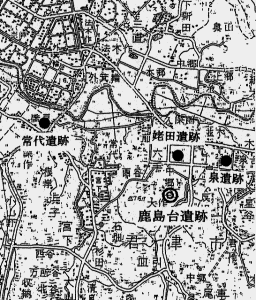 鹿島台遺跡は,君津市街地から約2.5km山側に入った小糸川中流域の標高40〜70mの起伏に富んだ台地上に位置している。 西に約2kmの沖積低地に立地する常代遺跡からは,弥生時代の大規模な方形周溝墓群や稲作農耕を裏付ける堰などの利水施設が調査され、鹿島台遺跡との関連が注目される。 また、古墳時代中期から後期にかけては、鹿島台遺跡の北側に隣接する低地上に、泉遺跡や姥田遺跡がみられる。 |
|
| ■遺跡の概要 | |
| 弥生時代: A区からは,中期の再葬墓1基と方形周溝墓16基・竪穴住居跡1軒などが検出された。 特に,再葬墓は1基の土坑墓内から3点の壷形土器が出土した。房総における再葬墓の分布範囲南端に位置する資料として注目される。 古墳時代: 古墳時代後期の円墳(4号墳)と中期から後期にかけての古墳の周溝2基及び埋葬施設が検出されたが,竪穴住居跡は営まれていない。 後期の円墳は,墳頂部に5基の埋葬施設が一部重複するような状況で検出された。埋葬施設が複数墳頂部平坦面に設けられるのは、中期以前に一般的にみられるもので、後期の古墳としては特異な状況である。 また,SMOOlの埋葬施設であるSKO32からは,3,000個以上の滑石製臼玉とともに、勾玉・管玉などが出土した。この施設からは,従来針と称される鉄製品が検出された。出土例が少なく,用途の解明とともに注目される。 |
|
 遺跡全景 |
|
| ■展示資料 | |
 再葬墓壷 土坑内から3個体の壷が発見された。 弥生時代中期の須和田式と呼ばれる壷で,貯蔵用として使用されたのではなく,人骨を入れる骨壷のような用途に使われた。 縄文時代からの伝統である縄文を地文とした文様が主体であるが,長い頸部や全体の形態は,縄文時代にはみられないものである。 |
|
 臼玉 古墳時代中期を中心に,滑石などの加工しやすい石で鏡や剣などを模倣した石製模造品が作られた。 臼玉もその一種で,首飾りのガラス玉を真似たものである。 本例のように,一つの埋葬施設から3,000個以上の多量の臼玉が出土した例は珍しい。 |