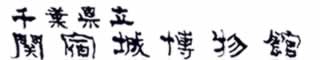
後北条氏と簗田氏〜古河公方足利義氏の家督相続と関宿移座をめぐって〜 〜島田 洋〜
カッコ内の数字は註を示す。 無断転載禁止、お問い合わせは当博物館まで。
- はじめに
鎌倉公方足利成氏の家臣簗田成助は、公方の古河移座に伴い(古河公方)関宿城を守備した(1)。以後簗田氏は古河公方の有力家臣としてその地位を高めていくことになる。天文8年に4代公方晴氏と北条氏綱の娘(後の芳春院殿)との婚姻成立を契機に、北関東への勢力伸張を狙う後北条氏は公方権力に浸透することになるが、公方権力の形骸化を目論む過程で簗田氏と対立・拮抗し、3次に及ぶ関宿合戦を経て簗田氏が関宿城を開城するまでその関係が続いた。
本稿は、5代公方義氏の家督相続と関宿移座における後北条氏と簗田氏の関係を先行研究(2)をふまえて改めて検証するとともに、両氏の関係を物語る新出史料を紹介することを目的とする。
- 後北条氏外戚化と家督相続
公方晴氏の代に簗田高助が宿老中筆頭となり、高助の娘が晴氏に嫁ぐことにより、その地位は一層強固なものになった。しかし、前述の晴氏と芳春院殿との婚姻は後北条氏による古河公方権力介入(3)への事実上の第1歩であるとともに、既に公方家と婚姻関係にあった簗田氏の地位を脅かしかねない事態でもあった。
天文20年に北条氏康は簗田晴助(高助の子)と起請文(4)を取り交わした。その内容には「奉対古河上意様、尽未来不可存無沙汰覚悟候」とあるが、「晴助御覚悟相違之儀、御表裏之儀、至于有之者、彼神罰可帰御身候」と、後北条氏の簗田氏に対する強圧的な態度が窺える。しかしその一方で「於氏康も対申晴助、不存別心所」「関宿御難儀之時、不可見離事」「晴助御出身之儀、相加世儀可申事」と述べており、後北条氏が領国支配化を推し進める上で簗田氏への対策が最大課題であることを物語る。
翌年、晴氏は高助の娘との間に生まれた正嫡藤氏ではなく、芳春院殿との間に生まれた梅千代王丸(後の義氏)に家督を譲った。この移譲は後北条氏による政変劇であり、これにより後北条氏の公方権力における外戚としての地位が強固なものになったが、一方で簗田氏はその対抗措置として公方権力の中で独自性を一層強める方向に志向したのではないだろうか。このことは後北条氏や公方にとって脅威であり、事実梅千代王丸は晴助に下野名間井郷と藤郷を宛行う(5)とともに起請文(6)を取り交わしている。そこには「はるすけにたいせられ、御とうかんあるへからす」「むニのはしりめくられ候に付てハ、出身させられへき事」などとあり、簗田氏の懐柔に腐心している。
家督相続により晴氏は公方の地位を失ったが、常陸の芹沢氏に年頭祝儀の返書(7)を発給するなどしているが、これは晴氏が非政治的存在に転化しきっていなかった(8)ことを意味する。この状況を後北条氏が認めた理由は、晴氏の背後に控える簗田氏をはじめとする公方家臣の抵抗をかわすための妥協策であり、この段階で後北条氏が公方権力に深く浸透しえない状況であった。
その後天文23年10月、晴氏は古河城に立籠った(9)。この時簗田氏は一色・二階堂氏らとともに与したようだが、古河城が程なく落居したことをかんがえると、少なくとも簗田氏はこの立籠りには積極的に関与しなかったのかもしれない。
昨今働忠信之至、感悦不少、就之永拾貫文、籠城為用意被下之候、猶以可走廻
急度之条、仍如件、
弘治元乙卯 晴助(花押影)
小沢長門守殿(10)
晴助は、水海村の小沢氏に籠城の用意として永10貫文を与えている。晴氏の立籠・落居に係る後北条氏との緊張状態の中で、簗田氏は籠城策をとったようだが、後述の公方義氏の元服式に関与している。先の家督相続で後北条氏により外戚への道を閉ざされたものの、その一方で宿老中筆頭としての地位を後北条氏が左右しかねない状況の中で、微妙な計算が働いたのかもしれない。
- 義氏の関宿移座
天文24年(弘治元年)、梅千代王丸は元服し、室町将軍足利義輝より偏諱を拝領して「義氏」を名乗る(11)。前年の晴氏古河落居に伴い、義氏は後北条氏の本拠小田原に移っている。ここで後北条氏の手により元服式を挙げたが、北条氏康は簗田晴助に対し次の書状を認めている。
如来意、御元服無相違相調、公私御満足、目出不過之候、就中今度始而遂面上、
年来之本望候、向後弥可申談覚悟候、御所様古河御移程有間敷候、悉皆御馳走
ニ可有之候、兼又二三ケ条承候、存其旨候、委細口上候条、不能審候、恐々謹言、
一二月十七日 氏康(花押影)
簗田中務大輔殿
御報(12)
ここで注目すべきは「如来意、御元服無相違相調」ったことであり、小田原での元服式挙行において簗田氏の意向を無視しえず、後北条氏と簗田氏との間で交渉が行われていたと推測することができる。その結果妥協の条件として「御所様古河御移程有間敷候」と表現された。古河城帰還を含意に義氏の小田原城在城を簗田氏に納得せしめた(13)。後北条氏の公方権力掌握は不完全であったが、それを完全たらしむる上で当面の大きな課題が簗田氏を公方権力からいかにして除外するかであった。後北条氏は簗田氏の存在を意識しつつ、様々な体制の変革(14)を通じて圧力をかけていくことになる。これに対し簗田氏側はどう対処したのであろうか。
山中田地一間、松沼田地一間、岩上田地一間、合三間之田地拾貫百五拾文之所、
御取越神妙申上候間、為御恩賞被下候、御番陣参以下厳密可申候、并不入之儀
御心得之諸事御用等、可走廻候者也、仍状如件、
弘治四年戊午
三月十七日 晴助(花押)
山中藤七殿(15)
簗田晴助は水海の山中藤七に山中など合計10貫150文を恩賞として与えているが、反対給付として「御番陣参」や「諸事御用等」走廻が定められていることから、急速に家臣の掌握を目ざし(16)、自身の基盤固めの心血を注いでいることがわかる。
義氏は小田原から古河に直接帰還する予定だったが、弘治2年10月に鎌倉葛西ケ谷に入り、「葛西様」と呼ばれるようになる。ところが永禄元年に義氏は簗田氏の本拠関宿城に移座することになる。4月に北条氏康は簗田晴助と起請文(17)を交わしているが、「関宿之城公方様為御座之地、来六月中可有御進上由」とあり、関宿城を公方の御座所とするので6月中に明け渡すこととしている。また、「其方御在城為可有之、古河之地被御申請度由」とあり、代わりに古河城が与えられることになった。さらに「御知行之事、聊相違有間敷、模寄之地者、相当程取替可申候」と、簗田氏の所領は安堵するが、関宿最寄りの地は別な地と替えることとしている。これは本拠地及び関宿周辺の支配権を簗田氏から剥奪し、簗田氏の勢力弱体化に導く政策であった。換言すれば簗田氏は古河公方成立以来関宿を本拠としたが故に公方権力の中で勢力を維持することができた。これは「抑彼地入御手候事者、一国を被為取候ニも不可替候」(18)とあるように、関宿が一国に匹敵する戦略的拠点であったとともに、簗田氏が「舟役」(19)を課していたように水上交通の要衝として認識されていたからである。
この後北条氏の圧力に対し、「今度之一儀中務無相違令納得候儀も、先万右馬允極々遺恨候」(20)とあるように簗田氏内部の抵抗があったものの最終的には後北条氏の意に従うことになる。
五ケ条之外、追而
(中略)
一小田助三郎事、如前々可属中務儀、数ケ度被加御下知候処、従前々抱来所領之事、
第一致侘言間、無御了簡過来候、加様之望有廉、自前代馬寄之儀、被仰付候者、
定強而菟角不可申得由思召候、其上尚以氏康、成田下総守ニも意見簡要之事、
以上
弘治四年六月朔日 朱印有之(21)
これは先の氏康の起請文に義氏が追加した申し出の一部である。武蔵国忍城主成田長泰と晴助との間で帰属が争われていた騎西城主小田朝興(長泰弟)の支配を晴助に認めている。移座をめぐり簗田氏の抵抗を抑止する懐柔策と解することができよう。さらに義氏は晴助に次の書状で関宿城明け渡しを賞賛している。
今般属氏康関宿之城進上申候、巷可然被思召間、可被立御座候、中務存寄候所、
不浅忠信被思召候、此上者末代可被加御懇切間、弥可令抽忠儀事、簡要仁被思召候、謹言、
六月朔日 義氏(花押影)
簗田中務太輔殿(22)
こうして晴助の関宿城明け渡し及び義氏の移座が実行されたが、義氏は同年6月19日に晴助に対して「秋務取納来町人以下可移事」や「御料所方諸奉公之知行、簗田成敗互人召仕間敷事、付百姓等迄も致他奉公者知行之内ニ不可指置事」(23)を示して、町人の帰還、奉公人や百姓の帰属の明確化を定めている。これについて新出の「簗田家文書」(24)により次の史料を紹介する(写真)。

分国中人還儀尋承候、氏綱壁書ニハ十ケ年と切而可還旨掟候、此度武上面々中申定
書出ニハ五ケ年と方尓致之候、然者御領中百姓并御家風仁令闕落、守当方者共之領
中ニ至り隠居者、急度可承候、則取還可進置候、御膝下諸奉公中者、幸今度御印判出
候間、如先法証文可被御申立候、猶兎角之者助言可申候、然者又御領中之内江他領
者於迎来者、則本所へ被還附可為肝要候、仍後日状如件、
(「禄寿応穏」朱印)
永禄元年六月廿日 中村平四郎奉
簗田中務太輔殿
これは氏康と晴助との間の人返し協定を示すものである。前述のとおり、義氏の移座に伴い本拠関宿城の明け渡しと関宿周辺の領地替えが実施されたが、簗田氏領内に動揺が走り、百姓・家人の闕落が多発したものと思われる。他方後北条氏にとっても領国支配を確立していく上で、農民支配強化及び闕落などに対する弾圧強化は第一儀の課題である。
後北条氏は今川氏や武田氏のような戦国法の成立をみなかったが、人返し規定(25)については、
(永禄9年)
右、闕落之百姓、為国法間、彼在所領主・代官ニ相断、早々可召帰(26)
(元亀2年)
右、闕落之百姓、縦雖為不入之地、他人之者抱置儀為曲事間、任国法、
領主・代官ニ申断、急度可召返者也(27)
などのように「国法」として定められている。永禄元年若しくはそれ以前において「国法」の語は管見の限りでは確認できなかったが、「氏綱壁書ニハ・・・」「武上面々中申定書出ニハ・・・」とあるように「国法」としての基盤は確立されており、これを根拠にして氏康は晴助と人返しの協定を結んでいる。しかしあくまでも後北条氏の法理を前提としている点に、公方支配権の深化と簗田氏勢力の弱体化を読みとることができよう。
- むすびにかえて
古河公方成立以来、簗田氏は公方権力の中で重き地位にあったが、この体制は後北条氏にとって公方権力を自らの支配下に組み込む上で最大の障害となった。このため後北条氏は、晴氏と芳春院殿との婚姻、義氏への家督相続を断行した。公方権力から簗田氏を疎外する意図が内在するものであるが、その一方で義氏を通じた懐柔策もとられている。しかし簗田氏にとっての最大の痛手は本拠関宿城の明け渡しであり、これにより後北条氏は簗田氏に対し決定的優位を獲得するとともに、課題が簗田氏から公方権力そのものに移行する契機となるはずであった。
しかしその後、簗田氏は永禄3年より南下した上杉謙信に与し、関宿城に復帰する。これにより後北条氏と簗田氏は、公方権力を介した拮抗から直接対立へ進むこととなる。
| 註 | |
| (1) | 関宿城は長禄元年に簗田成助が築いたとされるが(奥原謹爾『関宿志』1973年、関宿町教育委員会)、『鎌倉大草紙』の康正元年の記事に「関宿の城に簗田を籠」とあり、この時点ですでに関宿城が存在若しくは築城されていたことが窺える。今後検討を要する。 |
| (2) | 佐藤博信「後北条氏と古河公方足利氏の関係をめぐって」(『史学雑誌』87-2、1978年)、同「古河公方家臣簗田氏の研究」(『千葉大学人文研究』10、1981年)ーともに後に『古河公方足利氏の研究』(1989年、校倉書房)に所収、以下前者を佐藤論文1,後者を佐藤論文2とするー、長塚孝「戦国期の簗田氏について」(『駒沢史学』31、1984年)、鍛代敏雄「古河公方家臣下総相馬氏に関する一考察」(『栃木史学』創刊号、1987年)など。 |
| (3) | 佐藤論文1は婚姻成立の契機を前年(天文7年)の「国府台合戦」(古河公方と小弓公方の対立)に求め、晴氏が公方家存亡の危機を回避するするのに後北条氏の力を利用する以外に方法を持たなかったために、婚姻が実現したとしている。また、この婚姻の歴史的意義は後北条氏の公儀性を公方家との関係の中に位置づけることによる充全化、及び下野・常陸など伝統的豪族層に対する公方の対外的機能の利用にあるとしている。 |
| (4) | 『古河市史』資料中世編777号文書、以下『古』777の如く表記する。 |
| (5) | 『古』784。この時期、簗田氏に限らず他の家臣に対しても所領安堵や新恩給与を実施しており、この家督相続により家臣団内部に動揺があったことがわかる。 |
| (6) | 『古』791。 |
| (7) | 『古』779。 |
| (8) | 佐藤博信「古河公方足利晴氏についての覚書ー特に御座所変遷をめぐってー」(『金沢文庫研究』280、1988年)、以下佐藤論文3とする。 |
| (9) | その後晴氏は相模波多野にに幽閉され、関宿で隠居後の永禄3年5月に死去した。『喜連川判鑑』に「晴氏於関宿逝去」とあるが、冨田勝治は「足利晴氏死没地考ー晴氏は上総国嶋之で没したかー」(『埼玉地方史』17、1984年)で「鑁阿寺文書」(『古』991)に「嶋之上様」とあることから晴氏の死没地を御料所上総国市原郡嶋之郷に比定した。これに対し市村高男は『鷲宮町史』(1986年)で冨田説を否定し、古河公方関係の系図・記録類の記載内容や、関宿が常陸川や低湿地に囲まれ「嶋」と呼ぶにふさわしいことから関宿で死没したとしている。また佐藤博信も「『嶋之上様』のこと」(『戦国史研究』11、1986年)で冨田説を否定し、後年義氏の遺女氏姫が御座した栗橋嶋(茨城県五霞町)としている。なお、宗英寺(関宿町)に晴氏の墓がある。これについて佐藤論文3では石塔の形態や銘文の字配りなどから晴氏の墓であることに疑問を呈している。 |
| (10) | 『鷲宮町史』史料中世三297号文書、以下『鷲』297の如く表記する。 |
| (11) | 『古』921、922、923。 |
| (12) | 『古』931。 |
| (13) | 佐藤論文3 |
| (14) | 佐藤論文2「公方義氏成立にともなう『殿中』における芳春院殿・芳春院周興を中心とした奏者体制の整備であった」「従来の簗田氏を筆頭とする『宿老中』による奏者体制を否定する中で成立した」。 |
| (15) | 『鷲』324。 |
| (16) | 長塚前掲論文。 |
| (17) | 『古』967。 |
| (18) | 『古』970。 |
| (19) | 『古』977。 |
| (20) | (18)に同じ。 |
| (21) | 『古』974。 |
| (22) | 『古』973。 |
| (23) | (19)に同じ。 |
| (24) | 千葉県立関宿城博物館では簗田氏の子孫より40点余の受託・保管しており、その多くが『古河市史』などに掲載されている古河公方や後北条氏発給文書の原本である。現在分類・整理中であるが、今後機会を得てその成果を公表する。 |
| (25) | 後北条氏の人返し規定については、中村吉治『近世初期農政史研究』(1938年、岩波書店)、中丸和伯「後北条氏と虎の印判状」(『中世の社会と経済』1962年、東京大学出版会)、藤木久志「大名領国の経済構造」(『戦国社会史論』1974年、東京大学出版会)、同「戦国法の成立と構造」(同)など。 |
| (26) | 『戦国遺文』後北条氏編(1990年、東京堂出版)974号文書。 |
| (27) | 同1477号文書。 |
(しまだ ひろし:千葉県立関宿城博物館研究員)