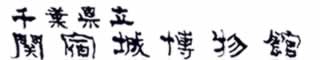
合 同 企 画 展
平成12年2月22日から3月26日まで開催されました。
当館企画展示室で開催
 |
江戸時代も中期になると、庶民の間に社寺参拝や遊山の旅が流行しました。なかでも伊勢神宮のお参りは多くの人々のあこがれでした。しかし誰もが容易に行けるものではありません。そこで人々は近隣の風光明媚な名所・旧跡や御利益があるとされる寺社に注目し、日帰りできるところから10日前後で帰ってこられるいろいろなコースが考案されました。 常総地域の旅は、比較的容易に行くことができるとともに利根川水運を利用した船旅も楽しみの一つとして流行しました。そして多くの文人墨客達も足を運び、旅の様子やその地域での出来事などを書き残しています。 この合同企画展では、常総地域、利根川・江戸川を中心に旅した文人墨客達の事跡・作品を紹介するとともに、近世の旅人の目に映った情景と現代を比較しながら、今も残る常総地域の史跡などを紹介します。 |
1 近世の旅人
○近世・旅の携行品
2 常総を旅する人々
○松尾芭蕉と旅する ○小林一茶と旅する ○句に詠まれた「布施弁天」 ○藤森弘庵と旅する
○小山田与清と旅する ○渡辺崋山と旅する ○十返舎一九と旅する ○旅人が訪れた小金牧
| 1 近世の旅人 | |
| 江戸時代はじめの旅人は、武士や高僧・公家のほか一部の支配層の人々が主でしたが、江戸時代中期以降になると一般庶民の間に社寺参詣や遊山の旅が流行しました。なかでも伊勢参宮は多くの人々のあこがれでしたが、日数や費用の関係から誰もが容易に行けるものではありませんでした。そこで当時の人々は日帰りや10日前後で往復できる近隣の風光明媚な名所や御利益があるとされる社寺を見つけだし、それらを取り入れた旅のコースを考案しました。 江戸庶民にとって常総地域への旅は、利根川水運を利用して手軽に行けるコースとして大変人気がありました。 |
|
| 近世・旅の携行品 | |
| 現代においても旅の荷物はなるべく軽くて小さい方が移動の際に都合が良いものです。まして徒歩での移動が主であった近世においてはなおさらでした。 そこで当時の人々は、携行品をなるべく小さく収納できるように様々な工夫を凝らしました。また、旅行が流行するようになると旅のガイドブックというべき「旅行用心集」や「絵図」などが数多く発行され旅の必需品となりました。 |
|
| 2 常総を旅する人々 | ||
| 常総地域には成田山や香取・鹿島・息栖の三社などのほか多くの名所・旧跡があり、文人墨客たちにとっても魅力のある地域です。『奥の細道』を著した松尾芭蕉や『東海道中膝栗毛』を著した十返舎一九、『四州真景図』を描いた渡辺崋山など多くの文人墨客が足を運び、旅の様子や各地の人々との交流・逸話などを句や紀行文、絵図に残しています。 | ||
写真:奥の細道行脚の図(天理大学附属天理図書館) |
 |
|
写真:一茶肖像画(一茶双樹記念館) |
 |
|
|
 |
|
写真:航湖紀勝(船橋市西図書館) |
 |
|
写真:相馬日記(千葉県立関宿城博物館) |
 |
|
崋山は高野長英、小関三英ら蘭学者と交わり海外事情を研究しましたが、蛮社の獄で蟄居を命じられ、後に自刃して果てました。 写真:四州真景図(千葉県立大利根博物館) |
 |
|
写真:諸国道中金草鞋(船橋市西図書館) |
 |
|
写真:冨士三十六景小金原 広重(千葉県立関宿城博物館) |
 |
|
展示資料一覧
1 近世の旅人
関東十九州旅程図・関八州全図・通行手形・旅行用心集・五街道中細見記・道中記(千葉県立関宿城博物館)、行李・折立式燭台・旅枕(国立歴史民俗博物館)、煙管・発火具・携帯用裁縫具・印籠(山本光正)、背負袋・小物入れ(野口紀久子)
2 常総を旅した人々
○松尾芭蕉と旅する
かしま紀行・利根川名所勝景図会(船橋市西図書館)
○小林一茶と旅する
帰郷日記・勝鹿図志手繰船(千葉県立中央博物館)、水陸刀根川筋絵図・発心帖(船橋市西図書館)
○句に詠まれた「布施弁天」
布施弁天来歴書抜(後藤敏)、利根川図志(千葉県立中央博物館・千葉県立関宿城博物館)
○藤森弘庵と旅する
春雨楼詩鈔(千葉県立中央博物館)、航湖紀勝(船橋市西図書館)
○小山田与清と旅する
相馬日記(千葉県立中央博物館・千葉県立関宿城博物館)、鹿島志(千葉県立中央博物館)、下総国累物語(船橋市西図書館)、鹿島日記・下総成田銚子香取常陸鹿嶋息栖略図(千葉県立関宿城博物館)
○渡辺崋山と旅する
四州真景図(千葉県立大利根博物館)、崋山翁刀寧游紀(船橋市西図書館)、香取参詣記(千葉県立関宿城博物館)
○十返舎一九と旅する
諸国道中金草鞋・常陸野州道中細見記(船橋市西図書館)
○旅人が訪れた小金牧
小金牧絵図(鎌ヶ谷市郷土資料館)、野馬捕図(川嶋亥良)、佐倉牧野馬捕図(渡辺とみ)、矢作牧麁絵図・取香牧麁絵図・油田牧麁絵図(千葉県文書館)、湯沸かし・弁当箱・酒入れ・水飲み(藤崎牧士史料館)、冨士三十六景下総小金原(千葉県立関宿城博物館)
展示協力者(敬称略)
愛宕神社 一茶双樹記念館 応順寺 柏市 柏市教育委員会 鎌ヶ谷市郷土資料館 光明院 国立公文書館 国立歴史民俗博物館 琴平神社 西光院 埼玉県立博物館 西林寺 実相寺 田原町博物館 千葉県立大利根博物館 千葉県立西部図書館 千葉県文書館 長禅寺 筑波大学附属図書館 土浦市立博物館 天理大学附属天理図書館 東海寺 徳満寺 流山市教育委員会 (財)日本地図センター (財)藤崎牧士史料館 船橋市西図書館 法蔵寺 本土寺 松戸市教育委員会、松戸市立博物館 萬満寺 八街市教育委員会 来見寺
植田敏雄 川上武雄 川嶋亥良 後藤敏 瀬能泉 田中正治郎 野口紀久子 山本光正 村松庸雄 渡辺とみ
Copyrightc©2005 Chiba Prefectural Sekiyado-jo Museum. All rights reserved.