
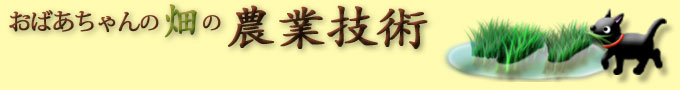
畑や田んぼに種子を蒔いて育てる。水や肥料をあげて時間がくれば収穫できる。
作物を育てるのは、そんな簡単な事ではありません。
たとえば、種子の蒔き方1つで、発芽率が違うのです。
おばあちゃんの作業の様子を見ていると当たり前のようにやっていますが、その所作1つ1つに技術がつまっているのです。
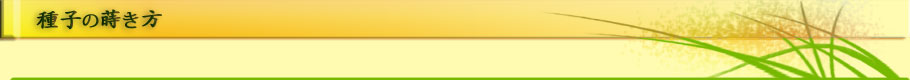
これは苗代(なわしろ〜苗を育てる場所〜)の写真です。
均一に苗が育っている方は、おばあちゃんたちが蒔いた所。
一方の虎刈りになっている所は、私たちが蒔いた所。
一目瞭然です。


カボチャはポットで苗をつくります。
1つのポットに種子は2つ入れます。

苗が大きくなったら、畑に定植です。

小さな小さなゴマの種子は「千鳥蒔き」です。
1つの畝に右左交互に蒔いていきます。

ショウガは適当な大きさに切って、ならべていきます。

座敷箒(ざしきぼうき)の材料になるホウキモロコシの種子、一粒一粒ていねいに蒔きます。
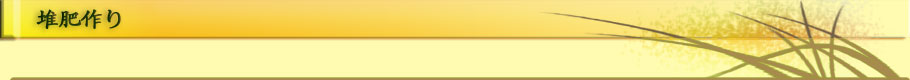

田んぼや畑に入れる堆肥(たいひ〜肥料〜)も作ります。

山の中の落ち葉を熊手でかき集めます。

集めた落ち葉は、ほんの少しの藁を使って俵にします。

おじいちゃんが足と熊手を使って、落ち葉を硬くかためると持ち上げても崩れません。
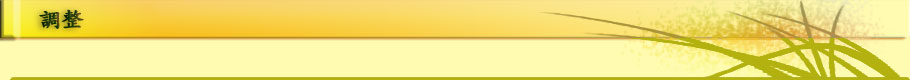
お米や麦などの穀物は、田んぼや畑から刈り取っただけでは食べられません。
乾かし、茎から落として、小さなゴミと分けて、皮をとって・・・
いくつもの作業の後にやっと食べられるようになります。この作業を調整といいます。
刈り取り方からはじまて、調整方法は作物によっても違います。

1.キビは穂の部分だけ刈り取って束ねます。

2.キビを干しているところです。

3.乾いたキビは、木槌(キズチ)でたたいたり、手で揉んで実を落とします。

4.実とゴミをより分けるには風の力をかります。これは、上総唐箕(かずさとうみ)という風で選別する道具です。