
�^����
��t�������������قƂ������̂���^���ƂƃR���N�V�������Љ�܂��B
���J �ߕF�@(1926-2007)
���J�ߕF���͐��E�I�Ɉ̑�Ȗ쐶�����^���Ƃł��B�䎩��Ɋ��J�T�E���h�A�[�J�C�u���₳��܂����B
���O�A���������قɂ����͂��ĉ�����A�u�O��i���J�j1959�C1975�C1986�v�Ɛ�t���̐̂̉��Ƃ��āu��t���i���J�j�v�Ɓu�V�l�̒� �i���� ��t���j�v����������Ă��܂��B�{�ٓW�����ɂ��M�d�ȉ����W��������܂��B
�W���� �u�[���̎��R�v�ł͒J�Óc�̎l�G�̉�������Ă��܂��B�،͂炵�○�̉��̑O��ŕς�鐶���̉��� �����ƕς��̂��Ȃ��Ȃ������ł��B�W���� �u���R�Ɛl�Ԃ̂������v�����̃W�I���}�u�J�Óc�̐����v�ł͒J�Óc�̓������牜�ւƉ��̕��i���W�J���܂��B
�W���� �u���߂���-���̔閧��O�ꋆ���v���g���ƁA�ڍׂ��킩�邱�Ƃł��傤�B�����ɂɂ͉p���}���� �쐶�������� (�a�k�n�v)�ɂ����Ď��^���ꂽ���J���̃C���^�r���[�^��������܂��B
�@ ���J�ߕF������ �v
��t�������������ق� ���R�̉��̘^�����W���n�߂�ɂ�����A���J�ߕF���̌䎩��ɂ���T�E���h�A�[�J�C�u�����K�˂��܂����B
�˒I�ɂ͂�������̃��[���e�[�v����������ƕ��сA�ҏW�@�≹�����͋@���z�u���ꂽ������
�u���Ȃ��� �ł��邩�ȁv�Ǝ���X���Ȃ���A�l���ĉ������Ă���p�́A���ł��Y��܂���B
����܂ő����̖쐶�����^���Ƃɉ���Ă��܂������A�ǂ�������ǂ��^�����Ƃ�邩 �^���̎�̓��𖾂������͂�����������܂���B
���̓��A���J���������ĉ��������S���́A�^������͕K���Q�g���낦��Ƃ������Ƃł����B����ꂽ�\�Z���Ń��R�[�_���Q��A�}�C�N�͂Q�{(�X�e���I�Ř^��Ȃ�S�{)�p���{����������Q��Ƃ����̂́A�������̂ł��B���R�͖�O�^���ł͉����N���邩�킩��Ȃ��A�}�C�N���R���痎���������背�R�[�_���}�Ɍ̏Ⴕ���肷��A���̎��_�ł߂����Ă����^�����ł��Ȃ��Ȃ邩��ł��B�܂��A���R�[�_�ƃ}�C�N�݂͌��Ƀo�����X���Ƃ����̂��悢�Ƃ������Ƃ������Ă��炢�܂����B�}�C�N�����悭�Ă��A���R�[�_��������� �������Ɉ���������Ƃ������̂ł��B
���̓�����20�N�ȏソ���܂������A���̓S���������Ă������������Ƃ��ϊ��ӂ��Ă��܂��B�����Ă��̊ԁA�����m�������Ƃ́A�^���͑��u�����ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃł��B���J�����D�������K���܂őҋ@����u���̏u�ԁv��^������Ă��邱�Ƃ͂��낢��ȏ�ʂł��b�����Ă��܂����B
���J���̌�p���玩�R�����Ɍ������������ɋ������ɐS��뎨�������ނ��邱�Ƃ̑���������Ă��܂��B
���������Ȃ��ł����̐������������ꂽ���ɘ^�������B
���̓V�R�L�O���Ɏw�肳��Ă����匵���̋����̃J���E�̃R���j�[��1971�N�Ɋ��S�ɏ��������Ă��܂����B
���Y��Y���́A�������{�����܂�B���z���w�сA�����g(��.��������)�ɋ߂��܂������A1939�N����c��w���z�Ȑ쓇�����̂��ƂŌ��z��������ɏ]������܂����B1943�N�ȍ~�͍����w�҂̑咬���q���Ɏt�����R�I���M�ނ̈�`�w���w�т܂����B1948�N�A��������������Ђ�ݗ����ꂽ����A���U �R�I���M�ނ̌������s���A�����̒��삪����܂��B�܂��A������J�G���A���ȂǍ����O�Ř^������₳�ꂽ�^���͊w�p�I�ȉ��l�̍������̂ł��B�^�����̊w�p���p�ɔM�S�ŁA1988�N�ɋ}�����ꂽ��́A��q���̏��Y �����Ɖ���ǎ}���̌����ȍ�Ƃɂ��S�^�����f�W�^���������t�������������قɊ֘A���鎑���ƂƂ��ɔ[������܂����B(�u����6�N�x����ϑ����Ɓv)
- �����̊ώ@�ƌ����i�j���[�T�C�G���X�� 1983�N�j
- ���͂Ȃ���-���̉Ȋw�i�����o�� 1990�N�j
- �����̔������i���ꑍ���o�� 1986�N�j
�I���W�i���̃��[���e�[�v�͎���̏��ւɒ����ۊǂ���A����Ԃ܂ꂽ���߁A�f�W�^�������s�Ȃ��܂����B���킹��DAT60���e�[�v72�{�Ƃ��̃o�b�N�A�b�v1�g���[������܂����B�܂��A�֘A�����Ƃ��Ė����̘^���Ɏg�p���ꂽ�@��⌤�������A�ʐ^�A�����E���瓹��ȂǏ��Y��Y��m�邽�߂̎���������Ă��܂��B����܂łɓW���⋳�畁�y�����Ƃ��Ċ��p����܂����B���ԉ��I���G���e�[�V�����n�E�X�ɂ������i�t�H���̃J�G������29��͂��ׂĂ��̃R���N�V�����Ɋ�Â��܂��B
���Y ��Y���ɂ�������̂�1987�N�x�̓����s���w��ł����B
���� ���M��w���w���Ő��������w�̍u�`�A���ʃZ�~�i�[��S�����Ă��܂����B���ЂƂ������̖������w�������ɕ����Ă��炢�����āA�^��������T���Ă����Ƃ���A���Y�����G���}�R�I���M��X�Y���V�̃{�L���u�����[�ƋC���ɂ�钎�̉��̕ω���^�������e�[�v�����������ĉ����邱�ƂɂȂ�܂����B
����䎩������K�˂��A��������̉����@��Ƙ^���Ə��ЂɈ͂܂ꂽ���ւŁA�f���e�[�v�ڍ���ĉ������܂����B
�u�`�ł����̉������ۂɕ������w�������̔������ƂĂ��ǂ��������Ƃ��v���o���܂��B
���̌�����������ق̍u����ώ@��ɂ����āA���Y���̘^���͑����̕��ɕ����Ă��������Ă��܂��B
1950�|80�N��̎��R�̉��̋L�^�ł��B
���� �T�Y�@(1928-2010)

 �y��� 2010�N4��26��
�y��� 2010�N4��26��
���ݓT�Y�͓����r�ܐ��܂�A�c������A�o�X�ʂ��q��(�т傤)�ɔ�щ��c�o���ɖ����꒹���D���ɂȂ��������ł��B(���O�A���{���ތ��������Â��A���{�쒹�̉�A�R�K���ތ������ɏ�������Ă��܂����B)
��菤�Ђ�ސE��A�{�i�I�ɖ쒹�̌������n�߂��S���Q�P�����̃S���t��ɐݒu���������̗��p��1989�N����11�N�� ����33,284�� �������܂����B���\�f�[�^����͑����̗��p�����オ��悤�ȁA�ݒu���@�����㌟������邱�Ƃ����͖]��ł����܂����B
�u������x��@�������߂Ă��܂����y���@1989�N�`2010�N�܂ł̘^���̔�r�^���v�́A21�N�O�ƌ��݂̊ԂɋN�������̕ω���m�邱�Ƃ̂ł���d�v�Ș^���Ƃ����܂��B���َ����̐��ԉ��̉����^���A���ݓT�Y���������^���R���N�V�����i����17�N�x�A�y���ɂ�����20�N���z�����_�^�����݂��lj��������p�����Ĕ[������Ă���j�Ȃǂƍ��킹�āA�ߔN�}���ɂ����Ă�����{�̎��R���̕ω���������T��d�v�Ȏ����ł��B
�u���̘^���͒��̂���������ӏ܂��邽�߂̘^���ł͂���܂���B�^�����_�ł̂���̂܂܂̐��Ԃ��A�����Ԃɂ킽���_�ɂċL�^�������̂ł��B �y���̕ʑ��n�ł́A1990�N�܂ł͒��̐������ɑ����������A�N�X��������A����2000�N�Ȍ�͌����Ƃ����ł��B ���̘^���L�^�́A���̕ω�����������̕p�x�̕ω��Ƃ��Ď����؋������Ȃ̂ł��B�v

�� ���ݓT�Y�́A��ϋÂ萫�ř{���ʂȐ��i�ł����B
�R�c�R�c�Ɠw�͂��N�����������Ȃ��M�d�Ș^�����₵�܂����B
�y���ɕʑ����w���������N��1989�N����J�n�����^�����T�|�[�g���Ă�������������������A�R���̂�q�l�A���̈�u���p���ʼn�����y���ʑ��c�̘A����ɐS���炨���\���グ��Ƌ��ɁA�y���̎��R�Ɗ�������邱�Ƃ�Ɋ肤����ł��B
(2012�N�P���R���@����)
���ݓT�Y������t�������������ق��ŏ��ɂ������ˉ��������̂́A���������ق��J�ق���1989�N�̂��Ƃł��B ���ݎ��̓S�~���A�J���X��A�����ɂ����ۑS�ȂǁA���L���e�[�}�����ɐ��͓I�Ɏ��g�܂ꂽ��M�I�ȕ��ŁA����ɁA���̕ω������łƂ炦�邱�Ƃ��ł��邩�ǂ����A�ǂ̂悤�ɂ�����^���ł��邩�A�^����͂̎d���ɂ��ĔM�S�Ɏ��₳��܂����B
���ꂩ��20�N�A���ݎ��̓R�c�R�c�Ɩ��N �t�̂�������̎����Ɍy���̕ʑ��Ř^���𑱂����܂����B
2007�N�ɂ́A�����̃f�[�^���܂Ƃ��_�����₳��܂����B�p�����Ę^�����邱�Ƃ̓���͂��Ă����A�c��ȃf�[�^�̉�͂����������A���̃f�[�^����ɕʑ��n�̎��R�ی�A���ۑS�A�܂��Â���ւƐϋɓI�ɂƂ肭�܂�܂����B�����I�^���̈Ӌ`�ɂ��ċ����_�����v�悵�Ă�������]��ł����B
���c �E�@(1934-)
 ���c �E��
���c �E�����c �E���i���s�쒹�̉�j�́A���s��e�n�̎��R�ی�ɂ��đ��w���[���A1986�N�ȗ����{�e�n�Ŗ쒹�̉����^�����s���Ă��܂����B�쒹�̖������ł��邾�����R�̏�ԂŘ^�����邽�߁A�[��ɘ^���n�֓������Ę^���@�ނ��d�|���A�����g�͂��̏ꏊ���͂Ȃ�đҋ@�����Ƃ������Ƃł��B�^��(�ҏWCD)�����������Ƃ���A�^���ꏊ�𗣂�Ă��邽�߁A�^�����x���ȂǓ�_�����鎑��������܂����A���݂ł͂Ȃ��Ȃ��������Ƃ��ł��Ȃ����炵���閾���̃R�[���X�A�M�d���d�v��̖������܂܂�Ă��܂��B
�R���N�V�����̒��ɂ́A���{�̖쒹���������̑n�n�҂ł���쑺������搶�̘^���i�f�[�^�C���jCD���܂܂�Ă��܂��B
���c���́A�������������̊w�p���p�Ȃ�тɎЉ�ɖ𗧂Ă邱�Ƃ����҂����������قɊɂ���܂����B
���c �E���ƒm�ȂɂȂ����͎̂l�����I�ȏ���O�̂��ƂŁA���߂ĎQ���������s�쒹�̉�̗��ł����B
����ۂ́A���{�����l�B�������łȂ��ɁA��̐��������ׂĂɐ[�����H�I�Ȓm����g�ɂ��Ă��܂����B
�y�₩�ɋ����u�o�[�h�E�H�c�`���[�̒B�l�v�Ƃ������A�[���X�̒��ɏZ��ł����l�̕���ł����B
�ނ����̐��̘^���ɂ��āu�a�A�p�Ӄj�����v(��܂��A���������ɂ���)�̋��n�Ɏ������̂������������̂��A�L���ɂȂ����炢�Â����Ƃł��B�����ɂ킽��A�q��łȂ��W���͂̐��̘^���ɒ�������܂����B
���R�̒��ŗǎ��̘^���邽�߂ɂ́A���l�I�ȓw�͂��K�v�ł��B��s�ɋΖ����Ȃ���A�f���炵���^���L�^�̃R���N�V�������~�ς��Ă䂭�̂͑�ςȂ��Ƃ������Ǝv���܂��B�钆�ɋN���āA�Ԃ��^�]���Č��n�ɁB���̏o�̈�A�ԑO�ɘ^���̏������ς܂���B���������������Ă��J�ɂȂ�����A����������������A��s�@�̔����������ɔ������E�E�E�B
�u�������ҁv�̗̈�ɓ��鍠�ɁA�u�ߍ��A���{�̒��̖���������ɂȂ����v�Ƃ��т��ъ�����悤�ɂȂ��������ł��B�������Ԃ��Ȃ��A���̌����������g�̒��͂̐����ł��邱�ƂɋC�t����܂����B�����ŁA�^�蒙�߂Ă����^���L�^�������̍��Y�Ƃ��čL�����p���Ă��炦��悤�ɂȂ�Ȃ����Ƒ��k���܂����B�����R���N�V�����͖{�l�������Ɋ��S�ɐ����������܂����A�����Ă���ԂɌ��������ł�����A���܂ł����p����邱�ƂɂȂ�܂��B����A��t�������������قŃR���N�V���������J����邱�ƂɂȂ�A�ނ̊�]�������������Ƃ��Љ�҂Ƃ��Ċ��ł��܂��B
�����قɂ����ĉ��̕W�{�� �u���{�Ɛ��E�̎��R�Ɖ����i�b�c�v�Ŏ����ł��܂��B
���S34��36�b���T�������ɔ���
�q�K���E�N���W�Ȃǂ̉̂��Ƃ荞��Ś����Ă���B
���S5��22�b��1��10�b�Ԃ�
�T���x�c�@8��56������^�� ���S��
1999�N5��13�� 4��44������^��
���͂��܂�̕�����1����
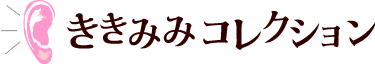

 �@1980�N��
�@1980�N��


