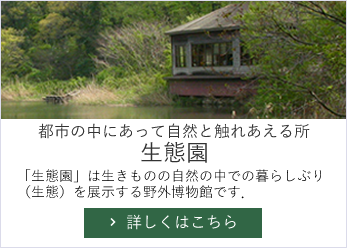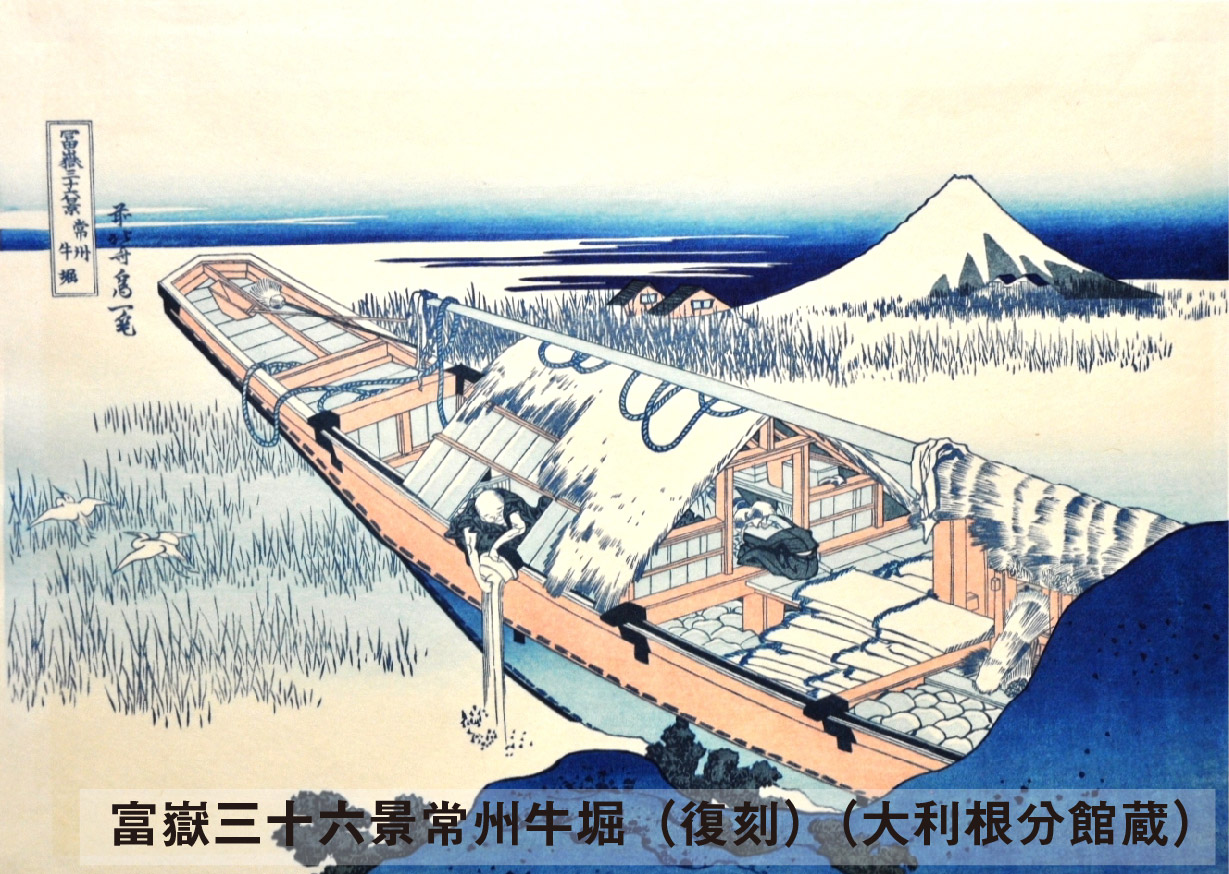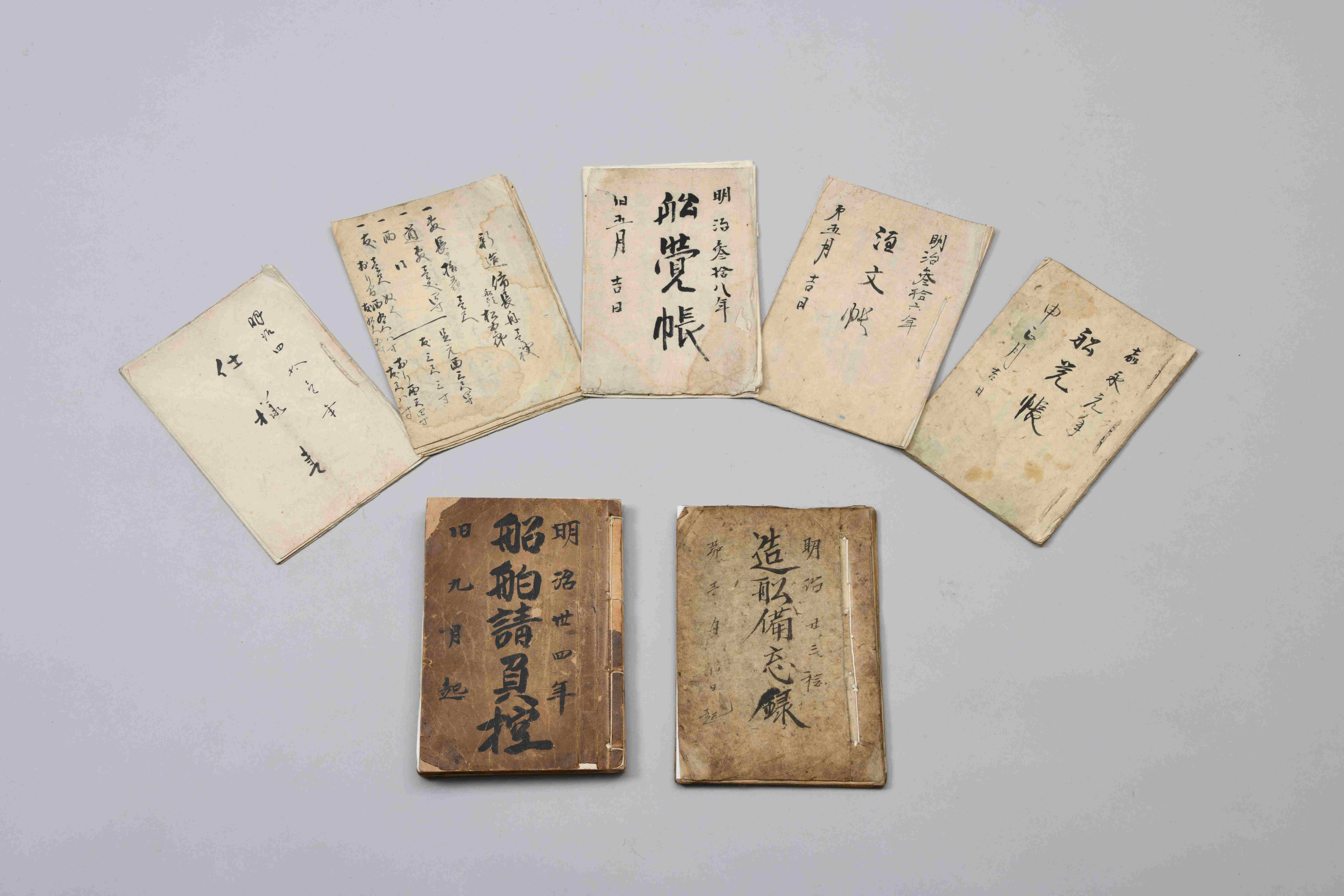「利根川中下流域の川船及び関連用具」が
国の登録有形民俗文化財に!
国の文化審議会は、文部大臣に対し、千葉県立中央博物館・大利根分館・関宿城博物館が収蔵する「利根川中下流域の川船及び関連用具」を登録有形民俗文化財に登録するよう答申しました(令和7年1月24日 答申)。
国登録有形民俗文化財の「交通・運輸・通信に用いられるもの」という分類で登録第1号となる資料です。
〈資料概要〉
名 称:利根川中下流域の川船及び関連用具
員 数:656点
種 別:交通・運輸・通信に用いられるもの
登録基準:有形の民俗文化財の収集であって、その目的、内容等が歴史的変遷、時代的特色、地域的特色、技術的特色、生活様式の特色又は職能の様相を示すもの
〈資料の特徴〉
利根川流域は江戸時代以来、銚子と江戸、また北関東一円をつなぐ舟運によって繁栄しました。舟運の発達が流域の醸造業など産業の発展を促し、大小の河岸が形成され、さまざまな物資や人を運ぶ多様な形や大きさの川船が造られました。なかでも利根川高瀬船は、江戸時代から昭和30年代まで活躍しています。
利根川の支流や湖沼の周囲ではサッパ舟などと呼ばれる小型船が人々の日常生活に欠かせない交通手段でもありました。本資料は高度経済成長期以前の利根川中下流域の水運を今に伝える貴重なものとして認められました。
〈資料の分類〉
①川船
…長距離輸送の高瀬船、生活の足のサッパ舟、利根川の氾濫時に活躍した避難用の揚船
・川船(サッパ舟、揚舟)
・川船部材(船体部分、帆桁など)
②川船用具
…操船、航行途中での寝食などに使った用具
・操船用具(櫓、滑車など)
・船上用具(とば、船箪笥など)
・補修用具(鍔ノミ、指ぬきなど)
③船大工用具
…利根川流域で活躍した高瀬船やサッパ舟を製作した船大工の用具
・船板図
・計測図(分度器、定規、墨さしなど)
・加工用具(鋸、鉋など)
・接合用具(船釘、かすがいなど)
・防水用具(マキハダ、ならしなど)
・固定用具(キリンなど)
・修理用具(砥石など)
・その他用具(道具箱など)
④信仰用具・その他…航行の安全の祈りや、造船の記録
・信仰関係(太子講、船霊など)
・模型・記録類(高瀬船模型、廻船問屋広告、蒸気船鑑札、船に関わる記録)