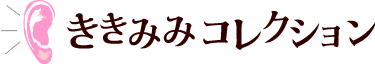利根川の河口から、茨城県、小貝川、鬼怒川の上流
地図のポイントにカーソルをあてると、地点の名前が出ます。
クリックすると各地点のページにジャンプします。
クリックすると各地点のページにジャンプします。
- 地点1へ
- フィールドワークのきっかけ
フィールドワークのきっかけ
大庭 照代
茨城県神栖町の利根川に広がるヨシ原に、オオセッカ(絶滅危惧種)が繁殖している。このさえずりを録音するため、利根川をたずねたのが1992年。
ヨシの茎から舞いあがり弧を描いて茎に戻るまでの数秒間、キャラキャラキャララララ・・・と美しい声でさえずる。川風に吹かれて揺れるような川辺の自然の音に惹かれた。
阪東太郎と呼ばれる関東一の大河を目前に、この川上や川下にどんな自然の音の響きがあるのだろう、と漠然と思ったのが始まりかもしれない。
ヨシの茎から舞いあがり弧を描いて茎に戻るまでの数秒間、キャラキャラキャララララ・・・と美しい声でさえずる。川風に吹かれて揺れるような川辺の自然の音に惹かれた。
阪東太郎と呼ばれる関東一の大河を目前に、この川上や川下にどんな自然の音の響きがあるのだろう、と漠然と思ったのが始まりかもしれない。
調査内容
川といっても実にさまざまで、中央博物館生態園の全長50メートルほどの人工の小川もあれば、源流から河口までの間にいくつもの支流や支川をもった複雑な水系の大河川もある。
この調査では、関東太郎と呼ばれる日本屈指の大河川である利根川を、千葉県銚子市と茨城県波崎市に開いた河口から川沿いにさかのぼり、中流から先は関東平野の比較的平らな場所に水源がある小貝川と、山岳地帯に発し広大は中流域をもつ鬼怒川の2つの川をそれぞれ上流までたどった。川のまわりには大自然もあれば人の住む町もある。
その多様な環境をできるだけ抑えられるように調査地点を選び、耳で聞く聴取記録とともにDATレコーダーで録音した。これらの録音から、川辺の音環境の音源構成を調べ、音響分析により川辺の音環境の音響構造を視覚化して、調査地点の植生や地形、土地利用との関連を探った。
思わぬ発見
小貝川は、懐かしい風景が広がる川だった。どこまでいってもあたりはとても平らで、小貝川が流れる音は常に柔らかだった。上流には山があるという川のイメージとは全く違う。
川はそれでもだんだん狭くなり、ついに田んぼの間を流れる三面護岸の水路になり、最後はU字溝だった。びっくりしている私に、農家のおじさんは、「こんなところまで整備するのは無駄遣いだ」と言いながら、自分の田んぼの稲が育つ様子をいとおしそうにいつまでも眺めているのだった。さらに進んだその先に水源地があった。少し丘のようになっていて、鶏のにぎやかな鳴き声が響いていた。
大変だったこと(苦労したこと)
鬼怒川の上流は、人を寄せ付けないような渓谷がひろがっている。キツネやハチクマやニホンザルなど、録音中にすぐ近くまでやってきた。
激しい水音に満ちて、林の中でさえずる小鳥たちの声はようやくかすかにそれらしいと聞こえるだけである。
こんなにうるさかったら、コミュニケーションは難しいだろう。
しかし、それにしても、どこにいっても水力発電所と送電線が追いかけてくる。
発電のうなり音も送電線から聞こえるビリビリ音も音環境ではあるが、マイクが反応して録音ができないのだ。
私たちの生活は電気に支えられているが、私たちの知らないところでこんなうなり音を出しているのだ。