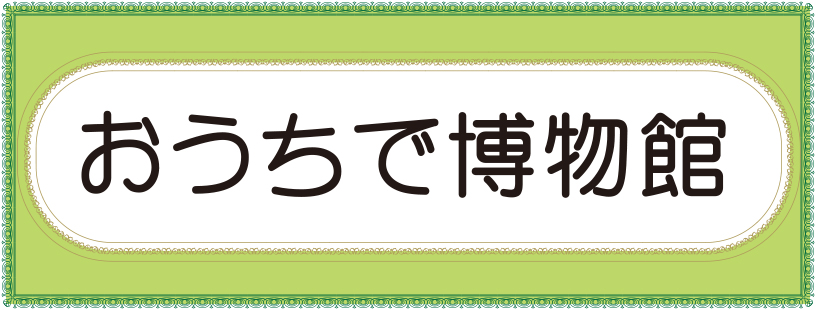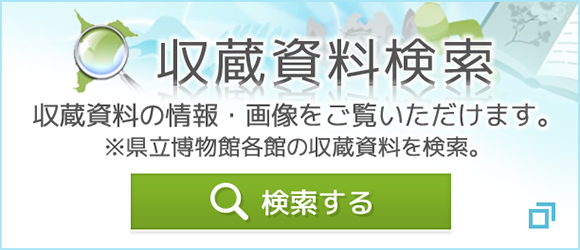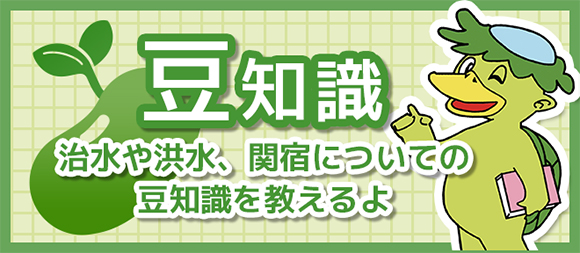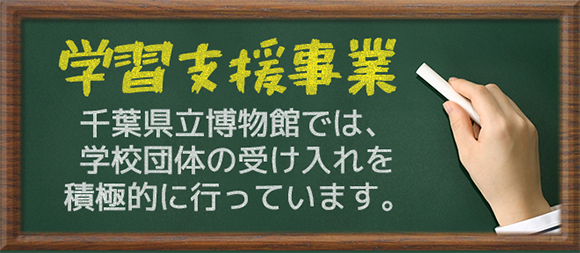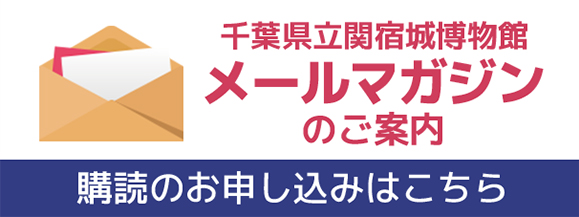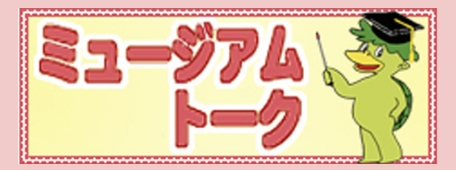中川低地の「領」と水防地形
~ 岡田 光広 ~
1. はじめに
平成九年八月十二日から九月二十三日まで、関宿城博物館では特別展として「忘れまい大洪水~カスリーン台風回顧展~」を開催した。これは、昭和二十二年九月のカスリーン台風襲来から50年目に当たりその被害の甚大さを振り返るとともに、それに至った原因などを紹介することで、これからの川と私たちについて考えるきっかけを得ようとすることが目的であった。
その中で被害の中心的な場所となった中川低地を取り上げ、水防に対してのひとつの共同体として関わった「領」について、伊勢湾に面する木曽三川流域の「輪中」と比較しながら紹介し、特別展図録にも「中川低地の輪中~いわゆる領について~」の表題で小論を掲載した(1)。この小論については、中川低地においても輪中のようなものがあった程度を紹介したもので、問題意識も曖昧だったと思っている。そこで、今回も調査などはまだ不十分ではあるが、中川低地における輪中的景観の保存や輪中意識の必要性を目的に、もう一度整理しておきたいと思う。
2. 輪中とは
木曽三川における輪中については、多くの著書が刊行されている。そのいずれにおいても共通して捉えられているのが、輪中とは単に堤防で囲まれた地域ということよりも、生命財産を水害から守るための共同体であるということである。
明治前半に起こった数々の利根川流域における水害は、明治三十三年から始まる利根川改修工事(第1期から第3期にわたり、その終結は昭和五年)を促し、それまでの低水工事から高水工事へと治水のスタイルを変換させた。その後も昭和十三年の洪水、昭和二十二年カスリーン台風などの水害を受け改訂が重ねられてきた。その結果大洪水の危険性は薄くなってきたように思われるが、それとともに、流域住民の洪水にたいする意識も薄れつつある。それは「輪中意識」という言葉に代表される住民の水防意識であろう。
3. 「領」について
「領」は、宮村忠氏によって1981年に論じられた「利根川治水の成立過程とその特徴」の中で「水利及び堤防によって利害を等しくする一団の区域」と定義づけられている(2)しかし、「領」は最初からそのような定義のもとに発生したわけではなかった。「領」という名称は中世からあり、戦国大名北条氏が設定した在地領主のための支配領域のことだったらしい(3)。これが全ての「領」の発生に結びつくとは思えないが、いくつかの領はそうであったろうし、後出した単位にもひとつの伝統的な単位名称として「領」が付されたものと思われる。
4. 水利共同体としての領
それではいつ頃から「領」に、水利を共にする共同体としての意味が生ずるのであろうか。『八潮市史』(4)によると、寛永十二年(1643)の「村毎堀浚実施触」からは何らかの水路組合の組織化が指示されていたとの指摘があり、延宝八年(1680)には瓦曽根溜井組合が八條領、谷古田領、淵江領で組織されたのに続き、天和元年(1681)には綾瀬川の藻刈組合が150か村で組織されたという。これらは、藻刈や川浚いをすることで、水流を良くするための治水対策を行った組合と捉えられる。別表に見るように、近世前期には江戸川の開削を含む利根川東遷事業をはじめ、多くの水路開削事業が実施されている。用水堀や悪水落は、中川低地の新田開発に伴って必要不可欠な要素であった。おそらく開発初期の段階では、水害を意識しての防衛共同体というよりも、新田開発に伴い沼沢地を灌漑するするための治水が先行されたものではないかと思われる。いずれにしてもこの頃、領=水利共同体という意識が起こったのであろう。また堤防についても、「囲堤」という表現の築堤工事が行われている。市町村史等から管見したものはほんの一部に過ぎないのであろうが、以下のとおりとなる。
慶長年間(1596~1615)には、伊奈忠次により川島堤が築かれている。元和年間(1615~1624)には吉見領の周辺に、伊奈忠次による囲堤が築かれている(5)。慶安年間(1648~1652)には川島領に、松平信綱による囲堤行われている(6)。安永六年(1777)には小合溜井の囲堤が築かれるが、その10年後の天明七年には、二郷半領の戸ケ崎村と寄巻村が囲堤を掘り割り、悪水を古利根川に流したことで、二郷半領80か村西葛西領、淵江領、八條領の62か村に訴えられるという事態が起こっている(7)。
5. 中川低地における輪中的景観
図(省略)に示すように各領は広範で、多くは水除堤で区切られている。
水除堤は、河川の流路に沿って形成された自然堤防や沼沢地を取り囲むように形成された自然堤防が基となっている。そして、各領は人工堤防である水除堤と自然堤防を巧みに利用して自らの領を水害から守っている。次に主な「領」とその内側に見られる輪中状地形について、宮村忠氏作図の水除堤の位置(前出宮村氏論文掲載)などをもとに考えてみたい。
(1) 南川辺領
現大利根町である。北側は利根川と接する人工堤防、他3方は自然堤防上に築かれた人工堤防により囲まれる。この部分の利根川は、東遷事業により新たに開削された新川であるから、自然堤防はもとからなく、人工堤防のみである。この人工堤防は、昭和二十二年のカスリーン台風で決壊した。
(2) 島中領
現栗橋町である。北側から東側にかけて旧渡良瀬川の自然堤防が発達するほか、自然堤防がほぼ全周し、また人工堤防によっても囲まれている。北西部は発達した自然堤防と南川辺領との境の間に開口部があるが、これは南川辺領側からの出水の際、当領北西部の自然堤防の手前で下流に流出させるためであろう。
(3) 鷲宮町鷲宮~幸手市幸手付近
北側は、権現堂川につながる島川の自然堤防上に造られた人工堤防が旧権現堂川に沿って関宿付近まで延びる。西・南側は大落古利根川の自然堤防上に築かれた人工堤防に守られる。東側には杉戸町高野付近から幸手市権現堂付近まで自然堤防が発達している。このうち、鷲宮町側からさらに北西から南東にかけて自然堤防により分けられるためか、東大輪・西大輪の地名がある。
(4) 大島新田
大島新田の開発は、享保八年大島清兵衛が沼地を干拓することにより完了した(8)。新田の周囲には付廻堀と呼ばれる排水路を掘り巡らし、掘り上げた土で堤防を築き入植者達の居住地とした。現況で見る限り、この盛土は決して高いものではない。現水田面よりプラス50cm位であろう。現在でも大島新田を囲むように集落がある。自然堤防は、新田の外周よりもさらに500m~800m外側に環状を呈して見られ、かつての沼の範囲を知ることができる。
(5) 越谷市花田付近
南側は元荒川の自然堤防上に築かれた人工堤防、西側は堰場から北越谷駅付近に自然堤防、北・東側は大落古利根川により形成された自然堤防と、周囲を堤防により囲まれた地域である。花田の地名はかつての美田を表しているのではなかろうか。
(6) 岩槻市末田付近
北側から東側にかけて元荒川右岸の自然堤防上に築かれた人工堤防があり、西側から南側は、大宮台地の東側と綾瀬川左岸から鈎上、北後谷、砂原を結ぶように自然堤防がある。後者の自然堤防は、上流での出水時は一時的に遊水池の機能を果たせるものと思われる。
6. まとめ
以上述べてきたように、水利共同体としての「領」は、沼沢地や蛇行する河川によって時に水害の起こされる低地を開発する段階で発生した。「領」の本質的意味合いは、支配領域等に用いられるそれだったのかもしれないが、低地という環境が故、水田を開発しなければならなかったし、水害の危険性もあったのである。このような環境のもとでは、輪中的集団の発生は必然的なものと考えられる。人工堤防のみでは完全輪中を呈さない中川低地の「領」では、自然堤防を利用することで輪中状の形態を有し、特徴ある水防地形を形作っている。
また、「領」における治水構造は、周囲に強固な堤防を巡らせることよりも、排水路の整備を主としていたように思われる。そのため、下流側からの出水に対しては、完全囲堤の形態をもって対応するのではなく、次のような形の対応策があったと考えられる。
- いわゆる控堤の構築や境道が小規模な洪水に対して十分対応できた。同様に自然堤防をうまく利用して水害に対応している。
- 溜井や自然堤防に囲まれた沼などに遊水池としての機能があったと思われる。
- 逆水除の水門の多用。近代になると当該地を中心に関東地方では煉瓦造りの水門が多く造られるようになった(9)。近世においては材質こそ異なれ、同様の施設が設置されていたものと思われる。煉瓦造りの水門の多用は、深谷に煉瓦工場を控えていたことが大きな原因であるが、まさしく当該地の地域的特色を表した治水構造のひとつであろう。
- 少なくとも八潮市・三郷市より上流では、高潮の被害を考える必要はなかった(潮止の地名がある)。逆にそれより下流では当然高潮対策が必要だったと考えられるが、この点は未調査である。なお、高潮対策事業が本格的に取り上げられたのは、昭和九年三月の東京市会で議決された「東京湾高潮防御計画案」(10)である。
別表 中川低地における利根川東遷以後の主な開発
| 施設名 | 年 | 年 | 施工者 | 目的・用途 |
|---|---|---|---|---|
| 利根川瀬替え着手 | 文禄二 | 1593 | 伊奈忠次 | |
| 亀有溜井施工 | 文禄二 | 1593 | 伊奈忠次 | |
| 利根川左岸堤防 | 文禄四 | 1595 | 荒瀬彦兵衛 他 | |
| 瓦曽根溜井 | 慶長年間 | 1596~1615 | 伊奈氏 | 八條領・葛西領を灌漑 |
| 備前堤 | 慶長年間 | 1596~1615 | 伊奈忠次 | 横堤 |
| 玉井堰用水 | 慶長七 | 1602 | 伊奈忠次 | 熊谷市北西の田を灌漑 |
| 奈良堰用水 | 慶長七 | 1602 | 灌漑 | |
| 備前渠用水 | 慶長九 | 1604 | 伊奈忠次 | 深谷領灌漑 |
| 吉見領周辺囲堤 | 元和年間 | 1615~24 | 伊奈忠治 | 吉見領 |
| 赤堀川開削 | 元和七 | 1621 | 伊奈忠次 | |
| 新川通り・赤堀川開削 | 元和七 | 1621 | 伊奈忠治 | |
| 幸手用水 | 元和九 | 1623 | 大河内久綱 | 幸手領用水・悪水落とし |
| 中条堤 | 寛永年間 | 1624~44 | 伊奈忠次 | |
| 中島用水 | 寛永年間 | 1624~44 | 庄内領・松伏領の用水 | |
| 松伏溜井 | 寛永年間 | 1624~44 | 伊奈氏 | |
| 中島用水 | 寛永年間 | 1624~44 | 庄内領・松伏領の用水 | |
| 松伏溜井 | 寛永年間 | 1624~44 | 伊奈氏 | |
| 中島用水 | 寛永年間 | 1624~44 | ||
| 伝右川 | 寛永五 | 1628 | 伝右衛門 | 干拓地の悪水落とし |
| 荒川瀬替え | 寛永六 | 1629 | 伊奈忠治 | |
| 見沼溜井 | 寛永六 | 1629 | 伊奈忠治 | 水源 |
| 新綾瀬川開削 | 寛永七 | 1630 | ||
| 江戸川 | 寛永十二 | 1635 | 伊奈忠治 | |
| 佐伯渠 | 寛永十二 | 1635 | 伊奈忠治 | |
| 北河原用水 | 正保元 | 1644 | 伊奈忠治 | |
| 川島領囲堤 | 慶安年間 | 1648~52 | 松平信綱 | 川島領 |
| 琵琶溜井 | 万治年間 | 1658~61 | 伊奈氏 | 幸手領の灌漑 |
| 神扇輪中堤 | 万治年間 | 1658 | 新田開発 | |
| 安戸落・倉松落 | 万治二 | 1659 | 排水 | |
| 幸手用水 | 万治三 | 1660 | 伊奈忠克 | 本川俣から取水 |
| 島川(中堀)成立 | 万治三 | 1660 | 羽生領の悪水落し | |
| 大境道 | 寛文二 | 1662 | 八條村と柿木村境(控堤?) | |
| 不動堀 | 延宝二 | 1674 | 二郷半領の悪水 | |
| 越谷領出羽堀 | 延宝三 | 1675 | 会田出羽 | 綾瀬川沼沢地の干拓 |
| 大場川 | 延宝三 | 1675 | 二郷半領の干拓 | |
| 将藍川開削 | 延宝四 | 1676 | ||
| 綾瀬新川疎削 | 延宝八 | 1680 | 谷古田領内の用水 | |
| 倉松沼廻り囲い土手 | 元禄九 | 1696 | ||
| 東葛西領用水 | 享保年間 | 1716~36 | 井沢為永 | |
| 大島新田 | 享保八 | 1718 | 大島清兵衛 | 開発 |
| 葛西用水 | 享保九 | 1719 | 伊奈忠達 | 川俣取水から各溜井を通る |
| 見沼代用水 | 享保十三 | 1728 | 井沢為永 | 見沼に代わる用水 |
| 庄内古川江戸川落ち口替え | 享保十三 | 1728 | 井沢為永 | |
| 飯沼・見沼干拓 | 享保十三 | 1728 | 井沢為永 | |
| 小合溜井 | 享保十四 | 1729 | 井沢為永 | 溜池 |
| 中川成立・亀有溜井撤廃 | 享保十四 | 1729 | 古利根川を排水路にする | |
| 小合溜井囲堤 | 安永六 | 1777 |
参考文献
- 『江戸川区史第1巻』1976年、江戸川区
- 『鷲宮町史通史中巻』1986年、鷲宮町役場
- 『新編埼玉県史資料編13』1983年、埼玉県
- 『新編埼玉県史通史編3』1988年、埼玉県
- 本間清利「河川用水の沿革概略ー埼玉県東部を中心として」『草加市史研究第5号』1988年、草加市
- 杉戸町史編さん室『杉戸町の歴史』1989年、杉戸町
- 八潮市史編さん委員会『八潮市史通史編1』1989年、八潮市役所
- 幸手市史編さん室『幸手市史自然環境編1』1994年、幸手市教育委員会
- 三郷市史編さん委員会『三郷市史第6巻通史編1』1995年、三郷市
註
- 拙稿「中川低地の輪中~いわゆる領について~」(『忘れまい大洪水~カスリーン台風回顧展』1997年、千葉県立関宿城博物館)
- 宮村忠「利根川池水の成立過程とその特徴」(『アーバンクボタ19』1981年、久保田鉄工株式会社)
- 三郷市史編さん委員会『三郷市史第6巻通史編1』1995年三郷市 453頁
- 遠藤忠「第2章河川改修と用悪水路の開削」(『八潮市史通史編1』1989年、八潮市役所)
- 『新編埼玉県史資料編13』1983年、埼玉県
- (5)に同じ
- (3)に同じ
- 杉戸町文化財専門委員会『大島新田の歴史と民俗第1集』1982年、杉戸町教育委員会
- 是永定美「明治期埼玉県の煉瓦造・石造水門建設史」(『土木史研究17号』1997年、土木学会)
- 東京都葛飾区『増補葛飾区史中巻』1985年
(おかだ みつひろ:千葉県立関宿城博物館研究員)
『千葉県立関宿城博物館研究報告』第2号、1998 所収