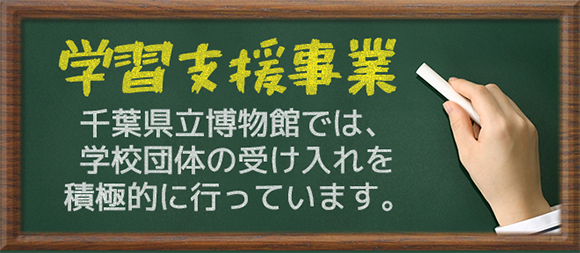中川低地の輪中 ~ いわゆる領について ~
~ 岡田光広 ~
1. はじめに
「輪中」といえば、木曽川・長良川・揖斐川の三川に挟まれた濃尾地方の木曽三川が有名である。
平成9年度特別展「忘れまい大洪水~カスリーン台風回顧展」の中で木曽三川と利根川・荒川流域に見られる水とのたたかいを紹介したが、「輪中」自体がまだまだ研究者間の専門的用語であり(1)、一般にはよく知られていないと聞く。実際には小学校4年生向け社会科教科書で「国土とくらし」という大単元(2)で扱われるが、さらに中川低地をはじめとする地域で用いられる「領」という概念(3)に至っては、一般に紹介されることは極めて少なく、かつて宮村忠氏によって論じられた「利根川治水の成立過程とその特徴」(4)の文中で「現在の中川流域は、自然堤防を利用した輪中状の控堤群の代表的な地域であった。
この地域は「領」の名称で境され、水利及び堤防によって利害を等しくする一団の区域があった。」と述べたものが近年刊行の利根川治水関係の書籍上に引用されている程度である。
ここでは、特別展を機会に調査し得たいくつかの資料と先学の解釈を元に、あらためて「領」について考えるきっかけを作りたいと思う。つまり、一応目的とするものは、「領」が「輪中」とどのように異なり、さらに研究を進める上で何が問題となるのかを提示することである。
2. 中川低地の地理学的歴史
今から約10,000年前に最後の氷河期であるヴェルム氷期が終わり、約6,000年前の縄文時代に、最も温暖な時期を迎え海水面が上昇していた。これは縄文海進あるいは有楽町海進と呼ばれており、当時の東京湾(古東京湾)が関東地方を現在よりも大きく抉っていたことが栃木県都賀郡藤岡町付近の貝塚の所在などから理解することができる。
その後再び気候の冷涼化に伴い海岸線は後退し現在に至っているが、海岸線が後退するときに中川低地にも大小の河川とともに多くの湖沼地及び沼沢地を残していった。また、流路の定まらなかった河川が氾濫を繰り返し、その度に自然堤防と後背湿地を形成した結果、次第に輪中状の自然堤防が発達し、そこに集落が営まれるようになったのである。明治15年前後に測量が実施された陸軍迅速図上で見る限りにおいて、当地域には平沼村、長沼村、皿沼村などの「沼」のつく地名がひじょうに多い。次に自然堤防によって囲まれた様子がよくわかる現在の春日部市赤沼を例に、中川低地における輪中状地形を考えてみる。
赤沼の北西から南東に庄内古川が貫き、その西側には古利根川が流れている。両川とも赤沼付近では比較的直線的に流れているが、下流域ではいずれも蛇行が激しい。庄内古川の両岸には赤沼村、水角村、銚子口村、永沼村などの記載が見られ、集落が自然堤防上に点在している。自然堤防は輪中のように環状となるが、地形自体は自然発生的である。また、この環状を呈する自然堤防は赤沼村などの地名から旧沼沢地の周囲に形成されたものと考えられる好例であろう。
では当地域の新田を中心とする開発はいつ頃から始まっているのであろうか。江戸時代前期においては、伊奈忠次による灌漑用水の開削によって羽生領、忍領を中心とする広大な範囲の開発が始まっている。忠次による灌漑は基本的に湖沼地・沼沢地を人工的に排水して低湿田とする方法だったようである(5)。実際には中世段階から小規模な水田耕作が行われていたが、この際に人的労働力がどのような契機をもって開発に当たったのかを知ることは、「領」の成立要因とも強く関わっていくものと考えられる。小出博氏は、開発に当たった農民の移住が武士団によるものかもしれないと考え、もしそうであれば、低地の開発に足場を作った先駆者として武士団を評価できるとしている(6)。
3. 輪中との比較
輪中と領を比較する前に、輪中についての定義をいくつかの文献から引用して紹介しておくことにする。
伊藤安男氏はその著書『輪中』(学生社、昭和54年発行)の中で、輪中は「外部形態としての輪中堤を意味するものではなく、内部構造の社会形態をも含めて定義すべきであろう」と述べ、さらに堤防が決壊してもその被害を最小限に止めるような住民の水防意識=輪中意識の必要性を説いた。
また、安藤万寿男氏はやはり『輪中』と題された著書(大明堂、昭和63年発行)の中で、「輪中は水害から人々自ら生命財産を守ると共に、その生産の基盤である耕地を同時に防衛するところに輪中の輪中たる所以がある。」と述べている。
いずれもその定義付けに共通することは、一般によく言われる「輪中とは堤防で囲まれた地域」ということよりも、生命財産を水害から守るための共同体であることに重点が置かれていることである(7)。
領と輪中の両者は、そこに住む人々の意識を中心とするソフト面では共通するが、現状での景観や地理的条件は著しく異なっている。領内にはいくつもの村が存在したが、ひとつの村だけでは行えないような規模の大きい治水事業は領を単位に行っていた。現三郷市を中心とする範囲にある二合半領でも80以上村があったという。
また、比較的上流に位置する鴻巣領や菖蒲領では、上流方面からの出水のみ注意すればよかった。山側からの出水は、低地の宿命ゆえ受容せざるを得なかったが、破堤等で一度流入してしまった水は、一刻も早く自領から追いやらなければならなかったのである。このような条件下では控堤が完結するところは少なく、下流側が開口したいわゆる尻無堤の形態をとっている。このことは、河川本流に沿った自然堤防を基礎とする連続堤が破堤した場合、上流部の領から順に濁水を貯めることにはなるが、下流への流入時間を遅らせるとともに、減水時には領内に濁水を止めず、復旧を早める効果があったのだろう。
現在の中川低地の住民間においては、確実に水防共同体という意識は薄れつつあり、控堤の存在すら知る人はほとんどいない。たしかにカスリーン台風以後、この地域を襲った大きな水害はなく、建設省はじめ各自治体の治水に対する努力は評価されるべきであるが、今後は住民レベルにおいて、よりいっそうの水防意識を高めていかなければならないだろう。
一方、木曽三川においては昭和34年の伊勢湾台風以後も度々水害に見舞われている。一時開発とともに取り壊された輪中もあったが、いわゆる9.12水害(8)以降再び輪中の重要性が論じられている。これはこの地域に海抜0mよりも低い場所が多いことから、高潮の被害に対する警戒が相変わらず必要であることにも起因すると思われる。このことは完全囲堤の形態を多く取る輪中も、成立の初期の頃には下流部が無堤部となる尻無堤の形態をとることが一般的であり、その後逆水除堤(干拓型の輪中では潮除堤と称した)を築くことで囲堤の輪中となっている(9)ことからもわかるように、木曽三川では下流側からの出水にも備えなければならないのである。現在では、かつての輪中堤も自動車の通行のために道路部分を切除されることが多くなったと聞くが、それでもその部分には開閉式の水門が設けられている。
註
- 伊藤安男『輪中』学生社、1979
- 単元名は各教科書によって若干異なるようである。
- 註4の宮村文献の引用文「水利及び堤防によって利害を等しくする一団」であり、輪中・領のほかに、曲輪・郷・輪の内という名称を用いる地域もある。
- 宮村忠「利根川治水の成立過程とその特徴」アーバンクボタ19(特集利根川)久保田鉄工株式会社、1981
- 小野文雄「前期の新田開発」『新編埼玉県史通史編3』第4章第3節、1988
- 小出博『利根川と淀川』中公新書、1975
- 江戸川流頭部に近い茨城県の五霞町は現在の利根川、かつての権現堂川が残した堤防に囲まれた輪中状の町であるが、もともと町の大部分は台地上に位置する。堤防に囲まれているからと言って一概に輪中とは呼べない代表的な区域といえよう。
- 昭和51年9月に襲来した台風17号は、西日本を中心に豪雨をもたらした。9月12日、岐阜県安八町長良川右岸の堤防が決壊し、周辺4,000戸以上の家屋が浸水した。
- 大垣輪中研究会編『大垣輪中調査報告書』大垣市教育委員会、1988
(おかだ みつひろ:千葉県立関宿城博物館研究員)
『平成9年度特別展図録 忘れまい大洪水~カスリーン台風回顧展~』1997、千葉県立関宿城博物館 所収