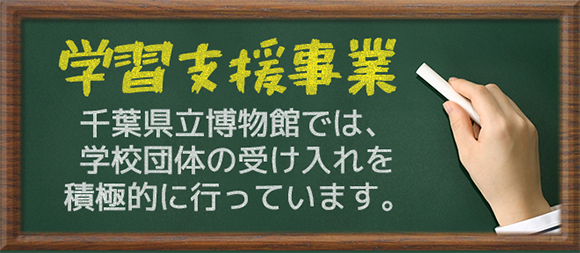|
第229号(平成31年3月) 2019.3 ――――――――――――――――――――――――――――――――――― せきはく豆事典「関宿藩主が就いた幕府の職制-大坂城代-」 ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 江戸幕府が西国に設置した出先機関の内、特に重要なものとして京都所司代と大坂城代があります。大坂はかつて豊臣秀吉が築いた大坂城があった軍事上の要地であり、瀬戸内海や淀川を航行する船によって全国の物資が集まり、商業・金融業が非常に発達して京都を上回る人口を有する大都市でした。 幕府は大坂冬の陣・夏の陣で豊臣氏を滅ぼし、新たな大坂城を再建し、大坂を直轄地として大坂城代を置きました。城代とは城の持ち主である徳川将軍に代わって城を守る重要な役職です。城代は、大坂城の他に駿府・伏見(元和5年に廃止)・京都(二条)の城に置かれました。特に大坂城代は重職なので、前職が奏者番や寺社奉行の5万石以上の有力な譜代大名が就任しました。 大坂城代の最も重要な役割は、幕府の西国統治の要である大坂城を警備すること。そして大坂に在勤する諸役人を統括し西国大名を監察することでした。また大坂周辺の地域の訴訟も扱いました。さらに京都所司代と同様、幕閣の重職を担い幕府の最高裁判機関である評定所(ひょうじょうしょ)の構成員として、幕政の重要政策の審議などに携わりました。 関宿藩からは久世広明が明和6年(1769)~安永6年(1777)まで就任しています。大坂城代就任後は京都所司代や老中へと進むことが多く、関宿藩主久世広明も大坂城代から京都所司代などを経て天明元年(1781)に老中に就任しています。 (尾崎 晃)
第228号(平成31年2月) 2019.2 ――――――――――――――――――――――――――――――――――― せきはく豆事典「地域に残された建造物の保存と活用」 ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 近世の関宿城下には、内河岸・向河岸・江戸町・台町・元町・境町などの町がありました。しかし、残念なことに、現在は江戸町周辺に外堀や土塁跡・筋違いの十字路等など、当時の関宿城のものと思われる遺構はあっても、古い町並みは全くと言っていいほど残っていません。それには度重なる洪水や河川改修など様々な理由があるかと思いますが、やはり、明治2年(1869)の版籍奉還(はんせきほうかん)により土地と人民を政府に返還したこと、同4年の「廃藩置県」、そして同6年の「全国城郭存廃ノ処分並営兵地等撰定方」(俗にいう廃城令)により関宿城が廃城になり周辺地域が廃れたこと、さらに、明治期になると鉄道や道路などの交通網が整備されるようになり、今まで日光東往還の往来や水運で栄えていたこの地域にダメージを与えたことなどが、主な原因ではないかと思われます。 では、町並みや建造物の保存に関する国内各地の動きはどうだったのでしょうか。 例えば、ある宿場町を例にとると、その地域は明治以降、鉄道網・道路網が整備されたことにより宿場としての機能を失い、町は衰退していきました。また、昭和30年代になると主だった産業もないため、若者が都市部へ流出し、過疎化がさらに進みました。 しかし、40年代になると折からの観光ブームからとり残された宿場を観光地として保存・活用できないかとの話が地域住民からあがり、学者や専門家の意見を聞く一方で、地域住民と行政が町並み保存の必要性などを話し合い、一体となって町並み保存へと舵(かじ)を切りました。その結果、町は観光客により活気を取り戻し、産業ができた事により若者の定住化も進みました。 そして、昭和50年(1975)には文化財保護法が改正され、昔からある町並みを国としてきちんと整備・保存していく伝統的建造物群保存地区の制度が発足、城下町や宿場町など全国各地に残る歴史的な集落・町並みの保存がその建物単体でなく、地域と言う面的な広がりのある空間として保存できることになりました。また、この制度は、住民が転居することなく、その家屋で暮らしながら保存するということが前提となっているので、外観を変更する際の制約などはあるにせよ、建物内部の改装などは、今のライフスタイルに合わせて比較的自由にできるようになり、多くの民家が再生・利用されるようになりました。 現在、この地域では、関宿城周辺の町並みを再現しようと言う構想が商工会を中心に練られています。古い建物の保存ではありませんが、いつしか関宿城下が当時のような賑わいを見せてくれることを楽しみにしています。 (谷鹿栄一)
第227号(平成31年1月) 2019.1 ――――――――――――――――――――――――――――――――――― せきはく豆事典「関宿城下の天王祭り(2)~“天保の改革”のみせしめとなった関宿の祭り~」 ――――――――――――――――――――――――――――――――――― (今回は講談調でお読みください) 江戸時代に「見物群衆なす、はなはだ賑(にぎ)やかにして近国にまれなり」(『関宿土産』)と謳われた、関宿城下の江戸町・台町の天王社(現在は香取神社に合祀)祭礼。 ところが天保12年(1841年)、老中、水野忠邦が打ち出した「奢侈(しゃし)禁止令」により、ぜいたくは禁止とあいなった。世にいう、「天保の改革」の一環である。とはいえ、贅を競い合い、町の誇りでもあった祭り。そう簡単には変えられない。それまでだって贅沢を禁ずるお達しはたびたび出されていたけれど、大したことはなかったと、やっぱりいつも通りに華やかな祭りを続けていた関宿城下の町人たち。 しかし、時は天保13年(1844)、陰の暦で6月13日の夜。関宿江戸町の天王祭にて、狂言の催しも準備万端、また雇い入れたる踊り子、囃子方を乗せた立派な山車がいざ出番、というところに、泣く子も黙る「関東取締出役」、今でいう公安警察が踏み込んできたから、さあ大変。 なんと喧嘩っ早い関宿の町の衆は、逆に関東取締出役の一行に棒やら梯子やらで打ちかかるは、石や瓦を投げつけるはの大暴れ。しかもなんと、それを指図したのは、祭りの現場を取り仕切っていた関宿藩家臣で同心役の須釜半助というおさむらい。関東取締出役側では、道案内役、手先の者たちがやられてかなりの手傷を負った様子。更に騒ぎは膨れ上がり、いつもは通れぬ関所の川通りを無理に押し渡る者やら、仲間を集めて領主へ強引に訴えようと企てる者まで出る大事件となってしまった。 その後、これら首謀者はしょっぴかれて取り調べを受け、百数十人の者達が罰金を科されたり、手鎖の刑に処せられたり、はたまた追放になったりしたのである。更にそそのかしたとされる同心の須釜半助は、町人達をかばおうと「関東取締役が屋台に乱暴を働いたからだ」などと訴えたが、これがまた虚偽申請であるとして、結局、死罪を仰せつけられた(その後病死)。 なかなかに厳しいご処分である。譜代藩で江戸にも近い関宿の祭りが、「天保の改革」のいわば見せしめにされた訳である。 その後、この祭りはしばらく中断されていたが、明治4年には再び、復活したらしい。現在、江戸町・台町ともに香取神社の祭礼として豪奢な神輿が出され、賑やかな祭りが続けられている。 参考:野田市郷土資料館『野田の夏祭りと津久舞』所載「下総国関宿渡場祭一件裁許書写」 (幸手市惣新田・増田境栄家文書)及び「御裁許書写」(千葉県立関宿城博物館蔵) (榎 美香)
第226号(平成30年12月) 2018.12 ――――――――――――――――――――――――――――――――――― せきはく豆事典「煉瓦と近代化」 ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 明治150年だった今年も残すところわずかとなりました。今回は、日本の近代化の象徴としての煉瓦建築について振り返りたいと思います。 明治政府による改革と同時に、当時の人たちは西洋から様々なものを取り入れてきましたが、建築材でそれを代表するのが煉瓦だと思います。最初に煉瓦建築が普及する契機となったのは、明治5年(1872)に起こった東京銀座での大火でした。従来の木材家屋により延焼が広がったことから、火災に強い煉瓦街を作ることになったのです。その建設には大量の煉瓦が必要となるため、早速、小菅に煉瓦製造所が設立されました。煉瓦街の設計や小菅煉瓦製造所における窯の築造・煉瓦焼成には、英国人技師のトーマス・ウォートルスの指導を受けています。 また、明治19年(1886)政府は官庁集中計画に着手しました。これに伴い明治21年、埼玉県深谷に日本煉瓦製造会社が設立されました。同じ年、栃木県野木町に下野煉瓦製造会社も設立されました(操業は明治22年末から)。これら二つの煉瓦製造施設は、国内に現存する煉瓦窯4か所のうちの2か所で、いずれも重要文化財に指定されています。この官庁集中計画は当時外務大臣だった井上馨が中心となり、ドイツ人技師らとともに進められましたが、当初の壮大な計画は縮小され、煉瓦建築として建設されたのは結局大審院と司法省だけでした。いずれも煉瓦に鋼材を埋め込むなどの工法により強度を高めていたため、関東大震災にも耐えることができました。戦後、大審院は最高裁判所として使用されましたが、昭和51年(1976)に取り壊されています。残された司法省の建物は法務省本館として使用され、現在は美しさと威容を兼備した歴史的構造物として重要文化財となっています。 明治東京の都市計画では、鉄道の整備においても煉瓦が象徴的に用いられました。煉瓦造りの駅舎といえば東京駅ですが、竣工は大正3年(1914)でした。その頃既に新橋から西や上野から北に向かっては、鉄道敷設がかなり進んでいましたが、都の中央部は鉄道馬車があったものの、明治の終わり近くまで鉄道の空白地帯でした。この地帯は既に都市化が進み、用地の取得や鉄道の立体交差構想が難問となっていたからです。幾多の審議を経て明治33年(1900)に始まった煉瓦高架橋の工事は、新橋から中央停車場(東京駅)の仮駅だった呉服橋駅までの区間で行われました。明治43年(1910)に完成し、以後100年以上にわたり列車の運行を支え続けています。 残念ながら銀座煉瓦街は、大正の関東大震災による火災で煉瓦塀などを残して焼失しました。確かに積み上げただけでの煉瓦建築は脆弱で、現在では耐震性の問題から一定以上の高さを超えると建築基準を満たすことができません。 以後、煉瓦建築物は急速に減少していき、建築の主役はコンクリートとなりました。しかし、昭和初期頃まで煉瓦による構造物が建築されています。耐震面やコスト的に優れたコンクリート建築の台頭は時代の流れでもありましたが、現存する煉瓦建築の多くは、温もりを感じるような煉瓦の魅力を今に伝えています。 (岡田光広)
第225号(平成30年11月) 2018.11 ――――――――――――――――――――――――――――――――――― せきはく豆事典「関宿藩主が就いた幕府の職制-京都所司代-」 ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 江戸に幕府を開いた徳川氏はその基盤を主に関東に置いていましたが、ほぼ全国に幕府領を配し、同時に重要な都市や城を直轄し幕府の出先機関を設け、地方統治が行き渡るようにしていました。特に朝廷の置かれた京都は古くから政治の中心であり、多くの寺社が集まり人々の信仰を集める土地でした。また高い工芸技術者が集まり商業も発達した江戸時代有数の大都市でした。幕府は京都をとりわけ重視し、京都所司代(きょうとしょしだい)を置き西国支配の拠点としました。 「京都所司代」とは、京都に設けられた幕府の重要な出先機関で、幕府の常置の最高職である老中に次ぐ要職です。関宿藩からは板倉重宗【就任期間 元和6年(1620)~承応3年(1654)】・牧野親成【同 承応3年(1654)~寛文8年(1668)】・久世広明【同 安永6年(1777)~天明元年(1781)】と3人の藩主が就任しています。 京都所司代の職務はまず朝廷の守護、公家や門跡の監察。そして西国大名の監視。さらに京都町奉行以下諸役人を統括し、山城国周辺の計8か国の民政や訴訟を管轄しました。また幕府の最高裁判機関である評定所(ひょうじょうしょ)の構成員として、幕政の重要政策の審議や大名・旗本の訴訟、管轄の違う奉行間の問題の裁判を行いました。 定員は1名で3万石以上の譜代大名から特に有能な者が選任されました。京都所司代になる前職は大坂城代や寺社奉行・奏者番が多く、就任後特に辞職・免職されない限りは老中へと昇格してきました。関宿藩主久世広明は天明元年(1781)9月老中に就任しています。 (尾崎 晃)
第224号(平成30年10月) 2018.10 ――――――――――――――――――――――――――――――――――― せきはく豆事典「文明開化の力(3)」 ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 近代的な国家を作るために、明治政府は新たな制度や法を整えました。そのひとつである教育制度は、人々が学問を現実に活かし、日本の近代化に貢献することを求めていました。近代日本の発展のためには、人々の力が不可欠だったからです。また、江戸時代まで幕府や藩に依存していた様々な階層の人々の生計は、明治期になり自立を余儀なくされ、生計の安定と生活の充実は、とても困難な状況であったと思われます。 その中で、幕末に国内へ海外へと販売を広げていった人々や、明治期に官営事業を買い取り、江戸時代に培ってきた技術と知識をうまく西欧の文化と融合させて民営化に成功していった人々、これからの日本を見据えて起業した人々などが次々と現れてきます。彼らは、より良い生活の充実を求め、古い因習にとらわれず、合理的な文明を積極的に取り入れようという前向きな姿勢をもつ人々でした。この姿勢こそ、啓蒙的精神であり、彼らは、いわゆる進取の精神を持っていました。 国力を上げるために明治政府が行った、資本主義を育てるための殖産興業の流れにのった人々が活躍し、明治期は経済的な発展を遂げます。そして文学・美術・音楽・科学などの分野でも多くの人材を輩出し、明治の文化も充実していきます。 文明開化は、生活上の表面的な変化だけでなく、商工業や農林水産業などの実業も確立させたといえます。それを成し遂げたのは、長きにわたる鎖国によって培われてきた技術と知恵・知識を下地とし、新しい西欧の技術と知識を貪欲に吸収し、結実させた多くの人々の力でした。彼らは、まさしく江戸時代を卒業し、その上に日本の近代化に向けた明治という時代を作り上げたといえるのではないでしょうか。 (鈴木敬子)
第223号(平成30年9月) 2018.9 ――――――――――――――――――――――――――――――――――― せきはく豆事典「文明開化の力(2)」 ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 明治中期になると、明治政府は経営の悪化が見られる一部の官営事業を民間へ払下げたり、新規の民間起業の支援も実施しはじめました。政府の保護を受けて政商となり、後に財閥となっていく浅野、岩崎(三菱)、三井、古河などの企業家たちがこの時、払い下げを受けます。また明治後期になると、政府は株式会社組織の法制化も行い、さまざまな部門での起業がさかんに行われました。 関宿は江戸時代、利根川と江戸川に囲まれた地の利を利用し、舟運の拠点として大いに栄えました。しかし、明治2年(1869)に関宿関所が廃止され、明治初期には利根川・江戸川に外輪蒸気船が就航すると、短時間の移動が可能となりました。さらに、度重なる水害で浅瀬が増えて、船の通航が困難な箇所が多くできたため、銚子と東京をつなぐ利根川・江戸川航路の短距離・短時間化を目的に利根運河が造られ、関宿を通る船は激減します。加えて、度々水害が起こったことにより、政府は河川改修の目的を、水運の整備である低水工事(水害によって溜まった川砂を取り除く浚渫(しゅんせつ)工事、高い堤防を築かず河岸場を保護する工事)から洪水対策をメインとした高水工事(河川敷を広げ、堤防を高くする工事)に切り替えます。こうして水運の町としての関宿は衰退の方向に進みましたが、関宿周辺では、利根運河の開通や日本鉄道、東武鉄道の敷設が進み、新たな輸送路が確立します。 また関宿周辺の各種産業も盛んになっていきます。江戸時代以来の野田の醤油醸造は工業機械化を進め、猿島茶製造は品質改良を行い、それぞれ輸出も積極的に行っていきます。また、埼玉県北東部では、当時輸出でトップの座にあった製糸業が盛んになり、道具や技術が向上していきます。その他、米づくりや商品作物づくりでの農業道具の改良、農作業の効率化なども進み、できた製品の輸送を新たに敷設された鉄道が担っていきました。 (鈴木敬子)
第222号(平成30年8月) 2018.8 ――――――――――――――――――――――――――――――――――― せきはく豆事典「文明開化の力(1)」 ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 江戸時代末期の嘉永6年(1853)に、アメリカの使節ペリーが来航し、幕府は翌年「日米和親条約」を締結します。その後、開国をめぐる賛否の対立が倒幕か佐幕かの対立へと変わっていきました。慶応3年(1867)、 十五代将軍徳川慶喜は大政奉還し、王政復古の号令が発せられて、江戸幕府は終わりを告げます。翌年(明治元年(1868))明治政府が発足し、日本の近代化が始まります。 転機となった幕末の開港によって、幕府だけでなく、財政難に陥っていた諸藩も海外貿易を視野に入れた経済施策をとります。また海外視察も行われ、欧米諸国の様々なシステム、技術、考えなどを吸収しました。 明治新政府は開国政策をとり、欧米に負けない経済力をつけるために国力を高める政策を行います。そのために、廃藩置県による中央集権国家の確立を図り、身分制の撤廃、職業選択の自由を認めます。視察から得たさまざまな知識をもとに貨幣制度、銀行制度、教育制度を整え、地租改正・土木・鉄道・通信といった基盤整備を行います。また資本主義経済の中心となる工業を盛んにし、民間の産業を育てる殖産興業施策の手始めに、生糸などの分野において先進技術を取り入れた工場づくりを官主導で行います。その際、「お雇い外国人」といわれる欧米の技術者を招き、先進技術の導入を図りました。また具体的な産業施策として「博覧会」も実施します。海外視察で見学した万国博覧会から、博覧会には各種製品の「展覧会」「品評会」「商品見本市」「即売会」の側面がある事を知った明治政府は、国内で「内覧会」も実施しました。 明治中期になると、欧米方式に頼りすぎていた官営による産業振興は、機械などの設備投資に資金がかかったことや日本人になじみにくい方法も多かったため、事業として振るわない分野も増えてきました。そのため、政府は民間への移行に踏み切ります。民間企業は、江戸時代から培っていた技術と欧米の技術を融合し、企業努力の甲斐もあり、成長に転ずるものも多くありました。また政府は、株式会社組織の法制化も行い、民間の起業支援も行っていきます。 資本主義を育て、欧米諸国と対抗できるよう国力を高めて国家の収入を増やし、その経済力をもとに軍備を充実させ、徴兵制度も実施する富国強兵政策を推進していきました。 (鈴木敬子)
第221号(平成30年7月) 2018.7 ――――――――――――――――――――――――――――――――――― せきはく豆事典「河川敷に棲んでいる昆虫」 ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 現在、当館3階で行っている『すごろクイズ「川辺の虫たち」』という参加型展示のクイズや、まめ知識に登場する昆虫は、河川敷の中に生息しています。この河川敷は、堤防と堤防の間を流れている河道と、その川が増水すると浸水して川幅が広がる地面からなる土地のことです。「河川敷の攪乱(かくらん)」については5月号の当メルマガでも紹介していますが、ここに大雨などが降ると、優占種の植物との競争に負けて地上では姿が見えなくなった植物の種が地中から現れ発芽するなどして、植生の変化(攪乱)が何十年かに一度起こる環境です。このような水辺の環境を好む昆虫には様々なものがいます。 その中でもフンを食べたり、1年では死なないおもしろい特徴をもつ蝶を紹介したいと思います。河川敷の中でも、土がむき出しになっている土地やヤナギ類やオニグルミを中心とした高い樹木植生を好む蝶であるコムラサキは、幼虫の時はヤナギを食べますが、成虫になると、花の蜜は吸わず、動物のフンや樹液を吸います。また、オスの翅(はね)は、光の当たりかたによって紫色に輝きます。砂利道でひなたぼっこをするものもいるので、その時が観察のチャンスかもしれません。また、河川敷の基本植生(江戸川流頭部で一番広く、基本乾燥しているが、時期により水没し、攪乱が激しい)に生息するアカタテハは、1年では死なず越冬します。アカタテハの幼虫はイラクサ科の植物を食べるため、希少種のホソバイラクサやカラムシの多いところでよく見られます。成虫になると花の蜜などを吸いますが、コムラサキと同じく、動物のフンや樹液を吸うこともあります。また、この蝶が近くを飛ぶと、力強い羽音が聞こえるようです。このように河川敷には、あまり知られていない特徴の蝶をはじめとして、さまざまなおもしろい特徴の昆虫が住んでいるのです。 (土井瑞穂)
第220号(平成30年6月) 2018.6 ――――――――――――――――――――――――――――――――――― せきはく豆事典「博物館と資料の劣化」 ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 私たちの身の周りにあるものは、程度の差こそあれ、すべて、作られたときからどんどんと劣化していきます。それは博物館の資料についても同じです。関宿城博物館では、文書や民具・浮世絵など、様々な資料を収集・保管していますが、それらの資料も適正に管理しないと、もちろん、劣化が進んでしまいます。 では、どのようなものが劣化の原因になり、どんな影響が出るのでしょうか。 見渡すと原因となるものはたくさんあります。まず、温度・湿度です。これは、具体的に言うと熱と水分になります。この中では特に水分が問題で、例えば、金属性の資料や刀剣類は高湿度で錆(さび)やカビが発生します。また、布や紙、油彩なども高湿度になると色が褪(あ)せたりカビが生えたり、強度の低下などが発生します。更に木製品・竹製品や漆、顔料では、乾湿の繰り返しで、資料にひび割れが生じたり、絵画資料などでは剥落(はくらく)も見られます。出土遺物なども、急激な湿度変化でひび割れや破損をおこすものもあります。 私たちは、毎日、日光の恩恵を受けていますが、資料のことを考えると、光も資料にとっては良いものではありません。光には目に見える可視光線と目に見えない紫外線・赤外線等がありますが、外光や照明器具から放出される紫外線により資料に退色や変質が、また赤外線によってひび割れなどが発生します。 また、資料を食べてしまうシロアリやゴキブリ・シミを初めとする様々な害虫や、カビによる被害も大きな問題です。害虫による被害は食害だけでなく、排せつ物により資料の汚損や腐食なども生じます。カビも見た目の汚らしさだけでなく、資料に食い込むことにより、物理的な劣化などを生じさせます。 その他、大気中に放出されるガスにも資料を劣化させるものがあります、まず、屋外では、工場のばい煙や自動車から排出される排気ガス、火山ガス、また、屋内では、建材や躯体・壁などに使われるコンクリートや塗料・接着剤からも有害物質が放出されます。ばい煙や排気ガスは、鉄や青銅を腐食させ、紙や木綿等を脆(もろ)くしますし、コンクリートや塗料・接着剤等の有害物質は、資料を腐食させたり変色を生じさせたりします。また、資料そのものが脆くなるなどの被害を与えます。 博物館や美術館では、収蔵している資料をただ展示や調査・研究に使用するだけでなく、数十年先、また五十年・百年先を見据えて、このような被害から資料を守り後世にきちんと伝えていけるよう、毎日様々な方策で点検・管理を行っています。 (谷鹿栄一)
第219号(平成30年5月) 2018.5 ――――――――――――――――――――――――――――――――――― せきはく豆事典「木間ケ瀬の水神様」 ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 私が17年ほど前、実際に博物館からほど近い木間ケ瀬地区のある方からお聞きしたお話しです。伝説というには、とてもリアルなお話しでしたので、ここに記しておこうと思います。 その前に少し説明をしておきますと、木間ケ瀬の慈眼院というお寺には、怪獣「カシャの爪」、もしくは「佉刃(きょじん)の爪」といわれる寺宝が残されています。昔、ある家で葬式があり、葬式行列が墓地に向かって進んでいると、一天にわかにかき曇り、激しい雷鳴と共に怪獣が下り降り、お棺を奪おうとしたそうです。その時、当院の弘道法印が法具で叩き落したところ、怪獣は爪を残して退散した、と伝えられています。 さて、お話に戻りましょう。 「ほんの6、7年前のこと。上納谷の地蔵様の裏にある水神様の社(やしろ)を建て替えることになった。それで、この社を壊そうとしていたら、ふらふらと近所のおじいさんがやってきた。普段は鼻をたらしているようなおじいさんだ。ところがこの時は急にシャンとした口調になり、「そんな簡単に壊していいと思うのか。」と言う。その場の者はぞーっとしたが、まぁ、大丈夫だろうということで取り壊してしまった。ところがこれが大丈夫どころではなかったんだ。 社には石が1つ祀(まつ)ってあったが、そこを掘ったら石が他に4つも出てきた。それらの石は、例のいわくつきの怪獣の爪のある慈眼院のものだった。それで、これは大変だ、と思って知り合いの物知りの人に話したら、それは大ごとだからすぐにお祓(はら)いしたほうがいい、ということで、きちんとお祓いをしてもらった。もう、これで大丈夫、全部済んだ、と思っていた訳だ。 ところがところが。実際に、さあ工事を始めようといって生コン(コンクリート)の車が着いた。と、思ったらあっと言う間もなく、やっぱり、慈眼院の爪の言い伝えのいわくのとおり、ライサマ(雷様)がそれはもう、すごい勢いで鳴り出して、もう、業者も何も恐ろしくてやってらんなくなって。ほっぽり出して逃げるように避難した。お昼頃になってようやく収まって何とか仕事はやったんだが、それからしばらくした頃、夢を見た。 普通は朝起きたら夢の中身なんか忘れてしまうんだが、はっきり覚えていた。それは、河童が、絣の着物を着て、俺はとにかく腹が減ってたまらないから餅をくれ、と言って出てきた。その河童には首がなかったが、不思議と怖い感じはなかった。 目が覚めてから不思議に思い、近くに河童の言い伝えなどがあるか探してみたが見つからない。そのうち、ああそうか、水神様のことだ、と思い当たり、その後、改修工事を行った7月になると、必ず餅を搗(つ)いて水神様にお供えするようになった。それは今でも続けている。」 その後、私自身も木間ケ瀬の水神様をお訪ねしていないままになっていますが、今もまだ、水神様へのお供えは続いているのでしょうか。今度、久しぶりに訪ねてみたいと思っています。 (榎 美香)
第218号(平成30年4月) 2018.4 ――――――――――――――――――――――――――――――――――― せきはく豆事典「河川敷と生物多様性」 ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 当館に近い江戸川流頭部は河川敷の環境で、河川改修に伴い、人工的に整備されたものです。洪水のリスクを避けるため、堤防と堤防の間の河川敷を広げ、通常水が流れる部分(低水路)と増水時に水が流れる部分(高水敷)に広がりました。数年に一度、高水敷まで増水することがあり、同一環境での競争に負け、地表で繁殖できなくなっていた植物のタネが地中から再び地表に現れ、発芽することで植生の変化(かく乱)が起こります。このかく乱で、外来種が優占種になりがちな河川敷内の植生がリセットされ、他では見ることが少なくなってきた植物もここでは見られることがあります。 人びとの生活に接し、利用してきた里山と違い、人工的な土地でありながらもその先に人びとの生活利用がない河川敷は、利用されなくなった里山のように、荒れた土地になりがちですが、かく乱が起こるため、自然環境がある程度維持されていると考えられます。そのため、レッドデータブックで絶滅危惧種や準絶滅危惧種になっていても、中には「生息地を過度に管理しないことが対処として望ましい」という文言が出てくることがあります。また、堤防の斜面の土を締め、緑化させるために輸入されて植えられているイタチハギなどが野生化し、在来植生の生育を阻害するなどの問題もありますが、砂防用に有用であるとして、特定外来生物には指定されていない例もあります。 河川敷は、河川による水害から我々の生活を守るためにつくられており、「多様な種類がある生物は、それぞれ直接、間接的に関わりあい、支えあって生きている」という生物多様性と一元化できるものではないと思われます。このように様々な環境ではそれぞれ人との関わりがあり、その方向性が一致してないことも多いため、今後の生物多様性の推進の難しさを感じます。 (鈴木敬子)
第217号(平成30年3月) 2018.3 ――――――――――――――――――――――――――――――――――― せきはく豆事典「関宿城下の天王祭り(1)」 ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 関宿城のお膝元、関宿江戸町・台町では、江戸時代より「天王様」と呼ばれる祭りが行われてきました。「関宿台町の天王祭礼」のほうは、野田市無形民俗文化財に指定されています。 江戸町も台町も、それぞれ氏神(鎮守)は香取神社ですが、各境内に八坂神社も一緒に祀られており、「天王祭」は正確にはこの八坂神社の祭礼です。毎年7月半ばに両町内が少し日程をずらして一週間前後の期間、祭礼を行います。江戸時代には関宿城内まで神輿が入り込むことが許され、城主の前で大きく揉んで見せたそうです。 先日、江戸町にお住まいの方から、かつて天王祭で使われていた山車の部材を博物館で預かって欲しい、という依頼がありました。どうも昭和の初め頃まで、神輿のほかに人形の乗った山車も町内を曳き回していたとのこと。拝見しに伺ったところ、山車の破風部分と扁額が残されていました。 部材の裏面には墨書銘があり、山車本体は文化3年(1806)の造営で、彫刻師は結城郡小森村(現茨城県結城市小森)の竹田重三郎であったことなどが分かりました。竹田重三郎は、栃木県小山市宮本須賀神社下町の屋台彫刻(文政2(1819)・小山市博保管)や千葉県白井市富塚鳥見神社本殿(文化9(1812)・白井市有形文化財)彫刻なども手がけており、江戸時代末期に関東で活躍した彫工師だったようです。山車本体は失われてどのような彫刻であったか、もう見ることはできませんが、他の作品を見るとなかなか見事な彫りで、こうした彫工に依頼することができた江戸町の財力はかなりのものであったと思われます。 旧関宿藩士南海友儀が関宿の様子を記した『世喜宿土産』(天保7年(1836))という書物には「毎年6月(旧暦では現在の7月頃※筆者注)に祇園祭礼があり、江戸町天王は7日より15日まで、台町は7日より12日までである。町内で年番があり祭を出す(神輿のことか?)。当日は関宿城の佐武門まで祭(神輿?)が入る。見物人が群衆をなし、そのにぎやかさは近隣の国には類を見ないほどである」と記されています。そして、この文の挿絵には、街道にあふれる人混みと「祇園祭礼」の文字が書かれた幟旗、神輿、剣の作り物などのほかに、はっきりと人形が乗った山車が描かれていました。台町の天王祭でも、古い人形山車があったそうですが、現存しておらず、今回拝見した部材等は関宿城下の山車に関する実物資料としては唯一のもののようです。 今回、博物館ではこの扁額のほうをご寄贈いただきました。上記のような山車の情報とともに、江戸時代からの関宿城下の祭礼の様子を今に伝える証拠として伝えていきたいと思います。 (榎 美香)
第216号(平成30年2月) 2018.2 ――――――――――――――――――――――――――――――――――― せきはく豆事典「明治の錦絵」 ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 明治期を代表する錦絵に「開化絵」があります。これは、明治政府が欧米化政策を積極的に推し進め、鉄道の敷設、ガス灯の設置、洋風建築、洋装・断髪などの西洋風俗の導入によって都市の風景が変化していく様子を絵画にしたものです。 新しいメディアとして、浮世絵師、落合芳幾は、東京で最初の日刊紙「東京日日新聞」(明治5年~)の創刊にかかわり、新聞錦絵の流行を作りました。同じく月岡芳年も「郵便報知新聞錦絵」(明治8年)で活躍しました。この新聞の内容は、殺人事件や刃傷沙汰、不倫などのスキャンダルといった、いわゆる三面記事が多く取り上げられていましたが、他にも西南戦争(明治10年)や、日清戦争(明治27、28年)を劇画風に生々しく1枚刷りの報道画として、それぞれ300点程度描いてもいます。 しかし、明治10年代~20年(1887~)代に入ると、明治の時代色(鮮やかな赤と紫)で強調された価格の安い錦絵は、版元の新趣向を凝らした努力もみせますが、錦絵そのものの形態や時代色とも言われた色合い自体が古臭いイメージとなり、紙質も落としていきます。そして、絵語りよりも写真のリアリティの方に人々の関心が動いていき、ついに、日露戦争(明治37年)時には、写真製版や石版画にその座を奪われてしまいます。 この赤と紫は輸入染料で、アニリン(赤)、ムラコ(紫)といい、それによって彩色された錦絵は「赤絵」と呼ばれました。新聞のジャーナリスティクな表現手法に一時期合致し、新聞メディアで隆盛しますが、伝統的な錦絵の絵画性を失わせることにもなっています。つまり、この赤こそ絵画性よりも情報発信メディアとしての役割を優先させた明治時代の錦絵の特徴なのではないでしょうか。 当館には、明治時代初期に花開いた開化絵の「東京両国通運会社川蒸気往復盛栄真景之図【歌川重清(野沢定吉)・画】」が展示してあります。怒涛の勢いで新しいメディア「新聞」で波に乗り、明治を彩った錦絵の赤に思いをはせてみてはいかがでしょうか。 (土井瑞穂)
第215号(平成30年1月) 2018.1 ――――――――――――――――――――――――――――――――――― せきはく豆事典「関宿と鉄道」 ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 関宿は関宿藩の城下町であり、日光東往還を往来する人々と利根川・江戸川の水運で栄えた町です。しかし、江戸から明治へと時代が変わると、明治4年7月の廃藩置県で関宿藩は廃止され関宿県となり、同年11月には合併により印旛県が成立し、関宿は城下町としての機能を失っていきます。 また、交通関係では、明治10年になると、銚子から利根川~江戸川を経て江戸まで物資を運んでいた高瀬船に加えて蒸気船が就航、これによって天候に関わらず高速で大量の人員・物資が一度に輸送できるようになり、関宿周辺には4つの寄航場が設けられ、水運による利便性は増すようになります。 しかし、国内に目を向けると、明治5年に新橋~横浜間に鉄道が開業、徒歩で7~8時間かかっていたのがわずか35分で行けるようになり、明治新政府は鉄道が政治や経済を始め国防などにも寄与するところが多いと考え鉄道の敷設を推進、7年には大阪~神戸間にも鉄道が開通します。その後は国の財政悪化のため、国だけでなく民間にも協力を仰ぎながら、16年には今の高崎線の一部である上野~大宮~熊谷間(日本鉄道)が、22年には今の東海道線にあたる新橋~神戸間(官営)が、24年にはほぼ現在の東北本線にあたる上野~大宮~仙台~青森間(日本鉄道)が開通するなど、東京から北や西に向かう鉄道の整備は進みました。 そのあおりを受け、当時の主要な輸出品であった生糸や絹織物の生産地である上毛地域(群馬県)と輸出港の横浜が鉄道で結ばれることになり、これらの輸送は今までの水運によるものから鉄道へと切り替わり、鉄道網の整備が進むにつれ水運での輸送は衰退し、それとともに様々な物品の集散地でもあった関宿も徐々に衰退していくようになります。 また、同時に道路網の整備も始まり、物資の運搬は、早くそして一度に大量の物資を安定的に運ぶことができる陸上の交通網にとって代わります。 そのような流れの中で、関宿にも鉄道計画が持ち上がります。それは、日東電鉄という鉄道です。日東という名前からもわかるように日光と東京(上野)を結ぶ鉄道です。昭和3年9月に東京府豊多摩郡渋谷町上智(現東京都渋谷区東)の福沢桃介(福沢諭吉の婿養子)を中心とした実業家らが、東京市下谷区上野山下町(現東京都台東区上野)を起点として、栃木県上都賀郡日光町(現栃木県日光市)に至る電気鉄道敷設の免許申請を行い、株式の募集により資金の調達を進めました。路線は現在の地名で言うと、上野~日暮里~尾久~江北~西新井~埼玉県川口~鳩ケ谷~東川口~さいたま市岩槻区~大袋~春日部~杉戸~幸手~千葉県野田市関宿~茨城県猿島郡境~古河~結城~栃木県小山~下野~上三川~宇都宮~日光で、敷設にあたっては、軌間1,067mmであること、30kgレールを使用すること、直流式1,200Vの電圧であること、東京電灯(現東京電力)から電力を供給して貰うことなどが決められていたようですが、明治32年には東武鉄道の北千住~久喜間がすでに開通しており、申請を出した時点で更に東武側は日光線と浅草雷門駅(現浅草駅)乗り入れの建設工事に着手していたため、隣接する地域から同様の方向に向かう日東電鉄は採算面での厳しさが懸念され申請は却下、関宿を通る鉄道はまぼろしとなりました。 (谷鹿栄一)
第214号(平成29年12月) 2017.12 ――――――――――――――――――――――――――――――――――― せきはく豆事典「新田開発と水塚」 ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 徳川幕府は、米の生産量を基準として、水田やその他の耕地に石高を割り当て、米を年貢として徴収する方法で全国を治めました。そのため、米の確保が重要で、新田開発が奨励されました。 もともと、河川が始まる山間や、河川沿いにつくられていた水田は、中世から近世になるにつれ、徐々に平地へと進出していきます。水田を、内陸部に広げることができたのは、用水路をつくったからです。近世になって水害対策や、輸送路の確保などのために行った河川の流路改修でできた旧河道は、用水路としても利用されました。 関東地方の水塚の成立は、新田開発と大きな関わりがあります。関東平野では、住まいは高台や微高地である自然堤防上に建てられることが多いのですが、自然堤防の後にできた平地である後背湿地(こうはいしっち)へ新田開発が進むと、水田をつくる際に掘った土を盛り上げ、そこに住まいを建てるようになります。自然堤防や後背湿地は、河川の水害にさらされる氾濫原(はんらんげん)を構成する要素であり、水害と背中合わせのため、低い後背湿地に住まいを建てるためには、防災対策として土盛りをした塚が必要でした。これらの地域では、敷地を盛土するだけでなく、その敷地内の蔵の部分もより高くし、防災対策をしています。埼玉県の中川低地や千葉県の利根川中流域に位置する栄町周辺、松戸市の坂川周辺では、水田の中に土盛りをした屋敷林に囲まれた住まいが見られ、散村の佇まいを呈しています。 関宿地域は、河川に挟まれた地域で、広い平野が広がっておらず、そのため土の調達も難しいため、敷地の一部に盛土をし、その上に蔵をつくるタイプの水塚が主流です。そういった地域では、水害により水塚も水に浸かった場合は、同じ場所に蔵を崩し、盛土して再度つくり直すより簡単な、他の場所に高い塚を築き、その上に蔵を建て直すという形をとったようです。 全国各地にある様々な水塚も、それぞれの土地に応じた形があったと思われます。その歴史的な背景を考てみてはいかがでしょうか。 (鈴木敬子)
第213号(平成29年11月) 2017.11 ――――――――――――――――――――――――――――――――――― せきはく豆事典「火縄銃と江戸時代後期の鉄砲」 ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 火縄銃は、御存知のとおり火縄式点火装置によって弾丸を発射する仕組みのもので、戦国時代後半にヨーロッパから日本に伝来し、瞬く間に日本全国に普及し、国友、堺などの産地も生まれました。 また、火縄銃の普及によって、戦の仕方や着用する甲冑、築城方法などにも大きな変化をもたらしました。江戸時代には、武士の武芸の鍛錬や戦の備えだけではなく、農民などでも狩猟や害獣駆除などの目的で所持(鑑札)が認められ、普及していたようです。 火縄銃は、銃口から火薬と弾丸を入れて火縄で点火して撃つものです。1分間に3発程度しか撃てず、雨が降ると使えませんし、銃身に溝もつけられていない古式銃ですが、甘く見てはいけません。一般的な中筒程度のもので射程距離は100m程度でせいぜい500m程度しか飛びませんが、発射したときの振動が少なく、射程内の命中精度はかなり良かったようです。パチンコ玉のような丸い弾丸で、直進安定性は劣りますが鉛製で重さがあるため、命中したときはそれなりの威力があります。弾丸の速度も現代の拳銃の弾丸よりも速いといわれています。50m以内の距離で撃たれると甲冑を着けていても胴を撃ち抜かれてしまうこともあったようです。しかも弾体としては柔らかい鉛ですので、当たった瞬間に細かく砕けて飛び散り、散弾で撃たれたようになることもありました。また、火薬の量も調節できるので、威力を上げたいときや遠くのものを狙うときには火薬の量を増やして撃つこともできました。火縄銃の銃身を見るとかなり厚めに造られていますが、こうした場合に耐えられるように造られています。 また、ちょっと変わった使い方ですが、丸い弾丸を1度に2個ないし3個入れて撃つこともありましたし、細かい弾丸をたくさんつめて、散弾銃のように使うこともありました。戦で弾丸がなくなると石などを入れて撃つこともあったようです。 こうした火縄銃ですが、細筒、中筒、大筒、長筒、馬上筒、短筒等さまざまな種類があります。火縄式ではない鉄砲としては気砲(きほう)とよばれる空気銃、火縄の代わりに燧石(すいせき)と呼ばれる火打ち石をつけてこれで叩いて発火させ発射させるフリントロック銃、火薬の入った雷管を装着し、ハンマーで叩いて発火させ発射させる管打銃等があります。いずれも弾丸を銃口から入れる前装式で、銃身内に溝が付けられていない滑空銃身のものです。 なお、江戸時代末期から明治時代になると、弾丸を手元から込める後装式の銃、銃身に溝のある施条銃、連発銃なども使われるようになります。 (村田憲一)
第212号(平成29年10月) 2017.10 ――――――――――――――――――――――――――――――――――― せきはく豆事典「関宿経由、にせもの肥料出廻り事件」 ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 前回の豆事典で、江戸時代には関宿がイワシの肥料で栄えたお話しを書きました。利根川舟運で運ばれる干鰯や〆粕は、全て銚子から高瀬船などに積んで送られて来たものでした。しかし、幕末期には鰯の不漁が続き、銚子周辺や八日市場などの干鰯生産者達も困窮したため、鰯の肥料の代わりに「肥糠(こえぬか。米糠を肥料としたもの)」を集めて糠俵(ぬかだわら)とし、関宿に出していたようです。 そんな安政4年(1857)12月、武州幸手宿(現埼玉県幸手市)において、銚子、関宿、そして北関東一円の干鰯商らが集められ、取り調べを受けた事件がありました。 銚子周辺から送られてきた糠俵が上方(かみがた)からの高級糠肥「下り俵」に似せて作られており、しかもその中身には魚の餌代わりに使っていた麦の糠や砂などが混ざっているのに、品質保証の印が押されて北関東一円の農家に出回っていたのです。これを取り次いだ関宿向河岸の干鰯問屋、また更にそこから買い付けて近在に売っていた栃木町、高崎宿、伊勢崎町、鹿沼宿、宇都宮宿、小金井宿、太田町、乙女村、古河宿、下小泉村、飯野村、大沼村、石橋宿、境町、久能村、下大野村などの干鰯商達が幸手宿に集められて、関東取締役の取り調べを受けました。関宿向河岸の喜多村藤蔵や小島忠左衛門などの大問屋達も関わっています。しかし結局、この一件では、関係各者が「悪気があった訳ではないのでお許し下さい。こんなことは以後、決してやりません。」という釈明・謝罪文を出し、幸手宿の名主たちも口添えをしてくれたお陰で、お咎(とが)め無しで皆放免されました。 このそれぞれの立場の者たちが訴えた釈明の文書が「武州葛飾郡幸手宿御用留」の中に書き留められています。鰯不漁期の房総漁民や干鰯・肥料問屋の困窮ぶりが分かるだけでなく、銚子周辺から関宿向河岸を中継点にして、関東一円に肥料が出回るルートをたどることができる好資料です。 ちなみに、明治28年(1895)の『大日本農会報』の報告によると、銚子の商人は干鰯に砂や海藻などを混ぜ、発酵させたものを俵にする。なぜ、そんなことをするのか問うたところ、この地方では昔からこうしているので、今さら本物を送っては、却って不正品と思われるから、と答えたといいます。糠俵と干鰯俵の違いこそあれ、どうも肥料に混ぜ物をする慣行は、この事件の後もずっと続いていたようです。 (榎 美香)
第211号(平成29年9月) 2017.9 ――――――――――――――――――――――――――――――――――― せきはく豆事典「鰯(いわし)で栄えた関宿の河岸」 ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 今でこそ、どちらかというと内陸のイメージのある関宿。「江戸時代、関宿は鰯で栄えた」、といってもあまりピンと来ないのではないでしょうか。今回は、そのお話しをしましょう。 現代では鰯といえばご飯のおかずですが、江戸時代には食べ物としてよりむしろ肥料として全国に広く流通していました。鰯を干しただけのものが「干鰯(ほしか)、そして鰯を茹でてから搾り固めたものが「〆粕(しめかす)」です。(以下、両方あわせた総称として「干鰯」とします。) 特に、17世紀に関西で広まった木綿栽培には、干鰯が欠かせない肥料でした。その材料となる鰯が関西の漁場だけでは不足し、紀州などの漁民達が鰯を求めて上総にやってきたのが関東の鰯網漁のはじまりです。九十九里、夷隅、銚子、安房など房総半島の海岸部は全国最大の漁場で、また最大の干鰯生産地となりました。 もともと、関西で需要があった干鰯ですから、最初の頃は作った干鰯はほとんど大坂に送られました。相模国(今の神奈川県)の東浦賀と江戸の深川の2か所が干鰯の2大集積地となり、いったんどちらかに集められた干鰯は、問屋を介して関西に船で送られました。 ところが、そのうち関東でも肥料としての効能が広まり、農村部に普及していきます。 そうしますと、銚子から利根川を通って運ばれる途中にも、干鰯を欲しがる農村部が多くなってきました。北関東では米作りにも干鰯が使われ、干鰯を取り次ぎする干鰯問屋が関宿の向河岸(現埼玉県幸手市)や境河岸(現茨城県境町)には立ち並びました。 境河岸の問屋、小松原家の文化7年(1810)の文書によれば、「境河岸は武蔵・上野・下野・下総・常陸、五ヶ国へ通船の便がよい場所で、私どもは南部・仙台また銚子周辺その他の浜の荷主から〆粕や干鰯を引き受け、五ヶ国の町や村に売りさばいてきた」との文面があります。 また向河岸随一の干鰯問屋、喜多村藤蔵家は、江戸後期に江戸の干鰯場に進出し、深川でも筆頭格の干鰯問屋となりました。(ちなみに明治11年には東京に6500坪あまりの土地を所有し、東京肥料問屋組合の初代頭取も務めています。)しかし、喜多村家の本店はあくまで関宿にあり、関宿藩にも多大な御用金を納めていました。「大和守さま(関宿藩主)五万石、喜多村さまは十万石」などともいわれたそうです。 但し、干鰯の需要は増大するのに、鰯は豊漁と凶漁の時期に波があるため、干鰯問屋は常に荷不足に悩まされていました。ですから、江戸や東浦賀の問屋達にとっては、産地から運ばれてくる途中で干鰯を関宿に降ろされてしまうと困る訳です。江戸の問屋達から意議を申し立てられることもありました。 先日、干鰯のことを調べに横須賀市の東浦賀を訪問した際、現地の歴史研究家の方に関宿から来た旨をお話しすると、「関宿は東浦賀のライバルですね」と言われました。 関宿は江戸や東浦賀にライバル視されるほどの一大干鰯集積地であり、関東内陸部への供給ポイントだったのです。 「関宿が鰯で栄えた」というお話し、ご納得いただけましたでしょうか? (榎 美香)
第210号(平成29年8月) 2017.8 ――――――――――――――――――――――――――――――――――― せきはく豆事典「近現代の関東地方の大洪水」 ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 昭和22年(1947)のカスリーン台風からさかのぼること37年前の明治43年(1910)に、関東地方で明治期最大の洪水が起こりました。停滞していた梅雨前線のため、雨模様が続いていたところに、8月6日から11日にかけて房総沖を北進した台風と12日から14日にかけて静岡県沼津市付近に上陸し、東北へ縦断していった2つの台風により、河川が増水し、堤防決壊を起こしたのです。決壊した河川は利根川、荒川、綾瀬川、多摩川などで、利根川上流部で山間部の山崩れも起こったため、土砂や流木が濁流とともに堤防を決壊させました。明治期最大の洪水で、荒川と利根川の出水があわさって南下し、埼玉県の全域を浸水させ、都内でも北区、足立区、荒川区、葛飾区、台東区、墨田区、江東区、中央区、江戸川区(現在)が浸水しました。被害は、死者679人、行方不明者78人と記載されています。(『利根川百年史』より)また、都内では溜まった水がなかなか捌(は)けず、場所によっては、排水に12月近くまでかかったところもあったようです。政府は、この洪水をきっかけとし、全国の河川に関して治水長期計画をたて、「河川改修」「砂防計画」「森林行政上治水」の3つの方向から治水を実行し、昭和5年(1930)に完成します。 しかし、利根川は昭和10年(1935)、16年(1941)にも明治43年の洪水後に策定された計画高水位を越える洪水を起こしたため、新たに利根川増補工事計画がたてられました。 カスリーン台風による洪水は、その6年後,昭和22年(1947)に起きます。ほぼ1日半という短い間に大量の雨が降ったことと、第二次世界大戦の軍事用と戦後の復興に向けて山林の乱伐を行ったことにより、山林の保水力が低下していたことが被害を増大させたと考えられています。また、この大洪水の発端となった埼玉県埼玉郡東村(現・加須市)の決壊現場は、江戸時代に人工的に開削された新川通と呼ばれる直線河道であるため、決壊するとは考えにくかったことと、明治43年の洪水では堤防決壊しなかったことから、決壊の危機感がありませんでした。しかし実際は、利根川上流部の遊水池が開発によってなくなっていたことや、下流の栗橋付近の鉄橋に漂流物か引っかかって流れを悪くしていたこと、渡良瀬川の合流地点で、増水時には流れが悪くなることなどの原因も加わり、この決壊が起こりました。この洪水後、利根川改修計画は大幅に改定され、治水のためのダム建設や調節池の整備、川幅の拡幅工事などが進み、それ以後、この規模の洪水は起きていません。 近年では、ゲリラ豪雨と呼ばれる集中豪雨による水害が増えています。水害は、悪天候だけが原因で起きるものではなく、これらの水害も異常気象という言葉だけですませていいものではありません。人々の営みがある限り、開発は起こります。様々な開発がいつ、どこで起こり、それがどのような水害につながるかという危険予測は難しいといわざるを得ません。今後の水害の予測は、大きな課題です。私たちは、水害がいつ何時でも起こりうると考え、日頃からの備えをしておく必要性を深く感じます。 (鈴木敬子)
第209号(平成29年7月) 2017.7 ――――――――――――――――――――――――――――――――――― せきはく豆事典「浅草寺の由来と関宿藩主寄進の梵鐘」 ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 浅草と言えば、ぱっと頭に浮かぶのは、観音様と呼ばれて親しまれている浅草寺と祭りで有名な三社様。このように、浅草寺は浅草の代名詞のひとつとなっています。 浅草寺は正式には金龍山浅草寺と言い、寺の縁起によると、推古天皇36(628)年、宮戸(みやこ)川(現隅田川)のほとりに住んでいた檜前浜成・竹成(ひのくまのはまなり・たけなり)の兄弟が宮戸川で漁をしていたところ、仏像が網にかかりました。兄弟はその仏像のことを何も知らず、兄弟にとっては不要なものだったので川に投げ込みましたが、網を曳くたびに仏像がかかってしまいます。しかも、魚は全くとれません。 そのため、仕方なく仏像を持ち帰り、土地の有力者である土師中知(はじのなかとも)に見せたところ、聖観世音菩薩像であることがわかり、お堂を建ててお祀りしたのが、浅草寺の始まりと言われています。 その後、大化元(645)年に勝海上人という僧がお堂を整備し仏像を秘仏としました。また、天安元年(857)年に延暦寺の慈覚大師が来寺し、現在あるお前立ちの観音像(普段見ることができない秘仏の代わりに拝むための仏像)を造ったと言われています。度重なる震災や火災により、幾度となく堂宇は壊れましたが、源頼朝や足利尊氏、徳川家康などの有力な武将の庇護により、浅草寺はますます栄え、江戸時代には、参詣・行楽・歓楽を目的とした一大観光地になりました。 この浅草寺の境内には、本堂を始め五重塔、薬師堂など様々なお堂がありますが、そのお堂のひとつに小高くなった弁天山があります。弁天山は名前の通り、弁財天をお祀りしたお堂ですが、そのお堂の脇に、鐘撞堂があります。この鐘は松尾芭蕉の句「花の雲 鐘は上野か浅草か」で有名な鐘ですが、第14代関宿藩主牧野備後守成貞が黄金二百両を寄進して、元禄5(1692)年8月に5代将軍綱吉の命により深川の太田近江大掾藤原正次が改鋳したものです。鐘の大きさは高さ2.12m・直径1.52mで、鐘銘によれば、撰文は浅草寺別当権僧正宣存のものと言われています。牧野成貞は、寛文年間に綱吉に奉仕し家老になり、綱吉が延宝8(1680)年に5代将軍となってからは、御側役、御側用人、侍従を歴任し、宝永6(1709)年に綱吉が亡くなるまで、綱吉に重用されました。そのような信頼関係があったからこそ、二百両もの大金を寄進することができたのだと思います。 なお、三社様は、この浅草寺建立のきっかけとなった土師中知、檜前浜成・竹成を奉った神社です。 ※土師中知の名前については、諸説あります。 (谷鹿栄一)
第208号(平成29年6月) 2017.6 ――――――――――――――――――――――――――――――――――― せきはく豆事典「ベロ藍と常州牛堀」 ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 江戸時代になり、世の中が安定し、経済的に力を付けてきた庶民は、享保年間(1716-36)頃から盛んに旅行に行くようになります。文化・文政期(1804-30)には旅ブームが起こり、近郊での行楽へと広がって行きます。明暦年間(1655-58)頃には、各地を紹介する名所記、道中案内記、地誌、紀行文などが次々と出版され、名所は全国的に広まっていきます。 浮世絵の風景画も遠近法を取り入れたり、精密な彫や、ぼかし等の摺の技法も発達し、多色摺へと発展していきました。色では、オランダ舶載(はくさい)の化学顔料「ベロ藍」〈ベルリン藍(プルシアンブルー)がなまって呼ばれるようになったもの〉が中国で安価に生産され、輸入されることで、多くの浮世絵に使われるようになっていきます。文政末期には、粒子が細かく、紙に摺りやすく退色しにくいこの藍は、海、川、空など、風景や自然の描写に使用されていきます。天保元(1830)年には渓斎英泉(けいさいえいせん)が藍摺を大流行させ、葛飾北斎(かつしかほくさい)も『富岳三十六景』の36図の輪郭線を藍で摺り、うち10図を藍摺で描いて人気となりました。現在、当館第3展示室に富嶽三十六景(46枚)の一枚で天保2(1831)年に描かれた常州牛堀(じょうしゅううしぼり)が展示してあります。 牛堀は現在の茨城県潮来市。霞ヶ浦の南端、利根川に近い水郷です。画面の対角線上に大きく描かれているのは高瀬船で、船頭が寝起きする場所は、雨露をしのぐ菅(すげ)や、茅(ちがや)などで編んだ、苫(とま)に覆われています。この舟は、船底が浅く、霞ヶ浦や利根川流域で盛んに使われていました。 北斎は、この船を濃淡の藍だけを用いて正確な構造で描ききっています。この図は朝食の仕度をしているところでしょうか、米のとぎ汁を船から流す音に、二羽の鷺が驚き飛び立つ姿に、緊迫感を漂わせています。そして、右下から左上へ対角線上に向けられた画面の動勢は、右上に置かれた富士により、構図の均衡が保たれて安定しています。 (土井瑞穂)
第207号(平成29年5月) 2017.5 ――――――――――――――――――――――――――――――――――― せきはく豆事典「関宿城主簗田氏(5) ―後北条氏への服属とその後の簗田氏―」 ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 永禄7年(1564)、安房国の里見義堯(よしたか)・義弘父子は足利藤氏(ふじうじ)を古河公方に擁立するため、下総国国府台(市川市国府台)に進出し、後北条氏の軍勢と衝突しました。これが第二次国府台合戦です。しかし、後北条氏は里見勢を打ち破って安房に敗走させ、上総地方の支配権を拡大させることになりました。 この後、後北条氏は、永禄8年(1565)から天正2年(1574)にかけて三次にわたって関宿城を攻撃してきました。簗田氏は、執拗に抵抗を続けながらも、かつてない危機感を感じ、和睦の道を探るなど交渉もしましたが、関東制覇を狙う後北条氏の攻撃は治まらず、第三次関宿合戦において関宿城を開城してかつての本拠地である水海(みずみ)城に逃れ、ここに落ち着くことになりました。 一方、勝利した後北条氏は、念願であった関宿の地を手に入れ、関宿城を支城として北関東への勢力拡大や支配力浸透のためのネットワーク強化を図りました。 簗田氏は、形の上では古河公方の家臣にもどりましたが、その上には後北条氏がおり、実際は後北条氏の支配下に入ることとなりました。晴助・持助父子は、公方義氏(よしうじ)の忠実な家臣として数々の働きをして忠誠を示し、公方からの信頼もあったようです。天正10年(1582)閏12月、古河公方足利義氏が亡くなり、古河公方は消滅しました。 このころからは、簗田晴助・持助父子の名前も古文書からほとんど見られなくなり、代わって助実(すけざね)、経助(つねすけ)、助縄(すけつな)といった名前が見られるようになりますが、これらは水海系簗田氏(傍流)と考えられています。古河公方の消滅を契機に関宿系簗田氏(嫡流)から水海系簗田氏へ実権が移ったと考えられています。 時は折しも、豊臣秀吉による小田原征伐の時期であり、水海系簗田氏は、後北条方につき、関宿系嫡流の晴助は浅野長政と親交があり秀吉方につきました。結果的には秀吉方が勝利をし、後北条氏は滅亡してしまいます。このことにより、水海系簗田氏は後北条氏と運命を共にし、関宿系簗田氏に実権がもどることになりました。 その後、関宿系嫡流の持助の子(弟とも)貞助とその子助吉が浅野長政の推挙を得て徳川家康に仕えますが、元和元年(1615)の「大坂夏の陣」で討死してしまいます。しかしながら、助吉の妹により簗田家再興がはかられ、子の助政に引き継がれることになりました。 この後、簗田氏は、江戸幕府の下で代々「留守居与力(るすいよりき)」を務め、明治維新を迎えました。 (村田憲一)
第206号(平成29年4月) 2017.4 ――――――――――――――――――――――――――――――――――― せきはく豆事典「関宿城主簗田氏(4) ―後北条氏の公方権力掌握と簗田氏―」 ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 天文23年(1554)10月、前古河公方足利晴氏は、不本意な家督相続への抵抗として、古河城(茨城県古河市)に立てこもりましたが、ほどなく落ち、相模国波多野 (神奈川県秦野市)に幽閉されてしまいます。一方、後北条氏の血を引く第5代古河公方の梅千代王丸(うめちよおうまる)は小田原に移りました。簗田晴助はこれらには深く関与はしなかったようです。 弘治元年(1555)に梅千代王丸は小田原の後北条氏のもとで元服し、将軍足利義輝から「義」の字をもらい(偏諱:へんき)「義氏」(よしうじ)と名乗りました。 しかしながら、まだこの段階では、古河公方家の最高家臣としての簗田氏の存在や意向を無視できず、後北条氏の公方権力掌握はまだ不完全なものでした。 北条氏康は、弘治2年(1556)10月に義氏を鎌倉の葛西ケ谷に移し、永禄元年(1558)8月には、義氏を古河に戻さず簗田氏の本拠の関宿城に入れ、ここを古河公方の御座所としました。その代わりに簗田氏には古河城が与えられました。こうして、後北条氏は重要な戦略的拠点である関宿を手に入れ、一方簗田氏にとってはこれが大きな痛手となりました。 永禄3年(1560)8月、越後国(新潟県)の長尾景虎(かげとら)(上杉謙信)が関東に進出し、後北条氏の支配下にある関東の城を次々と攻略し、永禄4年(1561)閏3月には小田原城まで迫りますが、後北条氏が籠城して攻めあぐねたため、しばらくすると小田原を引き上げてしまいます。その後、長尾政虎(上杉謙信)は、関東管領(かんとうかんれい)に就任し、足利藤氏(ふじうじ)(父は古河公方足利晴氏、母は簗田高助の娘)の公方擁立を画策します。この意を受けて簗田晴助は、足利藤氏、前関東管領上杉憲政(のりまさ)、関白近衛前久(このえさきひさ)を古河城に迎え入れました。関宿城にいた古河公方足利義氏は危険を感じ、これに先立って小金城(千葉県松戸市)に逃げています。 しかしながら、「川中島の戦い」が始まると、上杉謙信が関東から不在となり、古河城周辺の情勢が不安定となり、永禄5年(1562)になると、後北条氏は、古河城を取り戻し、一方関宿城は簗田氏の手に戻り、永禄元年の関宿城明け渡し以前の状態に戻りました。しかしながら、こうした一連の流れの中で、簗田氏は長らく保ってきた古河公方の家臣の地位を離れて、後北条氏・古河公方足利氏と直接渡り合うことになりました。 (村田憲一)
第205号(平成29年3月) 2017.3 ――――――――――――――――――――――――――――――――――― せきはく豆事典「関宿城主簗田氏(3) ―後北条氏と簗田氏―」 ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 簗田氏と古河公方足利氏とが血縁関係を基盤にした親密な関係にあったことは前稿で述べましたが、そこに介入してきたのが小田原の後北条氏(註参照)です。当時北条氏綱(うじつな)は、関東への勢力拡大を図り、関東管領(かんとうかんれい:古河公方を補佐する役目)の上杉憲政(のりまさ)と対立していました。そこで、関東進出の足がかりとするため、第3代古河公方足利高基(たかもと)に接近します。高基も、弟の義明が独立して小弓(おゆみ)公方を名乗り分裂状態にあったため、自己の権力保持のために北条氏の接近を容したようです。しかしながら、高基は天文4年(1535)に死去し、第4代古河公方には、嫡男の足利晴氏(はるうじ)が就任しました。 天文7年(1538)に第一次国府台(こうのだい)合戦がおこり、北条氏綱・氏康の北条軍と足利義明、里見義堯(さとみよしたか)、真里谷信応(まりやつのぶまさ)の軍が下総国相模台(しもうさのくにさがみだい:現千葉県松戸市)周辺で激突し、北条軍が勝利しました。 その結果、これまでとは情勢がまったく変わり、下総地方をほぼ勢力下におさめた北条氏綱は、古河公方足利晴氏に対し、自分の娘の芳春院(ほうしゅんいん)との婚姻を要請したようです。これに先立って、すでに天文4年(1535)に晴氏は、簗田高助の娘を娶(めと)っていましたが、勢力を拡大した後北条氏に脅威を感じていた晴氏は、芳春院を妻として受け入れざるをえず、翌天文8年(1539)には婚姻が成立しました。このことは、古河公方足利氏と特別な関係を築いてきた簗田氏にとっては安泰を揺るがす一大事となりました。 次いで、天文15年(1546)に武蔵国で河越合戦(かわごえかっせん:現埼玉県川越市付近にあった河越城周辺で行われた)が起きると、古河公方足利晴氏は、関東管領上杉憲政と同盟して後北条氏と戦いました。結果的には後北条氏の勝利に終わりましたが、この時の簗田氏の行動については、詳しいことはわかっていません。しかしながら、この戦いの直後簗田高助は出家し、子の晴助(はるすけ)に家督を譲っています。以後後北条氏と簗田氏の関係は一層緊迫したものとなっていきます。 天文21年(1552)、古河公方足利晴氏は、芳春院との間に生まれた梅千代王丸(うめちよおうまる:後の足利義氏)に家督を譲る書状を書いています。晴氏には先に娶った簗田高助の娘との間に正嫡の藤氏(ふじうじ)がいましたが、これを否定する形で、梅千代王丸に移譲しています。これは、晴氏の本心から書いたものではなく、後北条氏の意図によるものです。このことにより、後北条氏は、古河公方の外戚として高い地位を築いていた簗田氏を排除し、その地位を自分のものとし、事実上の「関東管領」として公方権力を手中にすることになりました。 このことは、簗田氏を筆頭とする公方家家臣団内部に大きな動揺を招くことになったようで、梅千代王丸は簗田晴助をはじめ有力家臣に領地をあてがっていますが、これも裏に後北条氏の意図が働いています。 (註)北条早雲を祖とする北条氏は、鎌倉幕府の執権を務めた北条氏とは傍系の遠い血縁関 係にあるものの、直接の後裔ではないため、後世の研究者が執権の北条氏と区別をす るために、早雲系の北条氏には「後」を付して後北条と呼んでいます。 (村田憲一)
第204号(平成29年2月) 2017.2 ――――――――――――――――――――――――――――――――――― せきはく豆事典 「関宿城主簗田氏(2) ―公方家足利氏の重臣となった簗田氏―」 ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 永享11年(1439)、第4代鎌倉公方足利持氏(もちうじ)は、不和であった関東管領の上杉憲実(のりざね)に攻められ、自害をしたため、鎌倉公方は一時断絶をしてしまいます。 しばらくした後、宝徳元年(1449)に足利持氏の子成氏(しげうじ)が第5代鎌倉公方となると、簗田満助の子持助(もちすけ)が奏者(そうしゃ:公方の取り次ぎ役)となりました。その後成氏は、戦乱(享徳の乱)のため、享徳4年(1455)に下総国古河(現茨城県古河市)に移り、初代古河公方となりました。 この頃から簗田氏は、古河公方足利氏の筆頭家臣として台頭してきます。これは単に簗田氏が水海(みずみ:現茨城県古河市)を本拠とし、下総国葛飾郡内の下河辺荘(しもこうべのしょう)の在地領主として治めてきた手腕を買われただけではなく、満助の代に娘が持氏の室となり、後に成氏を生んでいるという、公方足利氏との婚姻を介した血縁関係の深まりが大きく影響をしていると考えられています。また、足利満兼(みつかね)の名前の「満」の一字をもらって簗田満助と名乗ったと言われているように、公方家から偏諱(へんき:元服などの際に、将軍や大名などが家臣に自分の名前の一字を与えることで、名誉なこととされた)を得ており、次いで簗田持助は、足利持氏から「持」の字を賜り、同様にして、成助は成氏から、政助は政氏から、高助は高基から、晴助は晴氏から、と代々続きます。 こうしたことは、簗田氏が古河公方家の中で特別な存在であったことを物語っています。 簗田持助と成助は、古河公方の軍事を担当し、関宿城を本拠として、傍流の水海城も併せ、国衆クラス(政治的・軍事的に独立できず戦国大名などに従っている勢力)も支配下に置き、強力な軍事力を構築しました。 一方では、利根川水系及び常陸川水系を始めとする水上交通権も掌握し、品川から下河辺荘に至る水上交通のネットワークを築きました。むろんこれが経済的な面だけではなく有事の際の軍隊の移動など軍事的にも有効であったことは言うまでもありません。 その後、第2代古河公方となった足利政氏(まさうじ)と子の高基(たかもと)との間で内紛が起き、それが簗田政助(まさすけ)・高助父子へ波及し、政氏・政助に対する高基・高助という対立の構図が出来上がりました。これが、さらに関東管領家の上杉顕実(あきざね)・憲房(のりふさ)まで巻き込む内紛へと発展しましたが、結果的には高基・高助が勝利し、高基は第3代古河公方となり、高助は公方家臣の中で筆頭の地位を得ることとなりました。 さらに高助の娘は高基の子晴氏(はるうじ)に嫁ぐこととなりました。こうして、簗田氏は公方家と血縁関係を深めていく中で確固たる地位を築いていきました。 (村田憲一)
第203号(平成29年1月) 2017.1 ――――――――――――――――――――――――――――――――――― せきはく豆事典 「関宿城主簗田氏(1) ―簗田氏発展のルーツを探る―」 ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 簗田氏は、室町時代初期まで遡る武家で、もとは下野国簗田郡簗田御厨(しもつけのくにやなだぐんやなだみくりや:現栃木県足利市福富町)を本拠とする在地の小領主でした。足利氏の家臣でしたが、特別高い地位ではなかったようです。一説には、桓武平氏の流れをくむ平維茂(たいらのこれもち)の子良衡(よしひら)を祖とし、近江国久田郡(おうみのくにひさだぐん:現滋賀県長浜市余呉町)を本拠とし、義助の時に下野国簗田郡に移り、子の氏助の時から簗田姓を名乗ったといわれていますが、この説には検討の余地があります。 室町幕府が成立すると、関東を特に重視した幕府は、貞和5年(1349)に鎌倉に鎌倉府を置き、足利基氏(あしかがもとうじ)を初代鎌倉公方(長官)としました。この時に簗田氏は配下となりました。その後、第3代鎌倉公方足利満兼(あしかがみつかね)の代に、簗田助良(やなだすけよし)が「満」の字を拝領し、満助(みつすけ)と称したとも伝えられています。以後、鎌倉公方足利氏から1字拝領することが簗田氏の慣例となりました。 また、簗田満助の代には、それまでの本拠地であった簗田御厨から下総国葛飾郡内の下河辺荘(しもこうべのしょう:現千葉県北西部から埼玉県東部にかけて存在した荘園)に移り、水海(みずみ:現茨城県古河市)を本拠としました。 利根川東遷事業(中世末から近世初期にかけて行われた水上交通網の整備と江戸を水害から守り、さらに、水田を増やし米の収穫量を上げるための河川のつけ替え土木工事)が行われる以前のこの地域は、荒川・利根川・隅田川水系、渡良瀬川・太日川水系、鬼怒川・常陸川・香取海水系などの河川が入り組んでおり、これらを利用した水上交通の要衝であるとともに、洪水の多い地域でもありました。 同地域は、第2代鎌倉公方足利氏満(あしかがうじみつ)の時に鎌倉府の御料所(直轄地)として編入されたところで、似たような状況であった簗田御厨を治めてきた簗田氏の経験手腕を足利氏が見込んでのことと考えられています。 さらに、満助は自分の娘を第4代鎌倉公方足利持氏(あしかがもちうじ)の側室とし、鎌倉公方とのつながりを強固なものにしました。 しかしながら、持氏は第6代将軍足利義教(あしかがよしのり)と不和になり、永享10年(1438)に義教は関東へ討伐軍を送り、持氏を討つという「永享(えいきょう)の乱」が起こります。簗田一族発展の基礎を築いた満助でしたが、この最中に討死をしてしまいました。 (村田憲一)
第202号(平成28年12月) 2016.12 ――――――――――――――――――――――――――――――――――― せきはく豆事典 「柳田国男とツクマイ」 ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 『図志』は江戸時代末期に現茨城県利根町布川の医師・赤松宗旦が著した利根川中下流域の地誌ですが、後の民俗学者で『遠野物語』などの著者として知られる柳田国男(1875~1962)に大きな影響を与えたと言われています。それは柳田が、赤松宗旦の生まれ故郷である布川に少年の頃住んだことがあるからでしょう。 その布川に関連するものとして『図志』には、「布川(ふかわ)大明神(だいみようじん)帰輿(きよ)」と布川徳満寺の「地蔵市」が記されています。前者の祭礼では「ツクマイ」が行われていたとありますが、現在では布川大明神での開催はなく、一般には「つく舞い」というと野田市と竜ケ崎市で行われているものが知られています。野田では「津久舞」、竜ケ崎では「撞舞」とそれぞれ表記されますが、いずれも高い柱の上で曲芸的な舞を演じるものであり、語源は同じと思われます。また、その起こりについても、雨乞いや五穀豊穣を願う儀式から来ているようです。 野田の津久舞が組織的に行われるようになったのは明治時代からですが、昭和14年以降は中断され、同29年になって市の無形文化財として復活したそうです(現在は県指定及び国の選択無形民俗文化財)。復活を記念して、野田市興風会館に柳田国男を招き講演会が行われました。その記録が平成2年3月に野田市から発行された市制施行40周年記念記録写真集『遠ざかる風景』に収められています。柳田によると、「つく」は標柱のような「柱」のことであり、神や霊をお迎えするための印であろうということが述べられています。 現在、野田市では毎年7月中旬に一日だけ開催され、雨蛙の面を付けたジュウジロウが15mもの高さの上で舞う様子を見学できます。また、柱の先には白い布に覆われてはいますが醤油の樽が付けられるのが、いかにも野田らしく感じます。 (岡田光広)
第201号(平成28年11月) 2016.11 ――――――――――――――――――――――――――――――――――― せきはく豆事典 「関東平野の謎」 ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 人間の体の真ん中にはへそがあります。そのことから、その地域の中心地をへそという言葉で表現することがあります。では、関東地方のへそはどこでしょうか。 いろいろな意見がありますが、一般的には埼玉県久喜市栗橋~茨城県古河市あたりと言われることが多いようです。 古河市は、茨城県の西端に位置し、かつては、下総国・印旛県・千葉県に属しましたが、明治8年に茨城県に編入された、千葉県にとてもゆかりのある町です。当館からも直線距離で10km足らずですので、当館の4階展望室からもほぼ「へそ」から見たのと同じような景観を見ることができます。北東には、日本百名山では最も低い筑波山(877m)。また北西には、男体山(2,486m)を始めとする足尾山地・日光連山の山々、西方には、赤城山(1,828 m)・浅間山(2,568m)を中心とした上毛の山々、そして、南西には秩父連山~富士山(3,776m)を見ることができます。 また、平野の部分は関東平野と呼ばれ、日本最大の平野(約17,000平方メートル)と言われています。平野の部分の標高を見てみると、博物館のある関宿の西側、幸手~栗橋あたりが一番標高が低い事がわかります。一般的には川が海に向かって流れるように、山間部から沿岸部に向かってゆるやかな傾斜となっていくものですが、関東地方は平野の中心部が最も低く周辺部に向かってゆるやかに高くなっていくという盆地状の形状を示しているのが大きな特徴です。これは、関東構造盆地と呼ばれ、関東平野の中央部を中心にして沈降がおこり周囲の山地などが隆起する現象で、この運動によって台地や丘陵も形成されたと言われています。皆様もぜひ、関宿城から関東平野の広さを体感してください。 (谷鹿栄一)
第200号(平成28年10月) 2016.10 ――――――――――――――――――――――――――――――――――― せきはく豆事典 「利根川流域の行事と鮭」 ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 利根川流域では、そこに住んでいる人々や、水運従事者たちの信仰として、さまざまな祭りや民俗行事が行われました。 利根川下流部の印旛郡栄町の布鎌惣社水神社(ふかまそうしゃすいじんじゃ)では、昔秋祭りには、たくさんの御馳走が振舞(ふるま)われたそうです。その一つとして、このあたりの利根川流域で取れた鮭を使った料理があります。この鮭は、江戸時代、赤松宗旦(そうたん)が書いた『利根川図志』〈安政2年(1855)刊〉にも「利根川の鰱魚(さけ)は布川を以て最とす」とあるようにとてもおいしいと評判だったようです。また、現在の書籍でも、「利根川もこのあたりでとれる鮭は脂(あぶら)けがほどよく抜けてたいそう おいしい」とあります。 料理法としては、「身の部分を醤油と玉砂糖(赤い色の粗糖)で甘辛く煮つけたり、頭の部分を割っておし(味噌汁)の実にして食べたりする」などがあります。 また、利根川で漁が行われていた当時は、鮭をとるのにバカッピキ漁、(春にはウグイや鯉、スズキをとる春バカと、秋にも鮭をとる秋バカがある)という伝統漁法が盛んに行われていたそうです。ちなみに、そこで使われる網は投網(とあみ)と言って、当館でも郷土食講座「投網漁と川魚料理」で、実際の漁はしませんが、投網の打ち方を体験することが出来ます。 昭和30年ごろまで行われていた利根川の鮭漁は、高度経済成長期に水の汚濁(おだく)による水質の低下や、利根川改修工事における浚渫(しゅんせつ)工事などでの川砂利(じゃり)の採取等によって、鮭の遡上(そじょう)が激減(げきげん)し、行われなくなりました。そして、お祭りで食べるという風習も姿を消していきました。しかし、昭和50年代後半になると前橋市の市民団体をはじめ、群馬県や埼玉県が稚魚(ちぎょ)の放流を行ったり、埼玉県行田市と群馬県邑楽郡(おうらぐん)千代田町の県境にある利根大堰(おおぜき)では、魚が遡上できるように3本の魚道(ぎょどう)も装備されたため、徐々に遡上数は増え、平成25年度の調査では18,696匹と過去最高を記録しているそうです。(しかし、現在では資源保護のため禁漁となっています。) こういったことから、いずれ鮭漁も復活し、その昔おいしいと評判だった鮭が、祭礼のごちそうに加わり、また私たちの口に入る日が訪れると信じています。 (土井瑞穂)
第199号(平成28年9月) 2016.9 ――――――――――――――――――――――――――――――――――― せきはく豆事典 「暮らしと親水(その3)」 ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 現代では、海水浴などのスポーツ、渓流釣り、川辺の花火なども行われる傍ら、親水公園・海浜公園などの新たな癒しの親水空間も作られています。これらの公園は、1970年代から80年代にかけて全国的に広がった環境保全運動をうけ、政府や地方自治体、漁業者、研究者、環境団体、地域住民などさまざまな人々が協力し合ってつくられました。生態系を考えたビオトープ(疑似自然空間)を取り入れ、環境学習の一端も担っているものも多くあります。 また親水公園は、「まちづくり」「ふるさとづくり」として始まっており、住民が参加して公園を維持・管理しているところも多く、「公による安全な海・川づくり」から「自分たちの海・河川を自ら手入れする治水とそれを支える公」という構図が出来上がりつつあります。これは、人々の生活が「便利さ」から「豊かさ」へ変わったことの表れです。 そしてこれらの水辺の親水空間を利用したカヌーや和船、動力船の乗船体験、釣り体験、自然観察会などのイベントが多く行われるようになりました。様々な企業も、CSR(企業の社会的責任)活動として実施しています。また、川辺を楽しく散策するためのテラス整備に伴った店舗の進出や、コミュニティの場として親水空間を取り入れたマンションや商業施設の建設なども企業は行うようになっています。 川や海を利用した「利水」はかつてとは大きく変化しました。しかし、人々は再び水辺への親水意識を持って活動を起こし、それを自治体や企業が支えるようになってきています。このことは、我々が再び水との共存に向き合い、新たなる水との関わりに歩みを進めている証しといえるでしょう。 (鈴木敬子)
第198号(平成28年8月) 2016.8 ――――――――――――――――――――――――――――――――――― せきはく豆事典 「暮らしと親水(その2)」 ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 江戸時代は循環型社会として下水はきれいになっており、水辺のきれいな環境は維持されていました。大名は屋敷内の庭園の池などで、庶民は海辺や川辺で、ときには船に乗って花見や夕涼み、花火や月見を楽しみました。また、川沿いや海沿いは、見世物小屋や芝居小屋、水茶屋、花街などもでき、水辺は癒しの空間として広がっていきました。 一方で、水辺は被災者の供養と災害からの安全、豊漁・豊作を願い、多くの神社仏閣が建てられます。これらの建物は、後に観光地になっていきます。東京近郊から成田山や香取神宮・鹿島神宮などに向う人は江戸湾から船に乗り、船橋や行徳の湊から陸路で向かいました。船に乗り、水面をみながら移動することは、癒しになっていました。 江戸時代、人々は水辺の空間を楽しむだけでなく、干潟での潮干狩り、海や河川で釣り、水遊びなどと水に入ることも楽しむようになります。 そして明治期には、スポーツという意識とともに様々なウォータースポーツが入ってきます。武芸の泳法や療養として始まった水泳は、学校教育にも取り入れられる傍ら、海水浴は夏の暑さしのぎとして楽しまれました。時代が下るにつれ、海ではヨットやサーフィン、ジェットスキーなど、川ではカヌーなどが行われるようになっていきました。千葉県は三方を海に囲まれているため、現在では、マリンスポーツのメッカになっています。 またスポーツ以外にも、娯楽を兼ねた筏レースや近年様々な公園などで設けられる人口の池などでも幼児の水遊びなどもレジャーとして行われるようになっています。 昭和期の高度成長期頃になると、一時、河川や海の水質悪化による悪臭や公害により、人は水辺から離れます。しかし、政府や地方自治体、漁業者、研究者、環境団体、地域住民の努力によって水質は改善し、再び、川辺の花火や屋形船など水辺の空間は復活を遂げました。 (鈴木敬子)
第197号(平成28年7月) 2016.7 ――――――――――――――――――――――――――――――――――― せきはく豆事典 「暮らしと親水(その1)」 ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 人は水なしでは生きていけません。文明が発生した時から、人は海や川を利用し、生活を営んできました。飲料水や炊事・洗濯のために水を取水し、漁業を行い、農業用水を使い、舟を作り川や海を交通路として物資を運びました。 「水を制するものは、世界を制す」と言われるように、世の支配者たちは常に水の管理を行ってきました。徳川家康は江戸に拠点を置くに際し、物資を運ぶために湊を整備し、湊から城までの川を開削し、城を守るために堀を作ります。また上水道も完備し、明暦の大火(1657年)をきっかけに火除け地として庭園を造り、その中に消防用の池も作っていきます。造られた庭園の池では、それらの利用の他に、四季折々の景観も楽しみました。 水辺に住む人々にとって川や海は自然災害を起こす脅威ではありましたが、自分たちに利益をもたらすものでもありました。漁業や農業用水としての利用、舟を使った物資の輸送などをしていた人々にとって、海や川は身近なものであり、親しみのあるものでもありました。自然災害や水難事故から身を守るために神社を祀ったり、先祖供養の精霊流しなどの年中行事などを行うとともに、泳いだり、釣りをしたりと身近にある川や海は生活の一部でした。 明治時代になると、海や川の治水を政府が管理することになり、物資の輸送は、徐々に舟運から鉄道輸送の流れになります。舟運事業者が姿を消し、川を使った利水が減ったため、地域住民の持っていた川との共存意識が薄れていきますが、昭和の高度成長期頃までは、江戸時代頃から続く川や海の親水意識は存続します。 (鈴木敬子)
第196号(平成28年6月) 2016.6 ――――――――――――――――――――――――――――――――――― せきはく豆事典 「関宿藩主が就いた幕府の職制-寺社奉行-」 ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 「寺社奉行」(じしゃぶぎょう)は、江戸幕府の職制の中では、もともとは老中配下の職でしたが寛文2年(1662)以降は、老中や若年寄と同じ将軍直属の要職となりました。主な仕事は全国の寺院・神社及びその領地などの管理で、僧侶・神職をはじめ、陰陽師(おんみょうじ)・楽人(がくにん)・検校(けんぎょう)・連歌師(れんがし)や寺社領の領民などを支配し、領内での訴訟事(裁判)なども職掌としました。 本職は、1万石以上の譜代大名が就任することが原則でしたが、いわゆる「出世コース」の重要なポジションであり、5~10万石の譜代大名が任じられることも少なくありませんでした。定員は概ね4名で、自分の屋敷を奉行所とし、順番に月番で勤務しました。 関宿藩からは、板倉重郷(いたくらしげさと)【就任期間 万治元年(1658)~寛文元年(1661)】・久世重之(くぜしげゆき)【同 宝永元年(1704)~宝永2年(1705)】・久世広明(くぜひろあきら)【同 明和2年(1765)~明和6年(1769)】・久世広周(くぜひろちか)【同 天保14年(1843)~嘉永元年(1848)】と4人の藩主が就任しています。板倉重郷は寺社奉行を辞して間もなく亡くなりましたが、久世重之は、本職を経た後、若年寄、老中へと昇進しました。久世広明は、本職を経た後、大坂城代、京都所司代、老中へと昇進しました。久世広周も、本職を経た後、西丸老中、老中へと昇進しています。 なお、本職は、奏者番(そうじゃばん)に任じられた譜代大名のうちの上位者の兼職でした。奏者番というのは、江戸城での礼式を取り仕切る役職で、大名と将軍の取次役のような仕事です。この奏者番になることが譜代大名にとって、出世のための登竜門でもありました。 他に「奉行」と呼ばれる役職に、幕府の財政を管理する「勘定奉行」、江戸の治安や行政・司法を管轄する「町奉行」がありますが、これらは将軍直属ではなく老中配下であり、旗本の役職である点で、寺社奉行より若干格は下になります。 (村田憲一)
第195号(平成28年5月) 2016.5 ――――――――――――――――――――――――――――――――――― せきはく豆事典 「潮干狩りの歴史」 ――――――――――――――――――――――――――――――――――― ゴールデンウィークは終わってしまいましたが、3月下旬から始まった東京湾の潮干狩りはまだ楽しめそうです。そこで今回は潮干狩りについて書いてみることにします。 人々が貝を採った歴史と言えば、遠く縄文時代早期にまで遡りますが、レジャーとしての潮干狩りとなると、一般には江戸時代から始まるようです。 潮干狩りの様子は、江戸時代の浮世絵にも描かれています。初代歌川国貞の「汐干景」(文化12年(1815)~天保13年(1842)刊)や、初代歌川広重の「品川汐干の図」(安政2年(1855)刊)・二代目歌川広重の「江戸名所 品川沖汐干狩之図」(嘉永5年(1852)刊)などの他、比較的多くの浮世絵で潮干狩りの様子を見ることができます。 また、当館も所蔵する『江戸名所図会』(天保5年(1834)から7年にかけての刊行で、当時の名所案内のようなもの)にも「品川汐干」と題する画が描かれています。 これらに共通するのは、女性や子供が多く描かれていることです。潮干狩りが現代と同じように女性・子供でも安全に楽しめる行事だったことがわかります。その後、明治・大正・昭和と時代が変わっても、絵はがきなどに残された潮干狩りの様子は、江戸時代とあまり変わっていません。どれも着物の裾をまくって、夢中になっている様子を感じます。 潮干狩りの様子が大きく変わってしまったのは、東京湾では昭和40年(1965)頃からです。その頃から本格的に沿岸の埋立てが始まり、潮干狩りのできる場所が減少していきました。 ラムサール条約に登録された谷津干潟(やつひがた)も、昭和40年代までは海水浴や潮干狩りで賑わった海岸の一部です。当時は遊園地があり、そこから海に降りると、数キロメートル先まで干潟が広がっていました。『習志野市史別編民俗』によると、昭和50年(1970)には遊園地のビーチハウスの閉鎖と同時に海水浴・潮干狩りが中止になったと記されています。 (岡田光広)
第194号(平成28年4月) 2016.4 ――――――――――――――――――――――――――――――――――― せきはく豆事典 「ミシンと文明」 ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 和服から洋服に変わり始める明治時代、それを作るための道具、ミシンも日本にもたらされました。最初に日本に入ってきたのは、幕末、アメリカのペリー提督から13代将軍徳川家定への献上品だといわれています。家定の御台所である天障院が使用しました。民間では遣米使節団に通訳として同行したジョン万次郎(中浜万次郎)がアメリカより手回しミシンを土産として持ち帰っています。 明治時代になって、輸入の足踏みミシンが使われ始め、明治14年(1881)の内国勧業博覧会では、国産ミシンが展示されました。大正時代になり、足踏みミシンが量産されるようになり、工業用、家庭用ともに広く販売されました。高度成長期が到来する昭和30年代中頃から電動ミシンに変わるようになり、足踏みミシンは姿を消していきます。 ミシンが最初に発明されたのは、18世紀後期のイギリスです。18世紀から19世紀にかけて興った産業革命の頃で、19世紀には、アメリカで軍服を縫うために工場生産化に向けて開発されました。 西洋文明は、道具を改良し、大量生産を可能にする技術に長けています。それに対し、東洋文明は、シンプルな道具を使いこなす技術を身に付け、大量生産を可能にしてきました。当館の「昔のくらし展」で展示される昔懐かしいこの足踏みミシンを見ながら、西洋文明と東洋文明の違いなどに思いを馳せてみてはいかがでしょうか。 (鈴木敬子) |
メルマガ(平成28年度〜)
このページのお問い合わせ先
関宿城博物館