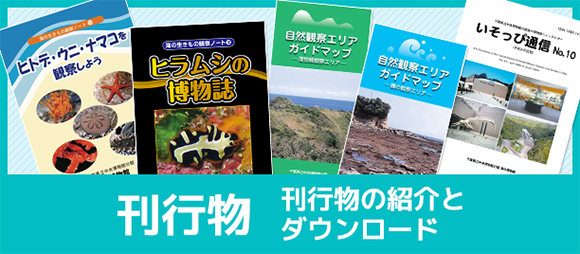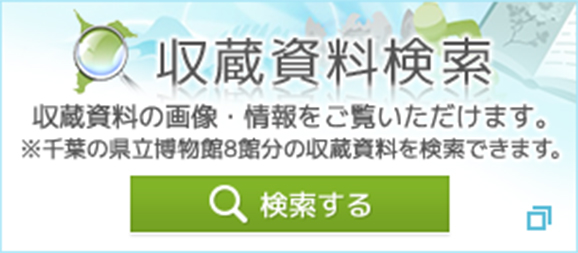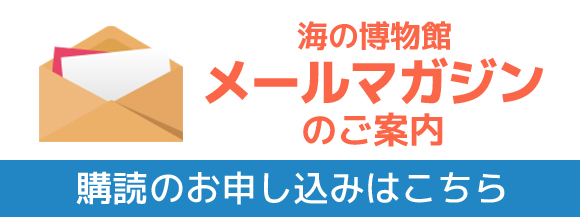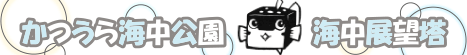概要
当館の柳研介主任上席研究員が一員となっている研究グループが、ヤドカリの「宿」を作るイソギンチャクの新種を日本沿岸の深海域から発見しました。本種の「特定のヤドカリとのみ共生する」という生態を、万葉集で「相手への強い気持ち」を表すために使われた言葉「桃花褐(つきそめ)」に例えて、ツキソメイソギンチャクParacalliactis tsukisomeと命名しました。この研究成果は、国際学術雑誌 Royal Society Open Science誌のオンライン版に本年10月22日付で公開されました。
新種「ツキソメイソギンチャク」について
私たちは、日本沿岸(三重県熊野灘及び静岡県駿河湾)の水深200~500mの深海から、ヤドカリの宿となる「巻貝のような形」を作る淡い桃色のイソギンチャクを発見しました。外部形態の観察や、組織学的手法を用いた内部形態の観察、刺胞のタイプ構成の分析、DNA塩基配列を使用した分子系統解析の結果、日本でこれまで発見されたことのなかったParacalliactis属に属する未記載種※ であることが判明しました。そこで本種をツキソメイソギンチャクParacalliactis tsukisomeと命名し、新種として発表しました。
さらに本種について、国内外の博物館や水族館の協力のもとで生態的な研究を進めたころ、以下のことが示唆されました。
①ツキソメイソギンチャクは、宿主であるヤドカリの糞などを食べている可能性がある。
②本種が一方向に動くことで「巻貝のような形」を作り出す可能性がある。
③本種との共生により宿主のヤドカリは、他の種よりも大きな体を獲得できている。
このようなヤドカリとイソギンチャクの共生生態を明らかにすることにより、イソギンチャクがヤドカリの宿となる「巻貝のような形」をつくる能力の進化的な原動力について議論することができました。本研究は、博物館や水族館による継続的な生物の収集と保管や、生物の出現に関する分類学的知見が、深海生物の未知の生態を明らかにするために非常に有効であることを示しています。今後、さらに深海生物の未知なる生態を明らかにしていくためにも、各研究機関での生物資料の収集がより活性化されていくことが期待されます。
※ 未記載種:学名の付いていない生物の種を「未記載種」と呼びます。そして本研究のように、論文にて名前を付けると初めて「新種」と呼ばれます。
掲載誌・論文タイトル
掲載誌 Royal Society Open Science(国際学術雑誌)
論文タイトル Mutualism on the deep-sea floor: a novel shell-forming sea anemone in symbiosis with a hermit crab.
URL https://doi.org/10.1098/rsos.250789
研究チーム
吉川晟弘(熊本大学)
泉貴人(福山大学)
神吉隆行(九州大学)
森滝丈也(鳥羽水族館)
北嶋 円(新江ノ島水族館)
大土直哉(東京大学)
木村妙子(三重大学)
勾玉暁(東京大学)
服部竜士(東京大学)
弓場茉裕(東京大学)
白井厚太朗(東京大学)
Michela L. Mitchell( Women’s and Children’s Health Network / The University of Adelaide)
藤田敏彦(国立科学博物館/ 東京大学)
柳研介(千葉県立中央博物館)
熊本大学のプレスリリースはこちら→熊本大学プレス資料