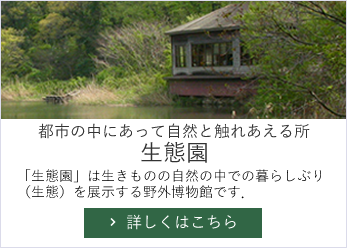動物
-
伊江島の海底洞窟から新属新種のテッポウエビを発見(2018.1.19)
[担当:駒井 智幸]
当館動物学研究科主任上席研究員の駒井と沖縄県立大学准教授藤田藤田喜久博士の共同研究により、沖縄諸島伊江島の海底洞窟からテッポウエビ科の新属新種が発見され、2018 年 1 月 8 日付けで学術雑誌「ズータクサ(Zootaxa)」に発表されました。
くわしくはこちら(473KB)(PDF文書) -
オオスナモグリは生きていた(2019.7.25)
[担当:駒井 智幸]
くわしくはこちら(5MB)(PDF文書)
NHK NEWS WEB で2019年6月5日に取り上げられました。
「“絶滅”の甲殻類 オオスナモグリか 干潟で発見」 https://www3.nhk.or.jp/news/special/sci_cul/2019/06/news/news_190605/(外部リンク)
「環境DNAでオオスナモグリ調査」
https://www3.nhk.or.jp/news/special/sci_cul/2019/06/news/news_190611-5/ (外部リンク) -
なぜ直接子どもを産むトカゲは出現したのか?(2020.8.13)
[担当:栗田 隆気]
当館生態学・環境研究科の研究員栗田隆気は、東邦大学研究員 児島 庸介、京都大学 准教授 西川完途、マレーシア・サラワク州森林局研究員 Mohamad Yazid Hossmanとの共同研究により、インドから東アジアにかけて生息するトカゲの仲間の生息環境、行動、繁殖様式の進化に関する研究を行い、「繁殖様式の進化が特定の生息環境と行動を基盤に生じている」という仮説を発表しました。本研究成果は、2020年8月13日に英国自然史博物館が刊行する学術誌「Systematics and Biodiversity」に掲載されました。
くわしくはこちら(600KB)(PDF文書) -
新種のヤドカリ「カイカタヒラテヤドカリ」を発見(2020.9.30)
[担当:駒井 智幸]
ホンヤドカリ科の新種Kumepagurus kaikata(和名新称:カイカタヒラテヤドカリ)を報告する論文がZootaxaにて2020年9月30日付けで公表されました。
くわしくはこちら -
新種のヒョウタンナガカメムシをマレー半島で発見(2022.1.5)
[担当:伴 光哲]
当館 伴 光哲研究員は、ヒョウタンナガカメムシ科のKanigara属について分類学的な検討を行い、マレーシアから新種 Kanigara nebulosaを、これまで本属の記録がなかったタイからK. punctataを、それぞれ報告しました。
本研究の成果は、2022年1月5日にシンガポール国立大学発行の動物学の雑誌「Raffles Bulletin of Zoology」にて公開されました。
くわしくはこちら(1017KB)(PDF文書) -
糞から調べる絶滅危惧種のトカゲの食べ物(2022.9.6)
[担当:栗田 隆気]
当館 栗田隆気 研究員と琉球大学熱帯生物圏研究センター 戸田守 准教授は、沖縄県に生息する絶滅が危惧されているヤモリの仲間のクロイワトカゲモドキ Goniurosaurus kuroiwae kuroiwae の食性に関する共同研究を行いました。この研究では、生体や個体群になるべく負荷をかけずに正確に食性を調査するための方法を検討するとともに、クロイワトカゲモドキがどのような餌を食べているのかを明らかにしました。本研究の成果は 2022 年 9 月 5 日に、オーストラリア連邦科学産業研究機構(CSIRO)が刊行する学術誌「Wildlife Research」にて Online Early で公開されました。
くわしくはこちら(823KB)(PDF文書) -
日本海若狭湾から新種スナモグリ類の発見 ―実験所すぐそばの海底から太平洋初記録の属―(2022.9.9)
[担当:駒井 智幸]
当館の 駒井智幸 動物学研究科長は、京都大学(京都府京都市)などの研究者との共同研究により、日本海の若狭湾でスナモグリ科 Callianassa属の新種(Callianassa ogurai:新称 ワカサスナモグリ)を発見しました。Callianassa属は、以前は世界中に分布するとされてきましたが、近年の研究により再検討され、現在では大西洋産の5種とインド洋産の1種に限定されていました。今回発見された新種は、形態比較と分子系統解析によりヨーロッパ産の本属種C. subterraneaに最も近縁であることが判明しました。本属に帰属する種の太平洋域からの初めての発見となります。本研究成果は、2022年9月8日付で国際学術誌「Zootaxa」で公表されました。
くわしくはこちら(1405KB)(PDF文書) -
沖合海底自然環境保全地域から新種のエビを発見(2023.2.10)
[担当:駒井 智幸]
当館の 駒井智幸 動物学研究科長は、沖合海底自然環境保全地域に指定された西マリアナ海嶺の深海生物の調査で採集された標本を研究し、テナガエビ科ホンカクレエビ属の新種 Periclimens variabilis(新称:ウスベニシンカイカクレエビ)を発表しました。本研究の成果は令和 5 年 1 月 31 日に「Zootaxa」にて公開されました。
くわしくはこちら(5MB)(PDF文書) -
海岸の”砂利”に潜むテッポウエビ類の新種を発見! 礫浜の間隙環境に生息するコエビ類を日本から初報告(2023.4.5)
[担当:駒井 智幸]
当館の 駒井智幸 動物学研究科長と東京海洋大学の研究グループは、海岸の砂利に生息するテッポウエビ科の新種 Metabetaeus lapillicola(和名新称:サザレオハグロテッポウエビ)を発見しました。
海岸の砂利(礫浜の間隙環境)に生息するコエビ類が発見されたのは日本初です。この発見により、これまで生物の生息に不向きだと考えられてきた礫浜が、重要な生息環境であることが示されました。
この成果は、2023 年 3 月 29 日付の国際学術雑誌 Zootaxa 誌で公開されました。
くわしくはこちら(978KB)(PDF文書) -
エビの巣穴に住む新種のエビを発見(2023.4.26)
[担当:駒井 智幸]
当館の駒井 智幸 動物学研究科長と琉球大学の研究グループは、沖縄本島において、アナエビ類の巣穴に共生するカギテシャコエビの新種を発見しました。スナモグリ類以外のエビと共生するカギテシャコエビは初めての確認です。
この研究成果は、2023 年 4 月 21 日付の国際学術雑誌 Zootaxa 誌で公開されました。
くわしくはこちら(1176KB)(PDF文書) -
若狭湾から新種テッポウエビ類の発見 ―貴重な抱卵メス1個体―(2023.5.10)
[担当:駒井 智幸]
当館の駒井 智幸 動物学研究科長と京都大学の研究グループは、日本海の若狭湾からテッポウエビ科の新種を発見し「ワカサムラサキエビ」と名付ました。
本種は1年間の調査で1個体しか採取されていませんが、昨年も若狭湾からはエビ類の新種「ワカサスナモグリ」が発見されており、日本海には未知なる生物多様性があると考えられます。
この成果は、2023 年5月2日付の国際学術雑誌 Zootaxa 誌で公開されました。
くわしくはこちら(566KB)(PDF文書) -
沖合海底自然環境保全地域から2新種を含む ワラエビ上科甲殻類4種を発見(2023.6.1)
[担当:駒井 智幸]
千葉県立中央博物館 駒井智幸 動物学研究科⻑と海洋研究開発機構 深海生物多様性研究グループ 土田真二博士・藤原義弘博士による共同研究グループは、2020年に実施された沖合海底自然環境保 全地域の調査で採集されたワラエビ上科甲殻類の研究結果を発表しました。
4種が報告され、そのうちの2種が新種、2種が日本近海から始めて記録されました。今回の研究において発見された種 は全てこれまでに日本周辺海域からは記録のなかったもので、沖合海底自然環境保全地域の生物相 の解明に向けた今後の調査・研究の展開が期待されます。
本成果は、2023年5月19日にニュージーランドの国際学術誌「Zootaxa」にオンライン掲載されました。
くわしくはこちら(1381KB)(PDF文書) -
沿岸魚類群集の種間相互作用強度の温度感受性(2023.8.4)
[担当:宮 正樹]
当館の宮正樹主任上席研究員を中心とする研究グループは,房総半島から得られた海水サンプル中の魚類DNA(環境DNA)を分析し,魚類群集における魚種間の関係性を検出することに成功しました。さらに,魚種間の関係性の強さが温度感受性をもつことも明らかにしました。これは,地球温暖化が個々の種だけでなく生物群集にも大きな影響を与えることを示しています。
本研究の成果は2023年7月11日に国際誌「eLife」で公開されました。
くわしくはこちら(1580KB)(PDF文書) -
千葉県から新種のカメムシ「キヨスミチビナガカメムシ」を発見!(2023.11.14)
[担当:伴 光哲]
当館の伴 光哲共同研究員(当時:当館研究員)は、千葉県南部の清澄山の周辺から新種のカメムシを発見し、「キヨスミチビナガカメムシ Stigmatonotum macronotum」と名付けました。カメムシの和名に千葉県の地名に由来する名前がつくのは初めてのことです。
本研究の成果は2023年10月27日に昆虫分類学の国際誌である「Acta Entomologica Musei Nationalis Prague」にて公開されました。
くわしくはこちら(793KB)(PDF文書) -
房総半島のみで採集 勝浦市と鴨川市の磯から新種のエビを発見(2023.11.21)
[担当:駒井 智幸]
当館の駒井 智幸 動物学研究科長は、勝浦市と鴨川市の磯でヒメサンゴモエビ科トゲツノモエビ属の新種を発見し、「ボウソウトゲツノモエビ」 と名付けました。本新種は、房総半島以外では採集例がなく大変貴重な種です。
この研究成果は、2023 年 11 月 1 日に国際学術雑誌 Zootaxa で公開されました。
くわしくはこちら(292KB)(PDF文書) -
駿河湾から新属・新種のカクレエビ類を発見-初記録!ウミユリ類のトリノアシに共生-(2024.1.12)
[担当:駒井 智幸]
当館の駒井 智幸 動物学研究科長とサンシャイン水族館の研究グループは、静岡県駿河湾から、テナガエビ科カクレエビ類の新属・新種を発見しました。このエビは、深海に生息するウミユリの仲間トリノアシに付着していたことから、「トリノアシヤドリエビ」と名付けられました。トリノアシに共生する甲殻類は初めてで、学術的に非常に貴重な発見となります。
この研究成果は、2023年11月30日に国際学術雑誌Zootaxaで公開されました。
詳しくはこちら(1055KB)(PDF文書) -
琉球列島における爬虫類の一新種〜やんばる固有の新種ヤンバルトカゲモドキ〜(2024.3.1)
[担当:栗田 隆気]
当館の 栗田 隆気 研究員と琉球大学熱帯生物圏研究センター 戸田 守 准教授は、沖縄県に生息する絶滅が危惧されているヤモリの仲間のクロイワトカゲモドキの分類に関する共同研究を行いました。本研究では沖縄島北部および古宇利島の個体群と沖縄島中南部。屋我地島、瀬底島、および伊江島の個体群が形態的・遺伝的に識別できることを示し、前者を新種として分割、記載しました。
本研究の成果は 2024 年 2 月27日付けで日本爬虫両棲類学会(HSJ)刊行の国際学術誌「Current Herpetology」にて公開されました。
くわしくはこちら -
房総半島沖の浦賀水道・相模湾から新種のアナエビ類を発見(2024.4.3)
[担当:駒井 智幸]
県立中央博物館(千葉市)の駒井智幸地域連携課長は、房総半島沖の浦賀水道・相模湾からアナエビ科カイメンヤドリアナエビ属の新種を発見し、「ビャクガンヤドリアナエビ(白眼宿穴蝦)」と名付けました。
カイメンヤドリアナエビ属はいずれも深海に生息し、キヌアミカイメン類の群体を住処に利用することが知られています。当該海域からはすでに本属の2種が報告されていましたが、DNA解析により新種の存在が明らかとなりました。
この研究成果は、2024年3月8日に国際学術雑誌Zootaxaで公開されました。
詳しくはこちら -
若狭湾と相模湾から新種テッポウエビ類「アカムラサキエビ」と「ワカサムラサキエビ」の雄個体を発見(2025.2.18)
[担当:駒井 智幸]
県立中央博物館(千葉市)の駒井 智幸 地域連携課長と京都大学フィールド科学教育研究センター 邉見由美 助教との共同研究グループは、若狭湾と相模湾の海底から新種のテッポウエビ類を発見し、「アカムラサキエビ Athanas acudactylus」と名付けました。
また、2023年に発見された新種「ワカサムラサキエビ Athanas exilis」は、雌1個体しか発見されていませんでしたが、この雄個体を発見しました。雄のワカサムラサキエビは、雌とは異なる大きな葉状の鉗脚(ハサミの脚)を持ち、雄雌で著しく形態が異なることが明らかになりました。
この研究成果は、2025年2月3日に国際学術雑誌Zootaxaで公開されました。
詳しくはこちら -
型破りな傾奇者のドウケツエビ新種 「カブキドウケツエビ」を発見(2025.4.18)
[担当:駒井 智幸]
県立中央博物館の駒井智幸 地域連携課長 兼 研究課長と 沖縄美ら海水族館 魚類課の東地拓生氏との共同研究グループは、2014年8月に沖縄で行った深海調査により、新種のドウケツエビを発見しました。
ドウケツエビ属の仲間は世界中で 13種 が知られていましたが、本新種は半透明の体に赤い線の模様や、槍の穂先のような形をした額角を持つほか、ツノサンゴ類の内部を生息場所とするなどの特徴があります。その型破りな生態から「カブキドウケツエビ(傾奇(歌舞伎)洞穴蝦)」と名付けました。
この研究成果は、2025年3月3日に国際学術雑誌 Zootaxaで公開されました。
詳しくはこちら -
深海の謎を解き明かす革新的な手法の開発 深海頭足類の多様性評価に新たな扉(2025.4.30)
[担当:駒井 智幸]
当館の駒井智幸(地域連携課長 兼 研究課長)と宮正樹(元主任上席研究員)が参加している共同研究グループは、水中に放出された生物由来の微量なDNA「環境DNA」を解析することで、頭足類(主にイカやタコの仲間を含む生物群)の存在を迅速かつ効率的に検出する技術を確立しました。
これにより、北西太平洋の水深200~2,000 mの深海域から、ダンゴイカのような小型種からダイオウイカのような超巨大な種まで多様な頭足類のDNAの検出に成功しました。知られざる深海の生態系を理解する新たな手段として、今後さらに発展することが期待されます。
本研究成果は2025年4月15日に、国際学術誌「Marine Environmental Research」に掲載されました。
詳しくはこちら -
県内中学生が千葉県初記録となる魚を発見し、 学術論文を発表(2025.5.13)
[担当:分館海の博物館 川瀬裕司]
鴨川市の中学生が漁港の岸壁で採集した魚が、千葉県初記録で分布北限記録となるクラカケエビス(イットウダイ科)であることがわかり、学術雑誌「Ichthy(イクチィ)」で発表されました。
中学生は分館海の博物館(勝浦市)の研究員に指導を受けながら、採集した魚の形態的な特徴を自分で観察・計測して、本種であることを明らかにしました。当館では、房総半島周辺に生息する海の動植物の標本を網羅的に収集してきましたが、これまでに本種の記録はありません。この標本は千葉県産魚類の多様性を示す貴重な資料として、当館で登録・保管しています。
分館海の博物館では、5月17日(土)から、研究内容の概要とクラカケエビスの液浸標本を、トピック展示として紹介します。
詳しくはこちら
-
新科・新属・新種のイソギンチャクを発表 〜海の中に屹立する富士山!?〜(2025.8.5)
[担当:分館海の博物館 柳研介]
分館海の博物館の柳研介主任上席研究員が一員となっている研究グループは、駿河湾・相模湾等から採集された異形のイソギンチャクを、新科・新属・新種として発表しました。その外見から「ウミノフジサン」と名付けられた本種は、イソギンチャクの中でも極めて珍しい形態を多数有しています。この成果は、本年6月19日付の国際学術雑誌 Diversity誌で公開されました。
【ウミノフジサンの特徴的な点】
・通常のイソギンチャク類で6対12枚あるはずの完全隔膜と呼ばれる隔膜が、本種では10枚しかない。※1
・触手が3本からなるユニット構造となっており、触手の生えない場所がある等、イソギンチャクとしては極めて異質な形態を持っている。
・収縮すると体は非常に扁平で中央にかけて徐々に盛り上がり、横から見ると富士山の姿を連想させる。※1 イソギンチャクの体の内部は、2枚で1対となる隔膜が多数配列することにより区分されている。
【掲載論文】
掲載誌 Diversity(国際学術雑誌), 17(6), 430.
論文タイトル Mt. Fuji in the Ocean–Description of a Strange New Species of Sea Anemone, Discoactis tritentaculata fam., gen., and sp. nov. (Cnidaria; Anthozoa; Actiniaria; Actinostoloidea) from Japan, with the Foundation of a New Family and Genus.
リンク https://doi.org/10.3390/d17060430詳細解説(準備中)
-
生物の進化を島が支える -シマクイナが明かす、日本列島が大陸集団の存続を支える仕組み- (2025.11.18)
[担当:小田谷 嘉弥]
当館の 小田谷 嘉弥 研究員が参加した共同研究グループは、ユーラシア大陸東部と日本の湿地に生息する絶滅危惧種の鳥・シマクイナの進化の歴史を解明し、日本列島の集団が大陸の集団の個体数や遺伝的多様性を「支える源」になったことを明らかにしました。本成果は、日本列島という一見すると大陸よりも小さな自然環境であっても、長い生物の歴史では大陸規模の進化や生物多様性の維持に重要な役割を担うことを示すもので、日本の自然の持つ価値を改めて浮き彫りにしました。
この研究成果は、2025年8月25日にJournal of Biogeography誌でオンライン公開されました。
詳しくはこちら
-
ブルネイでヤモリの新種を発見 (2025.12.11)
[担当:栗田 隆気]
当館の 栗田 隆気 研究員が参加した共同研究グループは、東南アジアで多様化しているマルメスベユビヤモリ(Cnemaspis属)の仲間を初めてボルネオ島北部のブルネイ・ダルサラーム国内で発見し、ホシマルメスベユビヤモリ Cnemaspis gituenとして新種記載しました。これまでマルメスベユビヤモリ類は、主にボルネオ島の西部において多く知られる一方、その他の地域の分布状況には不明な点が多かったことから、同島北部からの発見と生息環境の報告は、ボルネオ島におけるマルメスベユビヤモリ類の種多様性を解明するうえで重要な成果です。
この研究成果は、2025年12月4日に国際学術雑誌Zootaxaで公開されました。
詳しくはこちら
-
新種発見 ヤドカリの「宿」を作るイソギンチャク 〜万葉集に詠まれた「相手への気持ち」が学名に〜 (2025.10.22)
[担当:分館海の博物館 柳研介]
分館海の博物館の 柳 研介 主任上席研究員が一員となっている研究グループは、ヤドカリの「宿」を作るイソギンチャクの新種を日本沿岸の深海域から発見しました。本種の「特定のヤドカリとのみ共生する」という生態を、万葉集で「相手への強い気持ち」を表すために使われた言葉「桃花褐(つきそめ)」に例えて、ツキソメイソギンチャク Paracalliactis tsukisomeと命名しました。この成果は、国際学術雑誌 Royal Society Open Science誌のオンライン版に2025年10月22日付で公開されました。
詳しくはこちら
(2025年12月25日追記)
この成果が、科学誌『Nature』が選ぶ「November’s best science images」に選出されました。
『Nature』はロンドンを拠点に設立された国際的な総合科学学術雑誌で、世界で最も権威のある科学雑誌のひとつです。『Nature』では毎月、科学的独創性・学術的価値・視覚的インパクトのすべてを備えた研究を「best science images」 として厳選して紹介しています。これに選出されることは、当該研究成果が国際的に高い注目と評価を受けたことを表します。詳しくはこちら
-
ハゼも「ミステリーサークル」をつくる? サキンハゼが巣の周りに放射状構造を形成する行動を解明 (2026.1.14)
[担当:分館海の博物館 川瀬裕司]
潜水調査と水槽実験により、浅い砂泥底に生息する小型のハゼ科魚類の一種であるサキンハゼの雄が、巣の周りに放射状の溝とクレーター状のくぼみを形成することを明らかにしました。
小さなフグが海底に精巧な円形幾何学模様の「ミステリーサークル」を建設して繁殖に利用していることが発見されて世界を驚かせましたが、今回、全く別の分類群のハゼがフグとは異なる方法で巣の周りに「小さなミステリーサークル」をつくって繁殖していることを解明しました。この研究成果は、2026 年1月9日に、スイスのオンライン科学雑誌Fishes で公開されました。
詳しくはこちら
-
大規模環境DNA調査から沿岸魚の分布を決める要因を探る ー魚類相を形成する複雑な海流の働きが明らかにー(2026.02.17)
[担当:後藤 亮]
千葉県立中央博物館の研究員が参加した共同研究グループは、日本全国528地点に及ぶ大規模な環境DNA調査を実施しました。その結果、沿岸魚1,220種、現在報告されている種の約44%に上るDNAを検出し、これらの大半の種の分布に共通して影響を与える要因として、様々な海流の働きが明らかになりました。この成果は、日本の沿岸魚類の生物多様性に関する理解を深めるとともに、将来の沿岸魚類の分布変化の予測に役立つことが期待されます。
本研究成果は、2026年2月16日にScientific Reports 誌でオンライン公開されました。
詳しくはこちら