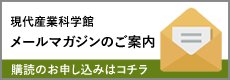千葉県立現代産業科学館研究報告
千葉県立現代産業科学館研究報告第31号 (2025年3月)
|
山崎恵美子・小笠原淳・鈴木淳一・齋藤純徳・河野隆一郎・佐俣憲範 |
|
| 2. プラネタリウム上映会における事前決済による座席予約システムの導入について | 重黒木誠・井上翔太郎 |
千葉県立現代産業科学館研究報告第30号 (2024年3月)
| 1. 報告 千葉県誕生 150 周年記念事業 令和5年度企画展「はかる」について |
山崎恵美子・鈴木淳一・髙橋真希子・大野将史・鈴木愛子・佐俣憲範 |
| 2. 千葉県誕生150周年を記念したプラネタリウム番組の制作について | 竹本勇一 |
千葉県立現代産業科学館研究報告第29号 (2023年3月)
| 1. 報告 令和4年度企画展「ネジる ツナガる -モノ×ネジ×ヒト-」について |
堀内裕子・鈴木淳一・家田 隆・井上嘉隆・鈴木愛子・倉内郁子 |
| 2. 令和4年度プラネタリウム上映会について | 竹本勇一 |
千葉県立現代産業科学館研究報告第28号 (2022年3月)
| 1. 報告 令和3年度企画展「カ・ラ・ク・る -歯車が伝える動き-」について |
佐俣憲範・荒井喜代美・家田 隆・髙橋真希子・村田憲一・金田幸代 |
| 2. オンラインを活用したプラネタリウムについて | 神野智尚 |
| 3. 千葉県における近代理数教育の幕開け―千葉師範学校旧蔵の明治前期教科書をめぐって― | 山口友樹 |
| 4. 千葉県立現代産業科学館における来館者サービス―これからの展示解説員に求められるものとは― | 梅原妙子 |
| 5. 展示物・展示入力装置を理解するためのマイコン制御学習講座に関する研究 | 家田 隆 |
千葉県立現代産業科学館研究報告第27号 (2021年3月)
| 1. 新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る学芸課の対応について |
屋代 卓 |
| 2. 新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る普及課の対応について-「おうち」シリーズの発信を中心にして- | 神野智尚 |
| 3. 主体的な学びへと繋げる補助的な実験器具の在り方 | 小島邦夫 |
千葉県立現代産業科学館研究報告第26号 (2020年3月)
| 1. 報告 令和元年度千葉県立現代産業科学館企画展 開館25周年記念企画展「潜水-水中の科学・技術・仕事-」について |
佐俣憲範・植野百代・今泉 潔 ・服部貴之・金田幸代・屋代 卓 ・黒田祐子 |
| 2. 一般向け公開講座の開発 | 青栁裕之 |
| 3. 開館25周年記念 プラネタリウム上映会「軌跡-今振り返る6作品-」について | 堀井康弘 |
千葉県立現代産業科学館研究報告第25号 (2019年3月)
| 佐俣憲範・森恭一・植野百代・金田雅成・石渡克彦 | |
| 2. 一般向け公開講座の開発 | 青栁裕之 |
| 3. 科学館わくわく教室利用促進のための効果的な運営 | 金子直哉 |
| 4. 常設展示場の展示映像システムの維持と変遷 | 川端保夫 |
| 5. 低年齢層における「プログラミング的思考」育成のための研究 | 黒田祐子 |
| 6. 松の資源-松根油製造の軌跡をたどる- | 渋谷さゆり |
千葉県立現代産業科学館研究報告第24号 (2018年3月)
| 1.報告 平成29年度千葉県立現代産業科学館 企画展「ちばの発酵」について | 山崎恵美子・高山輝雄・伊藤亮・石渡克彦・上野純司 |
| 2.平成29年度プラネタリウム上映会 「星のある風景」3作品について | 八代賢一 |
| 3.「光のスペクトルメーター」を用いた実験講座の研究および新規演示実験への導入 | 黒田祐子 |
| 4.来館者増につながる広報活動の事例考察 | 河西敦史 |
| 5.現代産業科学館で「食べる」を考える -平成30年度企画展の概要- | 森恭一 |
千葉県立現代産業科学館研究報告第23号 (2017年3月)
| 1.報告 平成28年度 千葉県立現代産業科学館 特別展「出発進行~もっと・ずっと・ちばの鉄道~」について | 石井俊正・伊藤亮・黒田祐子 |
| 2.鉄道のしくみの理解を助ける演示実験や工作の研究 | 須賀伸吾 |
| 3.千葉の発酵・醸造産業の調査 | 東畑宏之 |
| 4.「伝えたい千葉の産業技術 100選」の調査 | 村井克行 |
千葉県立現代産業科学館研究報告第22号 (2016年3月)
| 1.報告 平成27年度千葉県立現代産業科学館 企画展「最先端ネットワークのかたち」について | 竹内洋子・佐々木善裕・森恭一・石井俊正・伊藤亮・川端保夫 |
| 2.現代産業科学館の,中学校理科授業への活用について | 東畑宏之 |
| 3.「伝えたい千葉の産業技術 100選」の調査 | 村井克行 |
| 4.常設展示場「先端技術への招待」~スーパーカミオカンデ関連展示の更新をとおして~ | 生井敏昭 |
| 5.報告 広報媒体を有効活用するための事例考察-平成27年度の事例をもとに- | 石渡克彦 |
| 6.千葉県立現代産業科学館における来館者サービス-展示解説員としてできること- | 篠崎満理佳 |
千葉県立現代産業科学館研究報告第21号 (2015年3月)
千葉県立現代産業科学館研究報告第20号 (2014年3月)
| 1.千葉県の産業遺産とその活用を考える -3か年にわたる講座の実施を通じて- | 小笠原永隆 |
| 2.報告 平成25年度千葉県立現代産業科学館特別展「飛べ!大空に-とばすワザ とぶフシギ-」について | 長尾諭・冨澤弘・鈴木淳一・大木正之・上野純司・原田裕章 |
| 3.報告 平成25年度千葉県立現代産業科学館収蔵資料展「みてみて!ふ・し・ぎ?」について | 竹内洋子・金田幸代・鈴木淳一・生井敏昭 |
| 4.演示実験・工作教室での教材開発について~「ふりこ」「地震」「ろうそくの科学」の実演を通して~ | 生井敏昭 |
千葉県立現代産業科学館研究報告第19号 (2013年3月)
| 1.産業遺産の活用に向けての一考察 -講座「千葉県の産業遺産とその活用を考える」の実施を通じてー | 小笠原永隆 |
| 2.現代産業科学館サイエンスドームの活用について -特にプラネタリウムと大型映像を中心として- | 小笠原永隆 |
| 3.当館のカメラコレクションについて(その3) <資料1> <資料2> <資料3> |
金田幸代 |
| 4.平成24年度千葉県立現代産業科学館企画展「宇宙へのきぼう」について | 小池正樹・岩﨑正彦・長尾諭 |
| 5-1.平成24年度千葉県立現代産業科学館企画展「未来へつなぐエネルギー~いま 走り出した つくる ためる つかう 技術~」について | 今関文章・岩﨑正彦・冨澤弘・金田幸代・尾﨑晃 |
| 5-2. 付遍.千葉県における天然ガスの開発と生産の経緯 | 尾﨑晃・長尾諭・小池正樹 |
千葉県立現代産業科学館研究報告第18号 (2012年3月)
| 1.明治以降の千葉県における砂鉄採取について | 植野英夫 |
| 2.千葉県立現代産業科学館におけるプラネタリウム上映会について | 古山茂和・筒井道広 |
| 3.地域資源としての産業遺産の活用について-講座「千葉県の産業遺産とその活用を考える」の実施を通じて- | 小笠原永隆 |
| 4.大型映像の現状と今後の展開について-本館におけるサイエンスドーム活用可能性を中心として- | 小笠原永隆 |
| 5.魅力ある科学工作教室のために-女性サイエンスパフォーマー養成プロジェクトに参加して- | 佐藤裕子 |
| 6.平成23年度千葉県立現代産業科学館企画展「さぐれ!月を 惑星を」の取組と評価 | 金子俊郎・阿由葉司・今関文章・小池正樹 |
| 7.平成23年度千葉県立現代産業科学館企画展「わたしとロボット-くらしをささえるRT(ロボットテクノロジー)-」について | 岩﨑正彦・今関文章・金田幸代・日根野達也 |
| 8.平成23年度千葉県立現代産業科学館企画展「帰ってきた小惑星探査機『はやぶさ』-ちばから宇宙へ-」について | 小池正樹・金子俊郎・今関文章 |
| 9.千葉県立現代産業科学館の新しい常設展示「アルゴブロック」-幼児から大人までのプログラミング学習- | 今関文章 |
千葉県立現代産業科学館研究報告第17号 (2011年3月)
| 1.千葉県立現代産業科学館における教育普及事業の今後のあり方 | 石井久隆 |
| 2.産業遺産の活用と現代産業科学館の役割について -特に「産業観光」の観点から- | 小笠原永隆 |
| 3.千葉県立現代産業科学館の教育資源を生かした学習支援のあり方-電磁気領域を中心として- | 岩﨑正彦 |
| 4.企画展「とびだせ!宇宙へ」の取組と評価(平成22年度企画展) | 乙竹孝文・岩﨑正彦・阿由葉司 |
| 5.企画展「みる!みえる?-錯視から探る視覚のしくみ-について」(平成22年度企画展) | 金田幸代・金子俊郎・小池正樹 |
千葉県立現代産業科学館研究報告第16号 (2010年3月)
| 1. 教育用レゴマインドストームNXT○Rを活用した科学館における学習プログラムの開発【2】 | 小原一成・石井久隆 |
| 2.報告 平成21年度千葉県立現代産業科学館企画展「もっと星がみたい-望遠鏡とスーパープラネタリウム-」の取組と評価 | 金子俊郎・乙竹孝文・市之瀬啓之・遠山俊夫・金田幸代 |
| 3.デジタル技術による古典写真技術の再現について | 中松満始 |
| 4.当館のカメラコレクションについて(その2) 1. 2. 3. 4. | 豊川公裕 |
| 5.motion captureを使用した身体技能の記録・保存方法について | 乙竹孝文 |
千葉県立現代産業科学館研究報告第15号 (2009年3月)
| 1 教育用レゴマインドストームNXT○Rを活用した科学館における学習プログラムの開発 | 小椿清隆・石井久隆・吉野健一 |
| 2 報告 平成20年度千葉県立現代産業科学館「企画展 宇宙への夢 ‐星空へのあこがれと日本実験棟『きぼう』‐」 1. 2. | 小原一成・佐々木猛・金子俊郎 |
| 3 報告 平成20年度千葉県立現代産業科学館企画展 現代発明物語「ものづくりへの夢と情熱」への取組と評価 | 金子俊郎・佐々木猛・小原一成 |
| 4 報告 平成20年度千葉県立現代産業科学館企画展 現代発明物語「ものづくりへの夢と情熱」関連イベント | 佐々木猛・金子俊郎・小原一成 |
| 5 収蔵資料を活用したサイエンスドームギャラリーの展示と収蔵資料の管理について | 川端保夫・金田幸代・豊川公裕 |
| 6 「ものづくりの原点‐最古のハイテク 石器製作‐ | 橋本勝雄 |
千葉県立現代産業科学館研究報告第14号 (2008年3月)
| 1 現代産業科学館における体験活動について | 小椿清隆・石井久隆・立和名明美・吉野健一 |
| 2 報告 平成19年度千葉県立現代産業科学館企画展 「新エネルギー 風・太陽・大地 -あすの地球のためにー」 | 根本憲一・川端保夫・金田幸代・佐々木猛・豊川公裕 |
| 3 報告 平成19年度千葉県立現代産業科学館企画展プラネタリウム「星の降る夜」 -大平貴之の世界と宇宙への夢ー1. 2. | 金子俊郎・山崎恵美子・川端保夫 |
| 4 主任技術員との連携による展示場における新演示実験の解説1. 2. | 小原一成・黒田登志郎・井上勝・酒見征男・綿貫博亮・酒井英夫・中桐一 |
| 5 「博物館と学校教育」-学校教育に生かせる博物館の利用をめざして-」 | 小椿清隆 |
| 6 「理工系博物館における生物教育プログラムの研究」-冷凍保存法及びサーモビジョンによるコオロギの孵化観察- | 石井久隆 |
| 7 当館収蔵のカメラコレクションについて1. 2. 3. | 豊川公裕 |
千葉県立現代産業科学館研究報告第13号 (2007年3月)
| 1 博物館施設の多目的利用とプラネタリウム上映会の意義 | 吉野健一・橋本勝雄・中松満始 |
| 2 報告 平成18年度千葉県立現代産業科学館企画展「未来へ走るクルマとエコ」 | 佐藤公昭・阿由葉司・佐藤 仁・山崎恵美子・川端保夫 |
| 3 サイエンスパートナーシッププロジェクトの実施報告と今後の課題 | 佐藤 仁・坂本 永 |
| 4 今世紀の科学系博物館論-その課題と提言- | 新 和宏 |
| 5 科学系博物館資料としての工業製品カタログに関する考察 | 坂本 永 |
| 6 効果的なサイエンスショーについての研究 | 佐藤 仁 |
千葉県立現代産業科学館研究報告第12号 (2006年3月)
| 1 報告 平成17年度千葉県立現代産業科学館企画展「ハッピーベンリー‐ITがむすぶ人と未来‐」1、2、3、4 | 佐藤公昭・植野英夫・立和名明美・成島善夫・川端保夫 |
| 2 当館における大型映像の足跡と今後 | 佐藤 仁 |
| 3 故青木國夫著作物及び収集文献コレクションについて1、2、3、4、5、6、7、8、9 | 植野英夫 |
| 4 博物館における工業資料の保存・管理について‐科学技術分野の重要文化財指定に関連して‐ | 高木博彦 |
| 5 ヨーロッパの科学館の現状 | 佐藤 仁 |
千葉県立現代産業科学館研究報告第11号 (2005年3月)
| 1 科学館におけるバイオテクノロジーの展示化【2】 開館10周年記念企画展「バイオテクノロジー―生命のしくみを生かす技術―」開催について | 植野英夫 川端保夫 坂本永 芳野英博 長坂喜郎 奥山謙二 成島善夫 |
| 2 資料紹介 原川電気店資料 | 植野英夫 |
| 3 複合素材からなる文化財の活用に関する調査研究 グレート・ブリテン及び北アイルランド連合王国の科学博物館の活動を中心として | 亀井修 |
| 4 科学館収蔵品にみる規格と業界標準 | 落合昭雄 |
千葉県立現代産業科学館研究報告第10号 (2004年3月)
| 1 教育普及活動における連携事業について | 星野正信・土野 茂 |
| 2 友の会活動の充実を図る方策に関する研究-他館の友の会やNPO法人の活動を参考にして- | 佐藤 仁・渡貫 健・山口 剛 |
| 3 平成15年度特別展「スポーツの科学」の開催と評価について | 佐藤 哲・成島善夫・川端保夫・鵜沢和良・松丸敏和・佐藤公昭・長坂善郎・芳野英博 |
| 4 第11回千葉県立美術館・博物館合同企画展「鉄づくり今昔」について | 芳野英博・坂本 永・鵜沢和良・佐藤 哲 |
| 5 千葉県近代和風建築総合調査の実施について-その2 | 坂本 永・川端保夫・佐藤公昭・成島善夫・鵜沢和良・芳野英博・松尾克宏 |
| 6 小学生のための見学ワークシートの作成とその活用 | 佐藤 哲・長坂喜郎 |
| 7 理工系博物館のおける科学教育プログラムの開発-光を題材にした科学と生活との関連を図るためのストーリーづくり- | 松丸敏和 |
| 8 非接触ICタグ(RFID)を用いた博物館資料の管理-予察- | 高木博彦 |
| 9 バイオリテラシーの育成-生物教育と科学館の可能性- | 佐々 義子 |
千葉県立現代産業科学館研究報告第9号 (2003年3月)
| 1 千葉県立現代産業科学館と大韓民国国立中央科学館の友好協定の締結と「日韓市民交流フェスティバル2002」における展示会について | 田代 資二・渡邉 博典・山口 剛 |
| 2 教育普及活動における実験教材の体系化と教育実践 -工作クラブ・サイエンス教室・出前実験・科学の祭典の中から- | 土野 茂・渡貫 健・森澤雅夫・星野正信 |
| 3 平成14年度特別展「ROBOT-人とロボットの未来」の開催と評価について | 大山光晴・鵜澤和良・川端保夫・松丸敏和・渡邊 誠・在原 徹 |
| 4 平成15年度特別展「スポーツの科学」に関する資料調査 -スポーツ用具の科学・環境保全とスポーツに重点を当てて- | 佐藤 哲・難波幸男・川端保夫・鵜沢和良・渡邊 誠・桜田秀樹 |
| 5 千葉県近代和風建築総合調査の実施について | 坂本 永・川端保夫・佐藤 哲・鵜澤和良 |
| 6 博物館における環境学習について -エコキットの試行と活用を中心に- | 難波幸男・佐藤 哲 |
| 7 千葉県立現代産業科学館における教員研修の現状と課題 | 片岡 登喜子 |
| 8 科学講座における揚力をテーマにした教育プログラムの研究と開発 | 松丸敏和 |
| 9 オーストラリアの科学系博物館の展示・教育活動について -サイエンスワークス・ミュージアムとオーストラリア国立科学情報センター- | 在原 徹 |
| 10 バイオコミュニケーション -市民の視点から情報提供のあり方を考える- | 佐々 義子 |
| 11 シューズに関する工学的研究と課題 | 福岡 正信 |
千葉県立現代産業科学館研究報告第8号 (2002年3月)
| 1 博物館における環境問題の展示について | 林勉・難波幸男・西博孝・松丸敏和・佐藤哲 | |
| 2 連携事業のあり方についての考察 | 片岡登喜子・福地和夫 | 17 |
| 3 平成13年度特別展「スペース21・宇宙への招待」について | 松丸敏和・鵜澤和良・佐藤哲・大山光晴・在原徹・亀井修 | 23 |
| 4 展示・イベントへの参加体験を重視した事業展開 -平成13年度科学体験フェスティバル- | 渡貫健・土野茂・渡邉博典・山口剛 | 33 |
| 5 展示・運営協力会サイエンスショーについて | 櫻田秀樹・佐藤哲・松丸敏和 | 53 |
| 6 人間と機械との新しい関係を探る -平成14年度特別展「ROBOT」に関する資料調査報告- | 大山光晴・坂本永・亀井修 | 63 |
| 7 博物館展示評価 -展示場でのケーススタディにフォーカスして- | 亀井修・大山光晴・佐々木秀彦 | 75 |
| 8 東京芸術大学美術学部で使用された写真計測システムの保存修復 | 亀井 修 | 85 |
| 9 科学教育の国際的動向 | 笠 耐 | 95 |
千葉県立現代産業科学館研究報告第7号 (2001年3月)
| 1 インフォ-マル・エデュケ-ションとしての科学博物館の役割 | 難波幸男・西 博孝・亀井 修・大山光晴 |
1 |
| 2 千葉県立現代産業科学館における広報活動の現状と課題 ―アンケ-ト調査から― | 田代資二・森澤雅夫・渡邊博典 | 15 |
| 3 展示・講座・イベントの関連を強化した事業展開 -平成12年度夏休み科学体験フェスティバル- | 大村 尚・井上隆夫・渡貫 健 | 25 |
| 4 平成12年度特別展「万国博覧会の夢」について -万国博覧会の展示化- | 櫻田秀樹・君島健治・西 博孝・亀井 修 | 43 |
| 5 千葉県立美術館・博物館合同企画展「房総ロマン紀行-写真で見る産業・交通遺跡-」および関連事業について | 難波幸男・小仲居啓・在原 徹 | 61 |
| 6 資料解説の一手法としての体験活動の試み -平成13年度特別展「スペ-ス21・宇宙への招待」- | 松丸敏和・難波幸男・大山光晴 | 75 |
| 7 一般市民の期待や危惧を持つ新しい科学技術に関する展示モデル形成についての考察 -バイオテクノロジ-に関する特別展の調査を通して- | 牛島 薫 | 93 |
| 8 ミュ-ジアム・リソ-スと入館者数の関係 | 亀井 修 | 107 |
| 9 博物館と学校教育との連携 | 鳩貝太郎 | 113 |
| 10 20世紀の情報技術を支えた電子管技術 ―日本無線株式会社製電子管を中心にして― | 亀井 修・西 博孝 | 119 |
千葉県立現代産業科学館研究報告第6号 (2000年3月)
| 1 | 21世紀の産業技術博物館における展示と教育の展開について -新たなる視点を求めて-千葉県立現代産業科学館総合研究その2- |
高安礼二・難波幸男・西博孝・亀井修 | 1 |
| 2 | 映像ホールの利用拡大を図る | 鍋島隆・星野正信・村松伸弘・大村 尚 | 11 |
| 3 | 展示事業の評価について -平成11年度特別展「サイエンス&アート」の評価を通して- | 牛島薫・渡邉博典・小仲井啓・亀井修・西博孝 | 19 |
| 4 | 平成12年度特別展「万国博覧会の夢-万博に見る産業技術と日本-」に関する調査研究 | 櫻田秀樹・君島憲治・亀井修 | 33 |
| 5 | 現代産業科学館における千葉県産業・交通遺跡調査 -千葉県産業・交通遺跡実態調査に続く追加調査および関連資料調査について- |
在原徹・小仲井啓・渡邉博典 | 49 |
| 6 | リモートセンシングの原理とその展示化について | 大野英彦・難波幸男・井上隆夫 | 61 |
| 7 | 博物館における評価に関する一考察 -経営の評価を中心として- | 牛島薫 | 67 |
| 8 | 常設展示の一つであるペルチェ素子を使った温度差発電の教材開発 | 金子俊郎・片岡登喜子・渡貫健 | 79 |
| 9 | 青少年の教育と博物館の役割 | 吉武弘喜 | 83 |
千葉県立現代産業科学館研究報告第5号 (1999年3月)
| 1 | 21世紀の産業技術と科学博物館における展示の展開について -新たなる視点を求めて-千葉県立現代産業科学館総合研究その1- |
高安礼士・難波幸男・西博孝・牛島薫 | 1 |
| 2 | 科学博物館における教育普及活動について -身近なサイエンス教室の実施を通じて- |
鍋島隆・河原英治・小原一成・村松伸弘・金子俊郎 | 11 |
| 3 | 現代社会に影響を与えた科学技術 -大量生産黎明期の人物の展示を中心として- |
亀井修・在原徹・櫻田秀樹・西博孝 | 17 |
| 4 | 館・学・産連携による参加型展示の研究開発について -企画展示「人と石油」を通して- |
小野禮子・難波幸男・井上隆夫・牛島薫・大野英彦・小原一成 | 23 |
| 5 | 千葉県立現代産業科学館における教育普及活動の現状と課題 -アンケート調査から- |
実川純一・井谷芳明・鈴木淳一 | 39 |
| 6 | 科学館における芸術一アートの展示化について 平成11年度特別展「サイエンス&アート」- |
西博孝・渡邉博典・牛島薫 | 47 |
| 7 | 万国博覧会の日本における展開について | 高安礼士・君島憲治・片岡登喜子・亀井修・櫻田秀樹 | 53 |
| 8 | 公立博物館と民問企業等との協力についての一考察 -新しい博物館の活動の形を探る- |
高安礼士 | 65 |
| 9 | エッフェル塔・錬鉄使用の背景について | 片岡登喜子 | 71 |
| 10 | 経済史・技術史的にみた第一回万国博覧会 | 見市雅俊 | 79 |
千葉県立現代産業科学館研究報告第4号 (1998年3月)
| 1 | 産業技術の伝搬と継承の視点による万国博覧会と科学博物館の研究 -千葉県立現代産業科学館総合研究その3- |
高安礼士・西博孝・片岡登喜子・亀井修 | 1 |
| 2 | 広報の活動状況について | 反町恆昭・實川純一・村松伸弘 | 13 |
| 3 | 科学館におけるバイオテク鴻Wーの展示化 -平成9年度特別展「20世紀のバイオテクノロジー」-バイオ発見!くらしに活きる生命たち-開催について- |
牛島薫・井上隆夫 | 19 |
| 4 | 平成9年度企画展示「サイエンスで遊ぶ-イメージと錯覚の世界-」の開催について | 西博孝・難波幸男 | 33 |
| 5 | 平成10年度特別展20世紀の産業I「大量生産:エジソンとフォードその時代」実施に関する研究 | 亀井修・在原徹 | 47 |
| 6 | 平成10年度企画展示について | 大野英彦・難波幸男 | 55 |
| 7 | アイマックス・ドーム映写システムの特殊性と普及拡大について | 山本照道・井谷芳明 | 61 |
| 8 | 千葉県産業・交通遺跡実態調査会の運営について | 在原徹・田代資二・鈴木淳一・河原英治 | |
| 9 | 「現代産業の歴史」部門における解説シートの作成とその利用状況について | 大野英彦・片岡登喜子 | 77 |
| 10 | 展示解説について | 宮下朋子・小島和子・後藤真知子・清澤里枝・新田貴子・宮崎りか・岡本奏・安田美由紀・小倉恵美子 | 91 |
| 11 | エンジンと自動車 -その人々の歴史:ホイヘンスの火薬エンジンからT型フォードまで- |
田代資二・亀井修・在原徹 | 107 |
| 12 | 県立博物館職員の研修体系についての一考察 | 高安礼士 | 123 |
| 13 | 特別展事業の作業項目と分担方法について | 川端保夫 | 131 |
千葉県立現代産業科学館研究報告第3号 (1997年3月)
| 1 | 産業技術の伝搬と継承の視点による万国博覧会と科学博物館の研究 -千葉県立現代産業科学館総合研究その2- |
高安礼士・西博孝・村松二郎・亀井修 | 1 |
| 2 | 平成8年度特別展「エレクトロニクス通信展一ためして知ろう!通信のきのう・きょう・あした一」について | 川端保夫・村松二郎・井上隆夫・大野英彦・亀井修 | 13 |
| 3 | 平成8年度企画展示について | 林勉・根本憲一・大野英彦・鈴木淳一 | 23 |
| 4 | 特色ある教育普及活動の実施運営 | 渡邊誠・小原一成・在原徹 | 31 |
| 5 | 科学技術博物館の新しい役割の一考察 | 高安礼士・亀井修 | 39 |
| 6 | UndergroundとMetroporitana | 田代資二 | 47 |
| 7 | 史料を用いた工業教育実践への一考察:写真資料の保存と利用の視点から | 亀井修 | 53 |
| 8 | 千葉県立現代産業科学館設備の概要について | 江口修 | 61 |
| 9 | 近世日本における酒造技術の形成過程 -伊丹の酒造りを中心にして- |
鎌谷親善 | 83 |
千葉県立現代産業科学館研究報告第2号 (1996年3月)
| 1 | 大量生産技術の歴史的研究その1 -千葉県立現代産業科学館総合研究その1- |
高安礼士・鈴木道男・白石稔・村?郎・亀井修 | 1 |
| 2 | 平成7年度特別展「ふしぎ体感!!マジカル・サイエンス」開催にかかる手順と今後の他県類似館との共同企画の可能性 | 川端保夫 | 11 |
| 3 | 平成7年度企画展示について | 牛島薫・小泉敏文・白石稔・根本憲一・鈴木淳一 | 19 |
| 4 | 千葉県立現代産業科学館における教育普及活動の現状と課題 -アンケート調査から- |
糸賀憲治・実川純一・村松伸弘 | 25 |
| 5 | 常設展示更新のための活動報告 -展示運営協力会の活動を通して- |
田代資二・林勉・村松二郎・関口定雄・根本憲一・鈴木淳一 | 31 |
| 6 | 電圧印加状態下でのせっけん膜の塩濃度変化に対する安定性 | 河原英治 | 37 |
| 7 | 岡部金次郎のマグネトロンの復元模型製作に関わる研究 | 関口定雄 | 43 |
| 8 | 公立博物館における博物館活動の計画法の一考察 -平成7年度文部省委託事業を例に- |
高安礼士 | 49 |
| 9 | 千葉県立現代産業科学館におけるアートマネージメントの出発 | 高田洋一 | 61 |
| 10 | テレビ国産化初期の歴史 -受像機キーパーツ開発を中心として- |
高橋雄造 | 77 |
千葉県立現代産業科学館研究報告第1号 (1995年3月)
千葉県立現代産業科学館の設立の経緯と今後の方向性| 発刊によせて | |||
| 1 | 千葉県立現代産業科学館の設立の経緯と今後の方向性 | 1 | |
| 2 | 調査・研究について | 7 | |
| 3 | 常設展示 「現代産業の歴史」部門 |
池田文彦 | 13 |
| 「先端技術への招待」部門 | 鈴木道男 | 25 | |
| 「創造の広場」部門 (1)創造の広場展示製作の過程 (2)放電実験室展示製作の過程 |
牛島薫 | 31 | |
| 4 | 平成6年度特別展 | 池田文彦・牛島薫・川端保夫・小泉敏文・関口定雄 | 51 |
| 5 | 平成6年度企画展 | 牛島薫・白石稔・田代資二・林勉 | 61 |
| 6 | 人形劇の実施につト | 小泉敏文・高橋弘 | 67 |
| 7 | 科学情報コーナー利用の傾向 | 亀井修・小松登志雄 | 73 |
| 8 | 千葉県工業の発展に見る特殊と普遍 | 高安礼士 | 79 |
| 9 | 情報処理支援システムの構築 | 亀井修 | 99 |
| 10 | エネルギーと環境問題 | 佐藤正弥 | 105 |
| 11 | 「はかる」計器の由来を探る (その1)精密目盛りの原点と広がり | 松本栄寿 | 113 |